エンジニアの挑戦
富士ソフトだからこそ提案できる最適解を。富士ソフトのエンジニアの、仕事にかける想いや技術への挑戦に迫ります。
タグで絞り込む
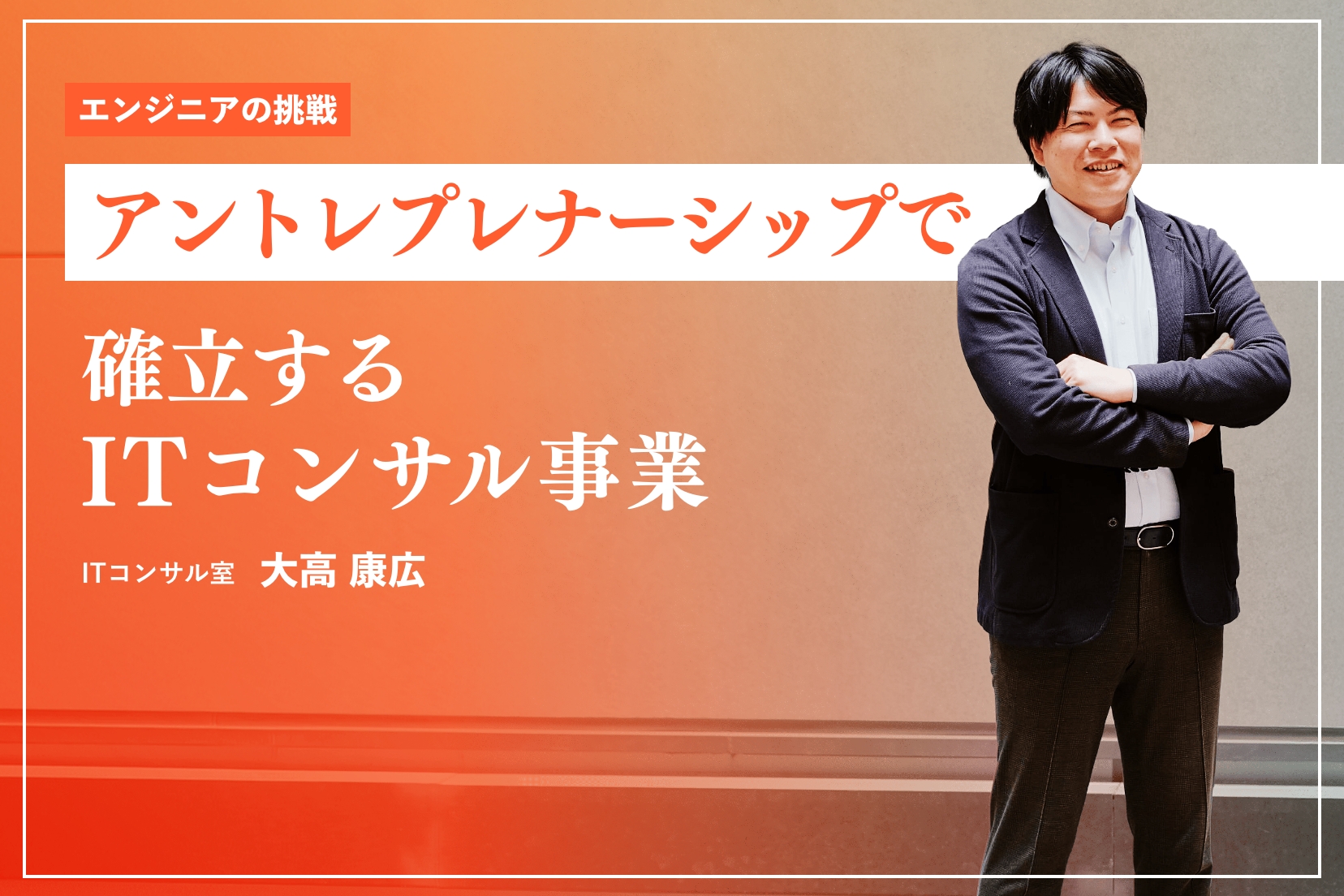
エンジニアの挑戦
2025年8月28日

エンジニアの挑戦
2025年7月31日

エンジニアの挑戦
2025年7月15日

エンジニアの挑戦
2025年5月16日
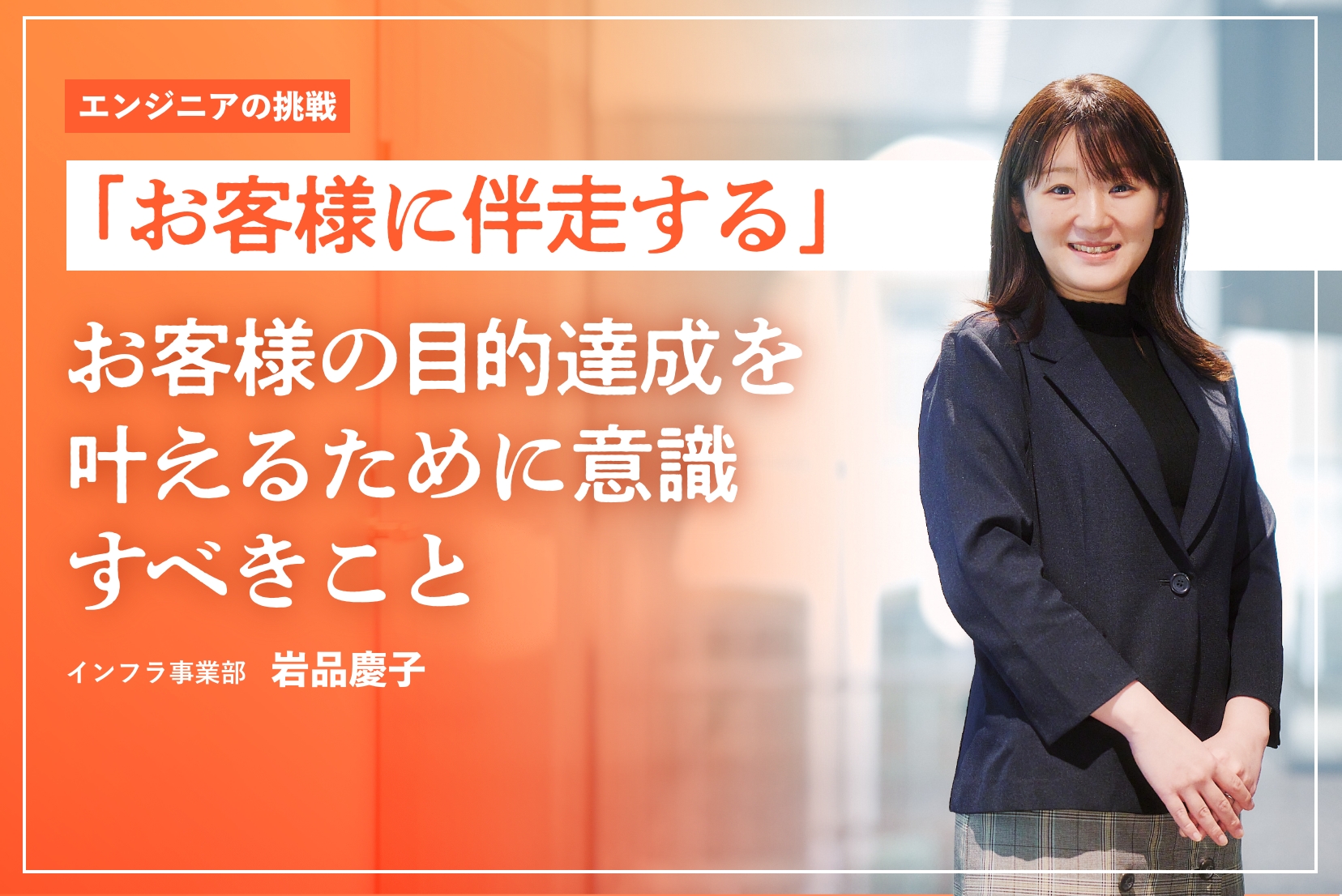
エンジニアの挑戦
2024年12月10日

エンジニアの挑戦
2024年11月18日
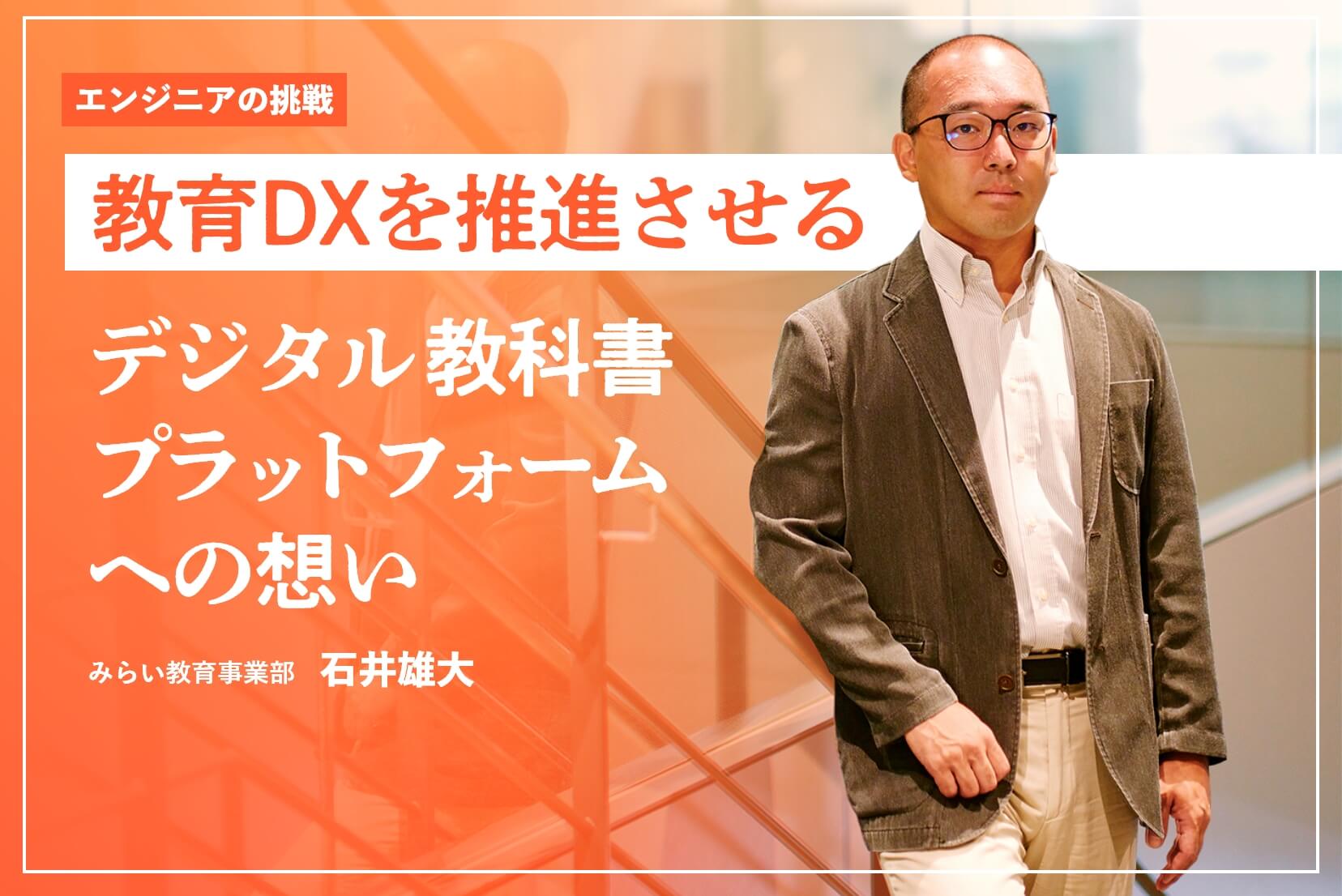
エンジニアの挑戦
2024年9月6日
タグで絞り込む
すべてのタグを見る話題の記事

エンジニアの挑戦
2025年7月15日

エンジニアの挑戦
2025年7月31日

エンジニアの挑戦
2025年5月16日
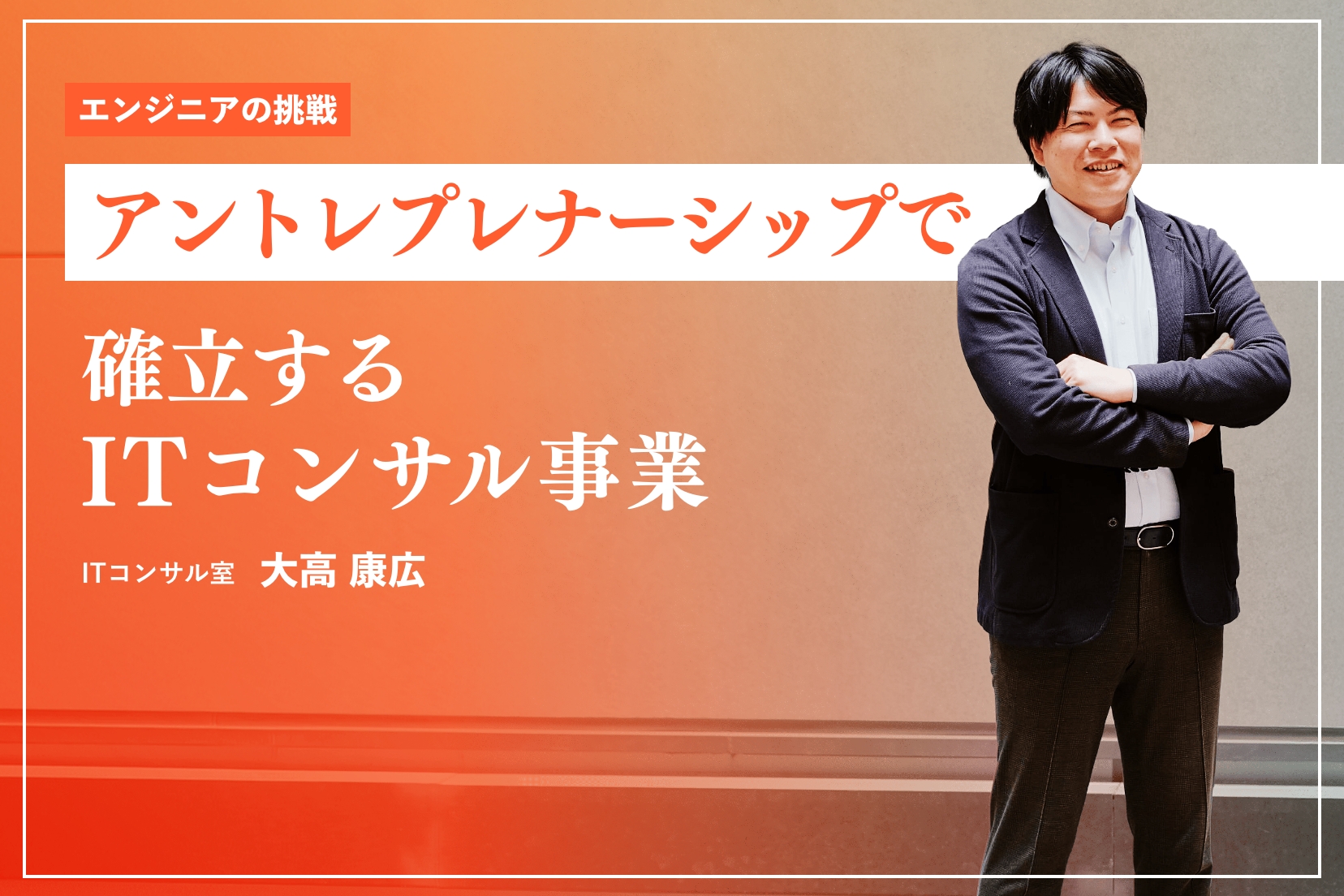
エンジニアの挑戦
2025年8月28日



