アントレプレナーシップでITコンサル事業を確立し、SIerならではの価値提供で差別化を図る
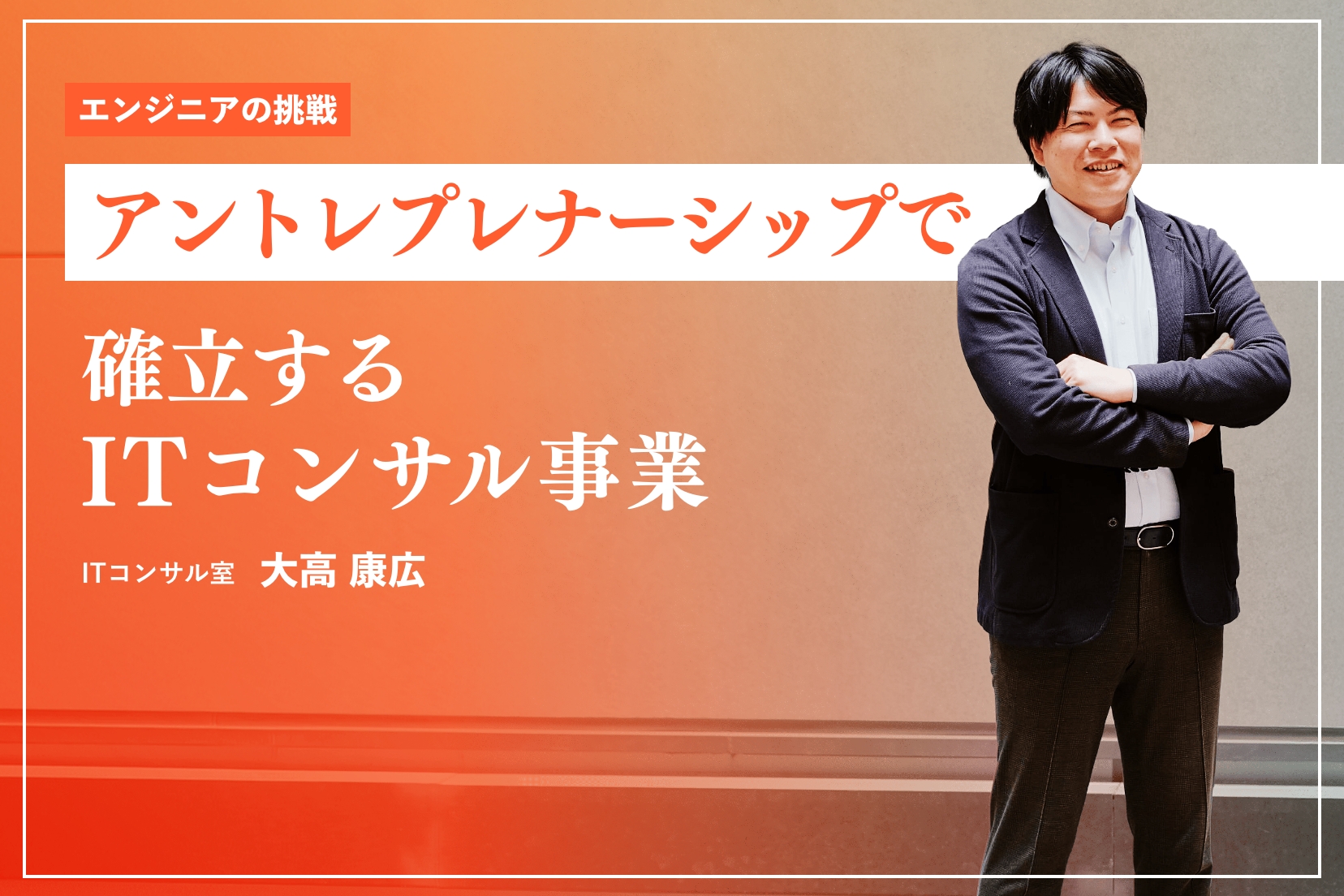
社会一般にDXが推進されていくなかで、企業にとってはITソリューションの最適化が課題となっています。多くのソリューションが市場に溢れており、自社に適したサービスを選ぶことが難しくなっているのです。富士ソフトではこうしたお客様のニーズに対応すべく、2024年に、幅広い技術領域で活躍してきた人材を集めた「ITコンサル室」を、拡大・増員しています。本記事では、顧客提案からサービス設計、サービス提供までを一貫して担っているITコンサル室の大高 康広に話を聞き、現在の取り組み状況とともに、組織での実践を目指す、サービスや事業に対して主体的に取り組み自ら創り上げていく、アントレプレナーシップ(起業家精神)についてもご紹介します。
-
 大高 康広ITコンサル室
大高 康広ITコンサル室
主任2006年に中規模のソフトウェア開発会社へ新卒入社し、大手クレジットカード会社向け業務システムの開発に従事。10年以上にわたり、金融業界向けのシステム開発に携わり、業務知識と技術力を磨く。
2017年に富士ソフト株式会社へ転職後は、引き続き大手クレジットカード会社のシステム開発に携わり、プロジェクトマネージャーとして複数の案件を推進。顧客との折衝や要件定義、ソリューション提案など、上流工程を中心に担当。
2024年には社内公募制度を活用し、金融事業本部フィナンシャルIT事業部クレジットシステム部からITコンサル室へ異動。これまでの開発・マネジメント経験を生かし、より戦略的なITコンサルティング業務に従事。
社内公募からITコンサル室へ
──富士ソフト入社からITコンサル室配属となった経緯を教えてください。

私は2006年より中規模のソフトウェア会社で、クレジットカードのシステム開発に携わっていました。前職では二次受けの立場だったため、上流工程に関わる機会がなく、プロジェクトマネジメントへの関心が高まるなかで物足りなさを感じていました。
そうした背景から、一次受けとして要件定義などの上流工程にも携われる当社に魅力を感じ、2017年に転職をしました。さらに有給休暇の取得促進や育児休業の活用など、働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでいた点も、入社を決めた大きな理由の1つです。入社後の7年間は、クレジットカードシステムの開発・運用に従事し、2024年には社内公募を通じてITコンサル室に異動。現在はその部所で業務に取り組んでいます。
──なぜITコンサル室を選んだのでしょうか。
クレジットカード分野にとどまらず、より幅広い業界で上流工程の課題解決に取り組みたいという思いが芽生えたことが、異動を希望した理由です。前の部門ではプロジェクトマネージャーとして、お客様に対してITソリューションの提案を行っていました。提案したソリューションを導入し、お客様に喜んでいただける経験を重ねるなかで、「もっと多様な業界・課題に向き合いたい」という気持ちが次第に強くなってきたのです。
また、ITコンサル室が新設されたばかりの部門であり、組織の立ち上げから拡大に貢献したいという思いも、異動を決意する大きな後押しとなりました。
新領域に身を置くことで得られた成長
──ITコンサルティングというとイメージしにくいのですが、携わったプロジェクトや業務内容を紹介してください。
ITコンサルティングは、企業や組織が情報技術(IT)を活用して業務の効率化、課題解決、競争力の強化を図るために、専門的な助言や支援を提供するサービスです。
私が担当した大手金融企業のシステム基盤移行プロジェクトをご紹介します。ITコンサルタントとして要件定義フェーズから参画し、業務課題の分析を通じて、クライアントに最適な要件定義を実施しました。設計以降は当社技術部門が開発を担当する体制となり、私はPMOとしてプロジェクト管理を担いました。開発チームと同一組織内での連携であることから、進捗状況や課題をリアルタイムで把握し、品質管理・スケジュール調整を効率的に実施できました。また要件変更や仕様調整にも社内で迅速に対応できた結果、計画通りのシステム移行を実現することができたのです。
PMOを設置することで、複雑かつ高難度なプロジェクトでも、全体の可視化と統制が可能となり、安定した運営と成果につながることを実感しました。

──異動後の業務について、感じたことはありますか。
今までのプロジェクトマネージャー経験から、プロジェクト管理や運営において大きな戸惑いはありませんでしたが、ITコンサルタントとして求められる学習スピードの違いを強く実感しました。
業務知識、技術知識、関係者の要望を的確に把握し、ファシリテーションを行うためには、各レイヤーの方々と一定のレベルで議論できる知識が不可欠です。私は関係者へのヒアリングや社内外の開発事例の収集を通じて、限られた時間の中で効率的に知識を習得する工夫を重ねてきました。こうした取り組みを支えてくださった皆様のご協力に、今も深く感謝しています。
──業務内容だけでなく、意識の部分での変化はありましたか。

今では「わからないことは積極的に聞きに行く」という意識がすっかり定着しました。ITコンサルティングの現場では、お客様が抱える課題が複雑で、背景や目的が多岐にわたり、表面的な情報だけでは本質にたどり着けない場合があります。
システム構築を担当していた頃は、設計書を見ればある程度の内容を把握できましたが、コンサルティングでは、より深い理解と洞察が求められます。お客様の意図や業務の背景を丁寧に掘り下げる姿勢が、価値提供のために不可欠だと感じています。要件定義書が存在していても、技術側がその背景を十分に理解できていない場合もあります。そうした時に、我々がどこまで「見えない部分」を掘り下げられるかが、プロジェクトの成否を左右する重要なポイントだと考えています。
一般的なITコンサルティングとの違い
──世の中でいうITコンサルティングと、富士ソフトのITコンサルティングは何が違うのでしょうか。

当社がITコンサルティングを提供する意義は、大きく3つあると考えています。
1つ目は、「構想」と「実行」をつなげられることです。構想段階では実行可能性を意識し、実行段階では構想の妥当性を見直す。このように、実行をベースにしたコンサルティングができる点は、当社ならではの強みです。
2つ目は、構想から開発までを一貫して担える体制があることです。当社には、幅広い技術領域をカバーする約1万人のエンジニアが在籍しており、構想段階からスムーズに開発・運用へと移行できる体制が整っています。
3つ目は、柔軟なサービス設計が可能であることです。ITコンサル室はまだ立ち上がって間もない部門であるため、既存の型にとらわれずお客様のニーズに合わせた柔軟なプランをご提案できるのも特徴です。
一般的なITコンサルティングがトップダウン型であるとすれば、当社はボトムアップ型にも対応できる点で、より実践的かつ現場に寄り添ったご支援ができると考えています。
──ITコンサルとシステム開発が密に連携する意義とは何でしょうか。
ITコンサルとシステム開発が密に連携する意義は、企業のIT戦略と実際の技術実装の間にあるギャップを埋め、より効果的で持続可能なソリューションを提供できることにあります。 構想をITコンサル会社が、実装をベンダーがそれぞれ担う場合、両者のコミュニケーションがうまくいかないことがあります。もしくはお客様が間に立つものの、うまくハンドリングできないこともあります。構想も実装も一貫して担える当社であれば、コミュニケーションロスはありません。必要なもの・不要なものを早い段階で切り分けるジャッジができるのです。
実際に私が経験した事例では、ソフトウェアのバージョンアップに伴う機能不具合が発生し、大きな手戻りが見込まれる状況になりました。プロジェクトメンバーでは知見が足らず対応が難しいと判断し、技術部門の上長へ相談しました。すぐに社内から有識者をサポートメンバーとして入れ、手戻りを最小限に抑えて予定通りにリリースすることができました。
このように、部門を超えて課題を共有し、会社全体でプロジェクトを成功に導けるのは、ITコンサルと開発が同じ組織内にあるからこそ実現できる価値だと思います。
ゼネラリスト型のコンサルタントを目指す
──今後のキャリア展望を聞かせてください。
私は、構想段階から実現まで一貫してご支援できるゼネラリスト型のITコンサルタントを目指しています。幅広い知識を生かし、さまざまな業種・業界に柔軟に対応できる人材になりたいと考えています。当社には、ITソリューションの開発や保守・運用において高い専門性をもつスペシャリストが多数在籍しています。そうした技術部門や営業部門と連携しながら、大規模案件のお客様にも最適な提案を行っていきたいと思っています。
今後、ITコンサル室はさらに拡大していく見込みです。新たに多様な技術領域をバックグラウンドにもつメンバーが加わることで、組織の専門性と対応力はいっそう高まるでしょう。私はそうしたメンバーを一つにまとめ、チームとしての力を最大限に引き出しながら、組織の成長に貢献していきたいと考えています。

誰よりもお客様のことを考え、シナジーを生み出す
──大高さん個人としてのポリシーや、仕事上のこだわりはありますか?
「お客様第一」は、プロジェクトマネージャー時代から一貫して大切にしている考え方です。お客様によって求める情報の内容や深さは異なります。たとえば、スピードを最優先される場合もあれば、詳細で丁寧な情報を求められることもあります。そのため、私はお客様ごとにニーズをしっかり確認し、それに応じて提供する情報の内容や伝え方を柔軟に変えるようにしています。また、直接お客様にお聞きしにくいことがある場合でも、その方に合ったご提案ができるよう、周囲の方からその方の人となりをうかがうこともあります。元々人に興味がある性格なので、お客様一人ひとりに寄り添った対応を心がけています。
そして上司が常々語っていることですが、組織全体でアントレプレナーシップ(起業家精神)を意識し、実践していける体制を目指しています。メンバー一人ひとりが、サービスや事業に対して主体的に取り組み、自ら創り上げていく姿勢をもつことで、将来的には事業本部規模への拡大を目指したいと考えています。
「自分たちの、オリジナルのスタイルを作っていくんだ」という高いモチベーションと、強みである会社の総合力を武器に、お客様に喜ばれる事業として育てていきたいです。

※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。





