クイッシング(quishing)とは?被害事例と安全対策を徹底解説!
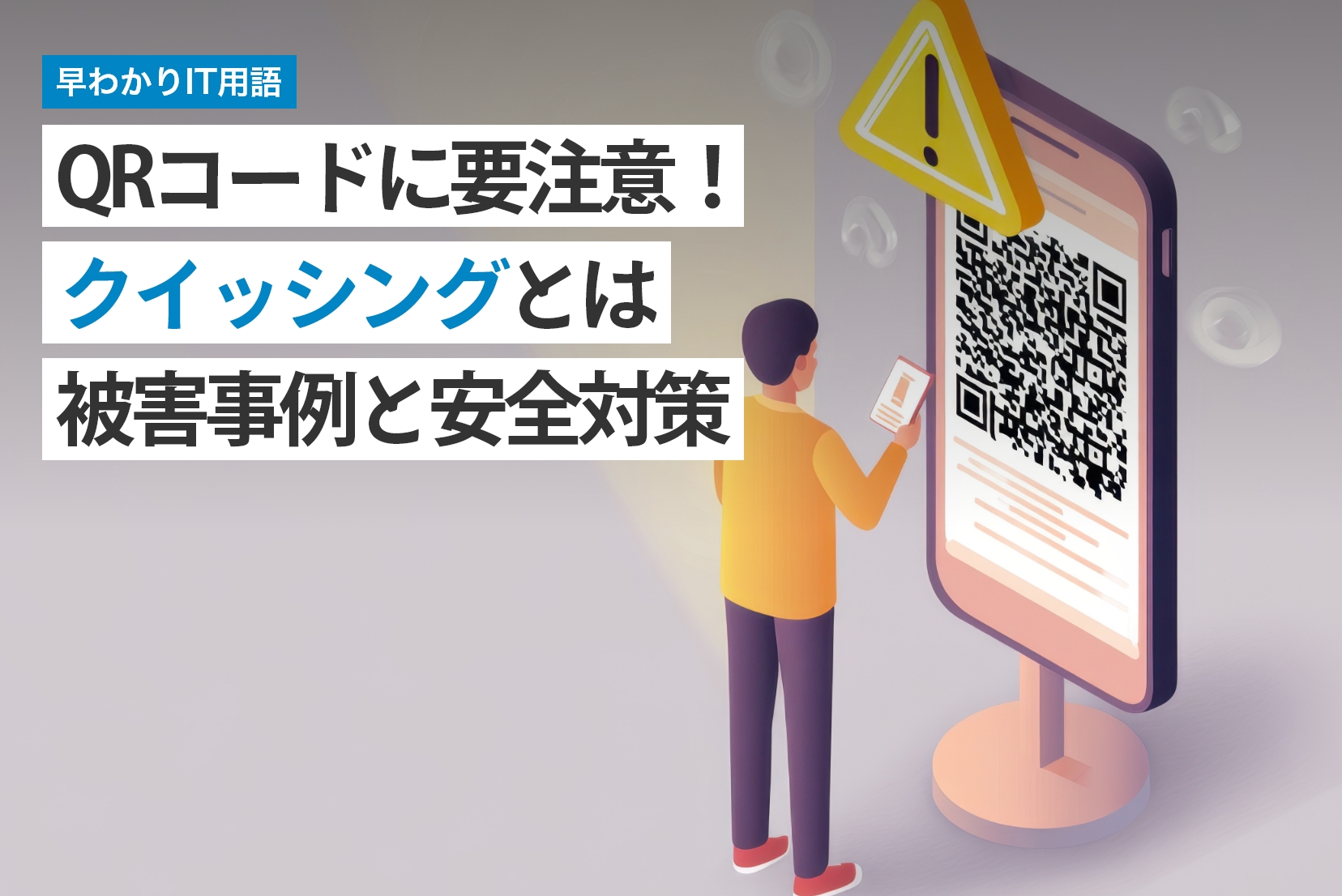
QRコードを使ったフィッシング詐欺に遭遇したことはありませんか?クイッシング(quishing)という新たなフィッシング手口が増えています。quishingは、日常生活で頻繁に利用されるQRコードを悪用した詐欺手法で、知らないうちに個人情報が盗まれる危険性があります。本記事では、quishingの基本的な仕組みや実際の被害事例を詳しく解説し、quishingの被害に遭わないための具体的な安全対策を紹介します。さらに、関連する最新トレンドや用語についても解説し、クイッシング詐欺に対する理解を深め、quishingから身を守るための知識を身につけてください。
- クイッシング(quishing)とは、QRコードを悪用したフィッシング詐欺の一種です。
- ユーザーがQRコードをスキャンすることで、偽のウェブサイトに誘導し、個人情報を盗み取ったり、マルウェアに感染させたりします。
- QRコードを読み込ませるクイッシングは不特定多数に影響を及ぼす可能性があり、特に公共の場でのQRコード利用には注意が必要です。
-
 Tech Tips編集部
Tech Tips編集部富士ソフト「Tech Tips」編集部です。トレンドのIT用語をわかりやすく解説しています。
quishingとは

本章では、近年急増している新しいフィッシング手法「quishing」について、基礎からしっかりと理解するための内容をお伝えします。quishingは、従来のフィッシング詐欺とは異なる手法を用いており、特にデジタル社会においてその脅威が増しています。quishingの基本的な仕組みやその特徴を知ることで、より安全にインターネットを利用できるようにしましょう。
quishingの定義と基本的な仕組み
クイッシング(quishing)とは、QRコードを悪用したフィッシング詐欺の一種です。QRコードは、スマートフォンなどで簡単に読み取れるため、悪意のあるリンクを仕込むことが容易です。quishingの基本的な仕組みは、ユーザーがQRコードをスキャンすることで、偽のウェブサイトに誘導し、個人情報を盗み取るというものです。この手法は、特にモバイルデバイスの普及に伴い、ますます巧妙化しています。quishingの被害を防ぐためには、QRコードの出所を確認し、信頼できる情報源からのみアクセスすることが重要です。
フィッシング詐欺との違い
quishingと従来のフィッシング詐欺の主な違いは、攻撃手法にあります。フィッシング詐欺は通常、メールやメッセージを通じて偽のリンクを送り、ユーザーを騙して個人情報を入力させる手法です。一方、quishingはQRコードを利用するため、物理的な場所や広告などにQRコードを設置し、ユーザーが自らスキャンすることで攻撃が成立します。この違いにより、quishingはより広範囲に影響を及ぼす可能性があり、特に公共の場でのQRコード利用には注意が必要です。
quishingによる被害事例
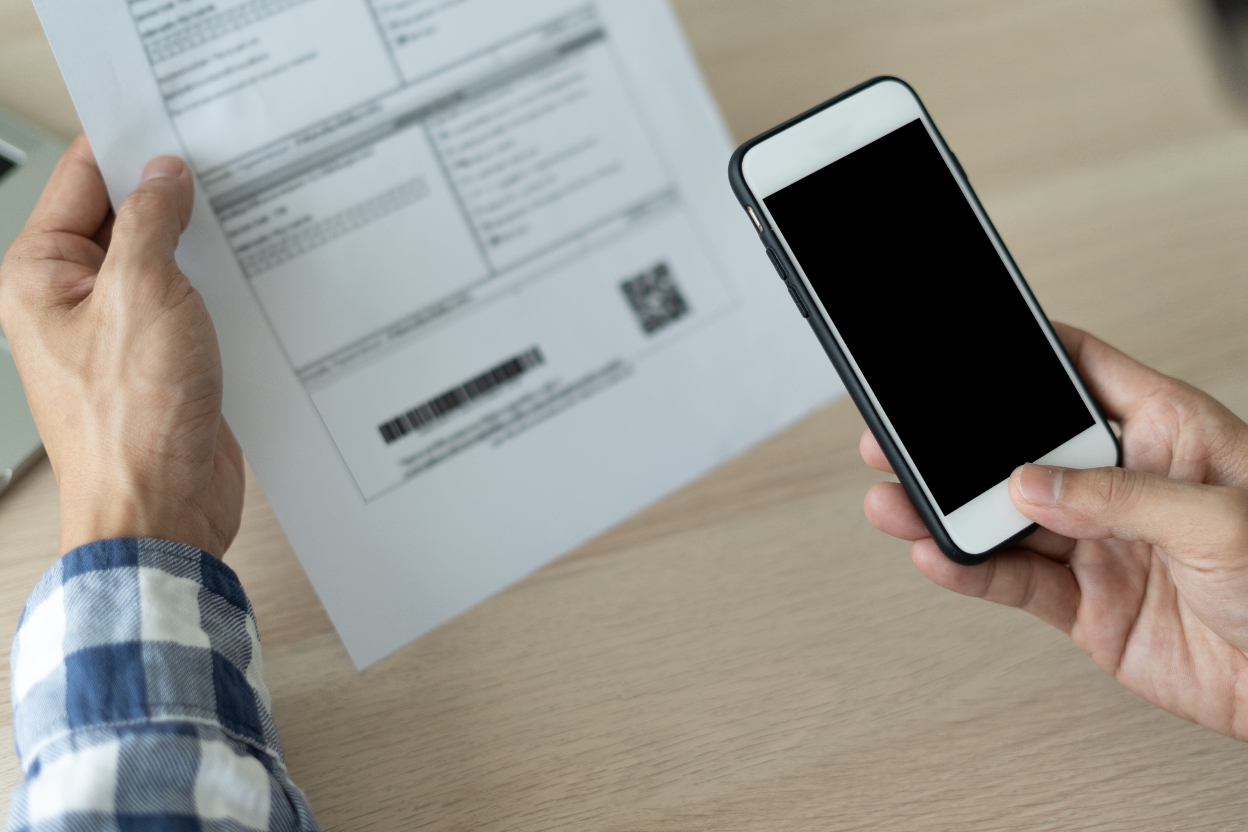
quishingは、近年注目されている新しいフィッシング詐欺の手法です。本章では、実際に発生したquishingの被害事例を紹介し、どのような手口が使われているのかを詳しく解説します。quishingの危険性を理解し、被害を未然に防ぎましょう。
1. QRコードを悪用した詐欺
攻撃者は、偽のQRコードを作成し、これを利用者にスキャンさせることで、個人情報を盗み取ります。例えば、店舗の入り口やイベント会場に偽のQRコードを貼り付け、利用者がそれを読み取ると、偽のウェブサイトに誘導されることがあります。このような手口により、利用者は知らないうちに個人情報を入力してしまう危険があります。
2. 偽のログイン画面へ誘導するケース
偽のログイン画面へ誘導するケースは、quishingの典型的な手法の一つです。攻撃者は、正規のウェブサイトに似せた偽のログインページを作成し、QRコードを使って利用者をそこに誘導します。例えば、偽のキャンペーンチラシを配布し、QRコードを読み込ませることで偽のページに誘導します。利用者がそこでログイン情報を入力すると、その情報が攻撃者に渡ってしまいます。
3. 支払い詐欺に利用されるパターン
支払い詐欺に利用されるパターンでは、攻撃者は偽の請求書や支払い依頼を送りつけ、利用者に不正な支払いをさせようとします。例えば、偽の請求書に記載されたQRコードをスキャンすると、偽の支払いページに誘導され、そこでクレジットカード情報を入力させられることがあります。このような手口により、利用者は金銭的な被害を受ける可能性があります。
4. 偽装された宅配通知を使った事例
偽装された宅配通知を使った事例では、攻撃者は偽の宅配通知を送り、利用者を騙して個人情報を入力させます。例えば、「お荷物が届いています。詳細はこちらから確認してください」といったメッセージと共にQRコードを送り、読み取らせることで偽のウェブサイトに誘導します。そこで住所や電話番号などの個人情報を入力させられることがあります。
5. 飲食店デリバリーを装ったチラシ
コロナ禍以降、急激に増えたクイッシング詐欺の一つに飲食店を装ったメニューやクーポンのチラシ配布があります。配送無料や割引キャンペーンなどで誘導しQRコードを読み込ませると、マルウェアなどを感染させるプログラムが立ち上がり、個人情報を盗む手口が増加しました。
quishingのリスクと被害を防ぐ7つの安全対策

quishingは、QRコードを悪用した新たなフィッシング詐欺の手口として注目されています。本章では、quishingによる被害を未然に防ぐための具体的な安全対策を紹介します。日常生活でQRコードを利用する機会が増えている中で、どのようにして安全に利用するかを知ることは非常に重要です。ここでは、quishingのリスクを軽減するための7つの具体的な方法を詳しく解説します。
1. QRコードをむやみに読み取らない
QRコードは便利なツールですが、むやみに読み取ることは危険です。特に、公共の場や不特定多数がアクセスできる場所に設置されたQRコードは、悪意のあるリンクに誘導される可能性があります。QRコードを読み取る前に、その出所や設置場所を確認し、信頼できるものであるかを判断することが重要です。信頼できないQRコードは、読み取らないようにしましょう。
2. 出所の明確な情報のみ利用する
インターネット上で提供される情報は、出所が明確であることが重要です。特に、QRコードやリンクを通じてアクセスする情報は、公式なウェブサイトや信頼できる企業から提供されているかを確認する必要があります。出所が不明確な情報は、詐欺や不正アクセスのリスクを高めるため、利用を避けるべきです。
3. セキュリティソフトの活用
セキュリティソフトは、quishingを含む様々なサイバー攻撃からデバイスを守るための重要なツールです。最新のセキュリティソフトをインストールし、定期的に更新することで、新たな脅威にも対応できます。セキュリティソフトは、怪しいリンクや不正なアクセスを検知し、警告を発する機能を持っているため、積極的に活用しましょう。
4. 怪しいリンクは開かない習慣をつける
怪しいリンクを開かないことは、quishingの被害を防ぐ基本的な対策です。QRコードを読み取り後リンクを開く前に、URLを確認し、公式のものであるかを確認しましょう。
5. 公式アカウントを確認する
SNSやメッセージアプリでの情報は、公式アカウントからのものであるかを確認することが重要です。公式アカウントは、認証バッジや公式マークが付いていることが多いため、それを目安に信頼性を判断しましょう。偽アカウントからの情報は、詐欺や不正アクセスのリスクが高いため、注意が必要です。
6. 定期的なパスワード変更
パスワードを定期的に変更することは、quishingを含む様々なサイバー攻撃からアカウントを守るための基本的な対策です。強力なパスワードを設定し、定期的に変更することで、不正アクセスのリスクを大幅に減らすことができます。パスワードは、英数字や記号を組み合わせた複雑なものにしましょう。
7. 家族や知人にも注意喚起する
quishingのリスクは、個人だけでなく家族や知人にも影響を及ぼす可能性があります。家族や知人にも、quishingの危険性や対策について情報を共有し、注意を促すことが重要です。特に、インターネットに不慣れな人々には、具体的な対策を教えることで、被害を未然に防ぐことができます。
quishingとあわせて知りたい関連用語・最新トレンド

本章では、quishingに関連する用語や最新のトレンドを知りたい方に向けて、関連する詐欺手法やセキュリティ対策について詳しく解説します。quishingは新しいフィッシング手法として注目されていますが、他にもスミッシング(smishing)といった関連する詐欺手法が存在します。これらの手法を理解することで、より効果的なセキュリティ対策を講じることが可能です。また、多要素認証の重要性についても触れ、quishing対策における最新のトレンドを紹介します。これにより、読者は自身のセキュリティ意識を高め、被害を未然に防ぐための知識を得ることができます。
スミッシング(smishing)とは
スミッシングは、SMSを利用したフィッシング詐欺の一種で、quishingと同様に個人情報を狙った手法です。smishingでは、偽のSMSを送り、ユーザーを偽のウェブサイトに誘導して情報を入力させることが一般的です。quishingとsmishingは、どちらもデジタルコミュニケーションを悪用する点で共通していますが、使用するメディアが異なります。これらの詐欺手法に対抗するためには、SMSやメールに含まれるリンクを安易にクリックしないことが重要です。また、送信元の信頼性を確認する習慣をつけることも効果的です。
多要素認証とquishing対策の重要性
多要素認証は、quishingを含む様々なサイバー攻撃から個人情報を守るための重要なセキュリティ対策です。多要素認証とは、パスワードに加えて、別の認証要素を組み合わせることで、セキュリティを強化する方法です。例えば、スマートフォンに送られる確認コードや、生体認証を利用することが一般的です。quishing攻撃では、偽のログインページを使用してパスワードを盗むことが多いため、多要素認証を導入することで、攻撃者が不正にアクセスすることを防ぐことができます。これにより、個人情報の漏洩リスクを大幅に低減することが可能です。
まとめとquishing対策のポイント

この記事では、quishingという新たなフィッシング手口について詳しく解説しました。quishingは、QRコードを悪用した詐欺手法であり、近年注目を集めています。被害事例としては、偽のログイン画面への誘導や支払い詐欺、偽装された宅配通知を利用した手口などが挙げられます。
これらの事例を知ることで、quishingの危険性を理解し、適切な対策を講じることが重要です。安全対策としては、QRコードをむやみに読み取らないことや、出所の明確な情報のみを利用することが推奨されます。また、セキュリティソフトの活用や怪しいリンクを開かない習慣をつけることも効果的です。さらに、公式アカウントの確認や定期的なパスワード変更、家族や知人への注意喚起も重要な対策です。これらの対策を実施することで、quishingによる被害を未然に防ぐことができます。
富士ソフトではセキュリティ関連資格を持ったスペシャリストが多数在籍し、お客様の環境に最適なセキュリティソリューションをご提案いたします。セキュリティでお困りのお客様はお気軽にお問い合わせください。
※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。






