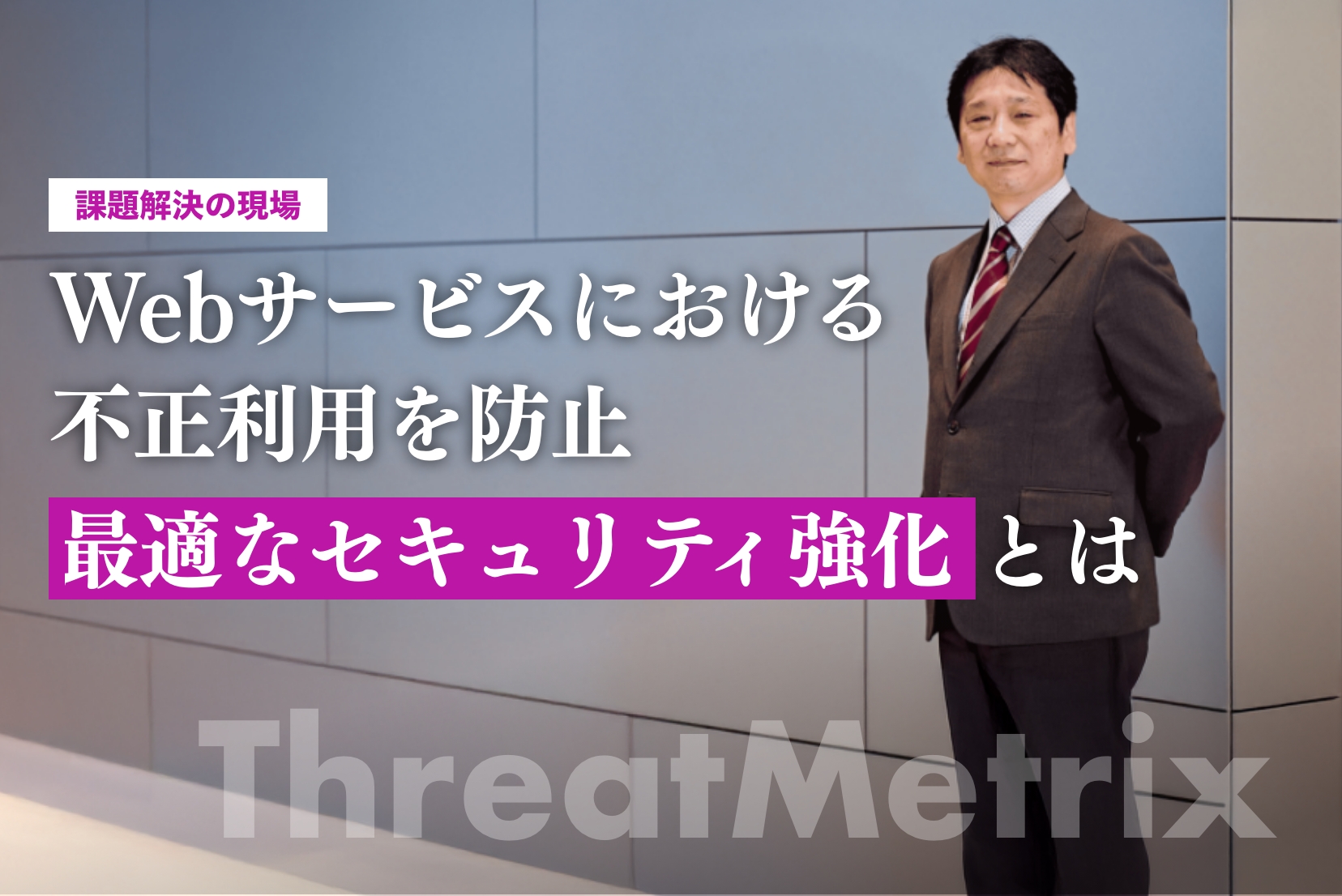開発スピードと品質を向上!CCCMKホールディングス社と取り組んだ生成AIを活用したシステム開発

システム開発における生成AIの活用事例が増えてきましたが、ほとんどのケースでは「やってみた」というレベルに留まることが多く、QCD(クオリティ・コスト・デリバリー)が求められるシステム開発においては、活用をためらっている企業が多いのが現状です。富士ソフトは業界に先駆けて、生成AIを活用したCCCMKホールディングス株式会社(以下CCCMK)が提供する、モバイルVカードを好きなデザインに着せかえできるサービス「V キセカエ」のシステム開発を行いました。本記事では、CCCMKテクノロジー戦略本部 エンジニアリング部 武川 有希氏と青木 文美氏にお越しいただき、プロジェクトを担当した江川 智子と福田 博紀を交えて、生成AI導入の経緯と得られた成果について話を聞きました。
- QCDの向上
- 短期間での開発が必要
- 担当するエンジニアのナレッジに依存しない安定した維持管理体制
- QCDが向上し自社事業に貢献できた
- 短期間で開発し予定通りのリリースができた
- 経験に左右されない高品質で標準化された維持管理体制が見込まれる
-
 武川 有希氏CCCMKホールディングス株式会社
武川 有希氏CCCMKホールディングス株式会社
テクノロジー戦略本部 エンジニアリング部
部長 -
 青木 文美氏CCCMKホールディングス株式会社
青木 文美氏CCCMKホールディングス株式会社
テクノロジー戦略本部 エンジニアリング部 会員サービスグループ
グループリーダー -
 江川 智子富士ソフト株式会社
江川 智子富士ソフト株式会社
システムインテグレーション事業本部 ビジネスソリューション事業部 第2技術部第5技術グループ
課長 -
 福田 博紀富士ソフト株式会社
福田 博紀富士ソフト株式会社
システムインテグレーション事業本部 ビジネスソリューション事業部 第2技術部第5技術グループ
主任
生成AIの活用に至った背景
──はじめに、CCCMK エンジニアリング部様の役割を教えてください。

CCCMK 武川:エンジニアリング部は、CCCMKが提供するさまざまなサービスを支えるシステム基盤の開発、保守、運用をしています。たとえば、自社で運営する「Vキセカエ」、モバイルVカードのサービス、Vポイントのサービス、会員基盤、ポイント基盤、分析基盤などが挙げられます。
──なぜ生成AIを活用しようとお考えになったのでしょうか。
CCCMK 武川:社会的に生成AIを活用しようという動きが広がるなかで、我々としてもシステム開発で生成AIを使って、生産性と品質を同時に上げたいと考えていました。しかしさまざまな課題感があり、なかなか手を出せなかったのが実情です。一方で、近年はリリースまでのスピードが強く求められており、開発の効率化を実現したい考えがありました。そんな折、富士ソフト社から「生成AIを使って開発してみませんか」とご提案をいただき、社内調整をして動き出しました。
これまで取り組めていなかった理由は、一般的にいわれているセキュリティの課題や品質の課題です。ネガティブな側面がフォーカスされがちですが、富士ソフト社のご提案が生成AIだけでなく、人間が補完しながら全体的な効率化を進めていくものだったので、やってみようということになりました。
──富士ソフト側にも聞きますが、CCCMK様に生成AI活用をご提案した理由はなんでしょうか。
富士ソフト 江川:CCCMK様と当社は2023年にお取引が始まり、2024年から本格的にWebまわりの開発を任せていただいています。CCCMK様のシステムについて知見が蓄積されていたことに加え、今回携わらせていただいた「Vキセカエ」についての構想や課題感を伺うなかで「生成AIがフィットするだろう」と判断しました。
当社としても、生成AIを活用した開発経験が蓄積されていました。基幹システムなどの開発で生成AIを活用しながら、高品質で標準化されたコード生成を行える仕組みを構築してきたので、ある程度自信もあったのです。しかし、厳しいQCDが求められる本格開発となると事例はまだ少なかったので、業界のなかで一歩踏み出したいという思いもありました。

生成AIの活用によって得られた成果
──「Vキセカエ」サービスの開発とは、どのような内容だったのでしょうか。
CCCMK 青木:当社の「Vキセカエ」は、VポイントアプリのモバイルVカードのデザインを、ユーザー様が好きなデザインに着せ替えられるサービスです。購入したくなるようなデザインを組み込む必要があり、そこは当社で内製化しています。富士ソフト社には、フロント表示に必要な部分を切り出して、バックエンドから情報を取得するAPI機能を中心に、バッチ処理や運用・CS担当者が利用する管理画面を開発していただきました。
──生成AIを活用してみて、いかがでしたか。
CCCMK 武川:我々エンジニアリング部の目標は、プロダクトのQCDを継続的に向上させていき事業に貢献していくことです。そのQCDで成果が出たのは大きなポイントで、富士ソフト社には本当に感謝しています。QCDはどうしてもトレードオフの関係になりがちですが、富士ソフト社が標準化のノウハウを適用する形で、品質の高い開発をスムーズに実現できたので、非常に良い取り組みだったと捉えています。

CCCMK 青木:「生成AIだから良くなかった」というケースはなかったですね。問題なく安定して処理ができる状態で、受入試験においては前工程からのすり抜け不具合は検出されませんでした。もちろんお互いの認識をすり合わせるなかで出てくる課題もありましたが、それは人が開発しても同じことなので、コミュニケーションをしっかりとることで解決できました。
ちなみに、今回の開発は規模が大きかったので、他のSIerさんも交えたコンペをしたのですが、納期を順守できるご提案をいただけたのは富士ソフト社だけでした。開発規模からすると短い開発期間となり難易度は高かったのではないかと思いますが、予定通りリリースできたのはとてもありがたかったです。
──富士ソフトとしては、どのような成果がありましたか。
富士ソフト 江川:当社としても生産性が大きく向上しました。具体的には20~30%程度の効率化を達成できたと思います。こう言うと、当社が楽をしているんじゃないかと思われるかもしれません。でも実は、コーディングの生産性を高めた分、別の部分でCCCMK様に還元するようにしています。
富士ソフト 福田:たとえば、CCCMK様が社内説明される際に必要となる資料作りに注力することや、リリース予定を守るための納品スピード、他にも社内教育の徹底などにリソースを使っています。ちなみに、生成AIがアウトプットしたコードはすべて人がチェックし、想定したものが出てこない場合は何度も生成AIと対話してブラッシュアップし、それでも出てこない場合は人が自らコーディングする対応もとっていました。

開発において人が担う部分と生成AIが担う部分の切り分け
──すべてを生成AIで開発したのでしょうか。
CCCMK 武川:個人情報や決裁に関わる機能は、人の手で開発していただきました。また、間違いが許されない暗号化や会員認証、外部の情報にアクセスする外部連携に当たる部分は、生成AIの活用対象から外していただきました。個人的には生成AIでも問題ない品質のものができるだろうと考えていましたが、万が一ミスがあった時のリスクが大きい部分は人の手で開発していただき、今回の案件の固有の機能、その他の機能はすべて生成AIを使っていただいても問題ない形にしました。
──生成AIならではの、苦労したポイントがあれば教えてください。

CCCMK 青木:先ほど申し上げたとおり、コーディング自体はとくに問題ありません。ただしドキュメントの書式には苦労がありました。設計書の書式はマークダウン形式で記述していただいたものを都度整形して納品いただきました。弊社のこれまでの開発では、処理順序がわかりやすいフロー図を多用する設計書が多かったので、最初は読み慣れない印象を受けました。このため、社内での設計書レビューにおいては、見てほしい範囲を明示的に伝えるといった手順を加えたり、追加で資料を作った事もありましたが、こうした生成AIならではの知見が得られたことも、今回の収穫の1つだったと捉えています。
属人化を排除した開発と保守運用を進めていく
──今後の方針についてお聞かせいただけますか。
CCCMK 武川:生成AIはまだまだ普及している最中で、完成形があるわけではありません。今回はToC向けWebサービスの開発に活用しましたが、システム部門内での生成AIの活用は模索し続けています。まずはできることをしっかりと見極めて、使いこなすことが大事ですが、中長期的には基幹システムにも切り込んでいきたいと考えています。当社でも定期的に基幹システムの更新をしていて、次の計画も始まっています。また2024年度から、新たにAI推進室という組織が立ち上がり、全社的にAIを積極的に活用していく取り組みが始まっています。今後もCCCMKのアセットをどんどん使って、生成AIをうまく活用していく流れを作っていこうと考えています。
今回得られた知見を次に活かしていくことが重要で、とくに生成AIを活用した属人化の排除は進めていきたいテーマの一つです。一定レベルのアウトプットが出てきて、常に同じレベルの品質を担保できれば、これは大きな成果と言えるでしょう。人が開発する場合、担当者が変わればノウハウが100%引き継がれることは難しいです。そういった面で、生成AIはまだまだ可能性に満ちているのではないかと思います。

お客様もSIerもWin-Winの関係を目指す
──富士ソフトとしての生成AIの活用方針についても、紹介してください。
富士ソフト 江川:今回はユーザーサイトに関わる開発を任せていただきました。今後も生成AIを活用して、さまざまな開発におけるQCDの向上に貢献していきたいです。ゆくゆくは、我々も今回のような取り組みを、基幹システム系でお困りのお客様にもご提案したいと思っています。
ここまでCCCMK様からご紹介いただいたように、我々のようなSIerが生成AIを活用することで、お客様に対してクオリティやデリバリー面でのメリットをご提供できると考えています。しかし一方で、「SIer側にメリットがあるだけでは」と感じている方がいることも事実だと思います。だからこそ、お客様もSIerも、お互いがWin-Winの状態を実現できることを大切にしていきたいのです。生産性を高めていければ、コスト面でもお客様と分かち合える余地を見つけだせるかもしれません。引き続き、お客様と一緒により良いプロジェクトを築いていけたらと考えています。
妥協せず、お客様に寄り添う気持ちで
──最後に、仕事を進める上で大切にしていることを教えてください。
富士ソフト 江川:すべてのお客様に納得していただけるよう、妥協せず仕事に取り組むようにしていますし、今後もそうありたいですね。お客様から「また一緒に仕事をしたい」と言われるように、目の前のことに妥協せず、一緒に笑って、仕事終わりには飲みに行けるような、良い関係が作れるようこれからも精進していきます。
お客様を前にしてこんなことを言うのは、とても照れますね。

富士ソフト 福田:私も、仕事をまた一緒にしたいと思われるような関係を目指しています。そのためのホスピタリティを大切にしていますね。お客様に寄り添って仕事をして、お客様にとって良いものを作りたいです。「こんなことできますか」と聞かれ、納期や予算的に難しいことがあっても、すぐに「できません」と言うのではなく、なんとかできるような可能性を探るなどの「気持ち」を大切にしたいと心がけています。


※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。