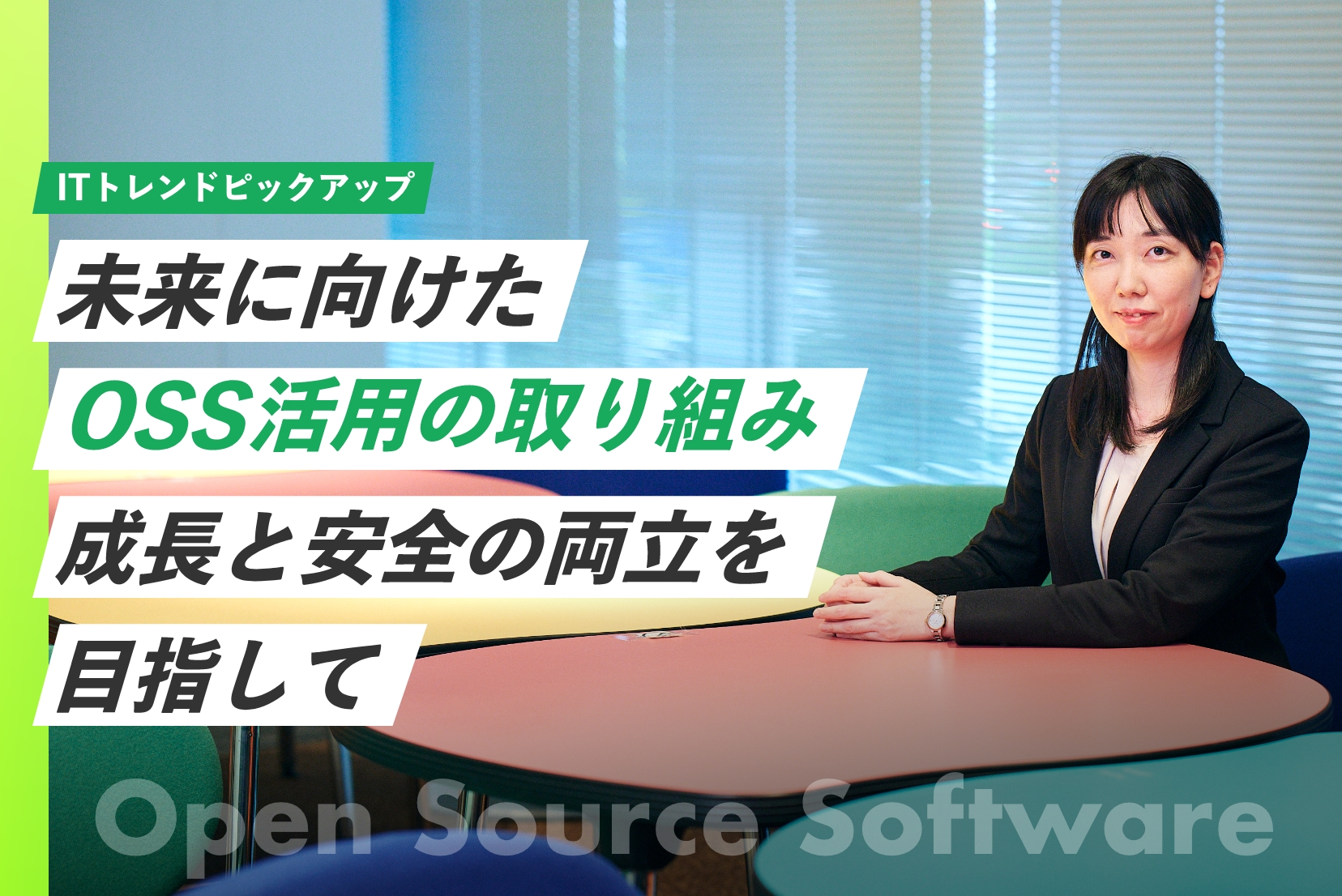「見やすさ」をあきらめない社会へ──富士ソフトとKiva社が取り組むWebアクセシビリティ

Webアクセシビリティの重要性が年々高まっています。その背景には、実際にWebを利用する際に不自由さを感じてきた当事者の存在があります。富士ソフトが2025年7月から協業を開始したKiva社の酒井様も、その一人です。視野が欠けていくご病気を患い、Webの世界で「見づらさ」と向き合いながらお仕事をされてきた経験が、「ユニウェブ」というサービスの開発につながりました。今回は株式会社Kivaの酒井 優一様をお招きし、当社のWebアクセシビリティ分野を担当する川相 剛之との対談を通じて、Webアクセシビリティの進化と最前線の取り組みについてご紹介します。
- 視覚障がい者でも見やすいWebサイトを実現
- 老眼に悩むユーザーの離脱防止にもつながる
- Webアクセシビリティが法制化された国に引けを取らない
- 日本語独特の読み方に寄り添った機能
-

酒井 優一氏
株式会社Kiva
営業部
事業部長大学卒業後、株式会社ディー・エヌ・エーにて、法人営業、事業開発、マーケティング業務に従事。
2024年より、株式会社Kivaにて、アライアンスを中心とした営業業務に従事。 -

川相 剛之
富士ソフト株式会社
ネットソリューション事業本部事業戦略推進室
主任WEB制作会社から大手インターネット広告代理店クリエイティブ部門部長を経てデータセンター運営会社(プライム市場)グループ会社にて動画配信や媒体運営と色々なWEB業界の業務を経験し、富士ソフト入社。
ECサイトの売上向上や、サイト集客のための様々なソリューションを提案導入する業務に取り組んでいる。
Webアクセシビリティに対応する企業が増えている
──はじめに、Webアクセシビリティを取り巻く社会情勢について教えてください。

Kiva 酒井:Webアクセシビリティは、現在世界各国で法整備が進み、企業にとって無視できないテーマとなっています。アメリカではすでにWebアクセシビリティが義務化され、対応が不十分な企業に対しては訴訟が起こるような事態になっています。
ヨーロッパでも同様の流れが加速しており、2025年に施行された欧州アクセシビリティ法では、一定以上の年商がある大企業に対して厳格な基準を求め、違反した場合には業務停止などの厳しい措置が科される可能性があります。Webアクセシビリティを満たすことは、今や企業活動の継続条件とされつつあるのです。
日本ではWebアクセシビリティの義務化はされていないものの、障がい者に配慮した社会形成が着実に進んでいます。2022年に障害者差別解消法が改正され、「合理的配慮の提供」がすべての事業者に義務化されました。Webにおけるアクセシビリティもその一環として注目が集まっており、当社の「ユニウェブ」に関する問い合わせも急増しています。
こうした法的背景に加え、SNSの普及も大きな影響を与えています。Webサイトが見づらいことをきっかけに炎上したりするケースが出始めており、企業にとってはアクセシビリティ対応をしていないこと自体がリスクになりつつあります。最近でも大手アパレル企業やゲーム機メーカーが、株主総会やソーシャルメディアでアクセシビリティの不備を指摘され、改善を迫られる事例も見られました。
国内でも、Webアクセシビリティの法制化を見据えて対応に乗りだす企業が出始めています。特にグローバル展開をする企業では、海外と同様の基準で日本のWebサイトも整備しておく動きが広がりつつあります。総務省は「みんなの公共サイト運用ガイドライン※」を公開しており、自治体の中にはガイドラインに沿ったWebサイト作りの一環で、「ユニウェブ」の導入を検討してくださるところも出てきています。こうした潮流を受け、当社は富士ソフト社と協業し、Webアクセシビリティの啓蒙・普及に取り組んでいます。
何から始めればいいのかわからず悩む企業も多い
──Webアクセシビリティというテーマ自体に知見のない人も多いのではないでしょうか。
Kiva 酒井:法律や社会的要請によってWebアクセシビリティへの関心は高まっていますが、知っていたとしても、「具体的に何をすればよいのかわからない」という企業は少なくありません。それは、視覚障がい者がWebサイトを見る際に、どのような見え方をするのか、どんなときに見えづらいと感じるのかを理解しにくいからです。
たとえば視覚障がいがある場合、まず問題になるのは文字サイズや色のコントラストです。初期の段階では「コントラストの反転表示」で読みやすさを確保できても、進行すれば文字そのものが見づらくなります。そのため、文字を自由に拡大縮小できる機能が欠かせません。さらに障がいの度合いが進むと、音声で文字を読み上げるツールが必要になります。しかし既存のWebサイトの多くは、こうした機能をまだ備えていません。大企業であっても、しっかりアクセシビリティ対応がなされているサイトは、全体の2〜3割程度に留まります。

もちろん重度の障がい者だけが対象ではなく、軽度の視覚障がいや老眼などによって、Webサイトを使いづらいと感じる人も少なくありません。40〜50代以降では、文字の読みづらさを理由にWeb利用を控えるケースが見られます。実際に「スマホで使うアプリを限定してしまうのは、見づらさも原因の1つだった」という報告も聞いています。企業がアクセシビリティ対応を怠ることは、障がい者だけでなく、幅広いユーザー層を取りこぼすリスクにもつながるのです。
つまり、アクセシビリティへの対応は特別な取り組みではなく、誰もが使いやすいWebサイトを実現するための基本条件だといえます。その一方で、何から始めればいいのかわからず足踏みしている企業が多いという現実もあります。
世界基準に沿いながら日本語ユーザーに寄り添う
──健常者には理解しにくい部分も多いですね。ぜひ「ユニウェブ」について教えてください。
Kiva 酒井:こうした状況を受けて開発したのが、当社の「ユニウェブ」です。世界基準のWebアクセシビリティ対応をベースにしつつ、日本語特有の課題にも対応できる点が大きな特長です。
その代表例が「辞書登録機能」です。たとえば漢字の読み上げにおいて、企業側が意図した読み方と機械の自動読み上げが一致しないケースは多くあります。「ユニウェブ」では、Webサイト運営者が辞書に登録することで、意図した読み方を正確にユーザーへ届けることができます。
さらに、カーソルを合わせると難解な表現をやさしい日本語に変換するアドオンや、画像に代替テキストが設定されていない場合でも、AIが自動で画像を解析する機能など、日本語環境に特化した工夫が盛り込まれています。
──視覚障がいをお持ちの方の目線では、どのような特徴があるのでしょうか。
Kiva 酒井:ユーザーが抱える障がいの程度に合わせて、柔軟に表示設定を変えられる点です。Webページ上のアイコンをタップするだけで、文字サイズや色のコントラストを自由に変更でき、障がいの程度に応じて設定できます。この機能は、たとえば老眼が始まってWebサイトの見づらさに直面している40〜50代の方々にも嬉しい機能ではないでしょうか。しかもブランドの世界観を崩さないようUIを調整できるので、「ユニウェブ」を導入すれば、そうしたユーザーがサイトから離脱するのを防ぐ効果も期待できます。導入も既存のWebサイトにタグを追加するだけという簡単なものです。
私自身、視野が徐々に欠けていく病気を患い、進行の度合いに応じてさまざまなツールを組み合わせてきた経験があります。初期には反転表示、次に拡大機能、さらに音声読み上げと、病状に応じて段階的に対応してきた経験が「ユニウェブ」の設計思想に活かされています。
こうした設計や機能が評価され、今では600サイト以上に導入されています。大手小売企業のECサイトや、大手コンビニエンスストアの公式サイト、東京都が運営する「新型コロナ後遺症ポータル」、大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」公式サイト、最近では「東京2025 世界陸上」の番組ポータルサイトでも採用されました。

富士ソフトとKiva社の協業で目指すもの
──富士ソフトとして協業を推進している理由も教えてください。

富士ソフト 川相:まず酒井氏から「ユニウェブ」のご紹介をいただいたとき、私自身、即座に「これは社会に広げるべきだ」と感じました。そのことを社内で説明したところ、同じように感じてくれたメンバーが多く、自然と協業に向けて進んだ経緯があります。また当社のお客様から「アクセシビリティ対応をしたいが、具体的にどうすればいいのかわからない」という声が多く寄せられている状況もあります。今まさにKiva社との協業を通じて「ユニウェブ」の普及を進めるのは、時代が求めているという背景があるのです。
当社は、Webアクセシビリティだけでなく、DX(デジタルトランスフォーメーション)全般を一括して提案できることが強みです。「ユニウェブ」の導入を契機に、UI/UXの改善やシステム全体の最適化まで含めたソリューションを提供することで、より包括的なサポートを行える体制を整えています。
また公共機関や医療機関、自治体など、まだ十分にアクセシビリティ対応ができていない領域への展開も進めていきたいと考えています。その領域のWebサイトは社会インフラに近いもので、障がいをお持ちのユーザーが訪れることが多いサイトでもあります。Kiva社と力を合わせて、早急にこうしたWebサイトへの導入を推進していきたいと考えています。
当社は、アクセシビリティ対応を単なる「義務」ではなく、企業の価値を高め、より多くのユーザーに寄り添う姿勢を示すものと捉えています。今後もぜひKiva社と共に取り組みを拡大していきたいです。
視覚障がい者があきらめなくてもよい社会を目指して
──「ユニウェブ」が普及した先には、どんな社会になると思いますか。
Kiva 酒井:障害者差別解消法の改正によって、合理的配慮の提供が義務化されました。しかし現実には、視覚障がいを持つ方々が日常生活の中で「頼みにくい」「我慢してしまう」という状況が依然として存在します。
たとえば私が、レストランに入ってメニューが読みづらいと感じたとき、お店の方に「代わりに読んで欲しい」と頼んだとします。それは法律上、合理的な配慮の範囲内なので断ってはいけないとされています。ただランチタイムで凄く混んでいるときに、何種類もあるメニューを読んで欲しいというのは、なかなか頼みづらくてつい我慢をしてしまいます。「人に迷惑をかけたくない」という意識が強い日本人には特にこういう傾向が強いのです。
Webアクセシビリティにおいても、障がい者は主張を控えてしまい、多少の見づらさは我慢して受け入れてしまうことが多いのです。だからこそWebサイトの方に、ユーザーが見やすさを改善できる「ユニウェブ」のようなツールが必要なのです。全ての人が平等にWebサイトを利用できる、「誰もあきらめなくてよい社会」を実現していきたいと思います。


富士ソフト 川相:Webアクセシビリティの考え方は、これからの社会でますます必要になってくるでしょう。とはいえWebサイトすべてを、一気にアクセシビリティ対応させることは、企業によって難しい場合もあります。たとえば自治体のWebサイトは1万ページほどあることも多く、「ユニウェブ」がいかに導入しやすいといっても、切り替えには相応の時間と労力がかかります。まずは一部のページから、またはコーポレートサイトなど主要部分からなど、段階的に実施していくことをご提案していきたいです。
当社はこれまで、お客様に伴走する形で、Webサイトの最適化に向けたロードマップの策定や実行を、またWebサイト全体のリニューアルのご支援もしてきました。今回Kiva社との協業により、アクセシビリティという、お客様に提供できるソリューションの幅をさらに広げることができ、まだまだ当社にも取り組むべきことがありそうです。これからも、すべてのユーザーにやさしいWebサイトの構築に向けて邁進して参りますので、ぜひ期待してください。

※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。