早わかりIT用語
ITやテクノロジーに関する専門用語やトレンドキーワードを、富士ソフトの専門家が分かりやすく簡潔に説明します。
タグで絞り込む

早わかりIT用語
2026年1月29日

早わかりIT用語
2026年1月29日

早わかりIT用語
2026年1月22日

早わかりIT用語
2025年12月24日

早わかりIT用語
2025年12月24日
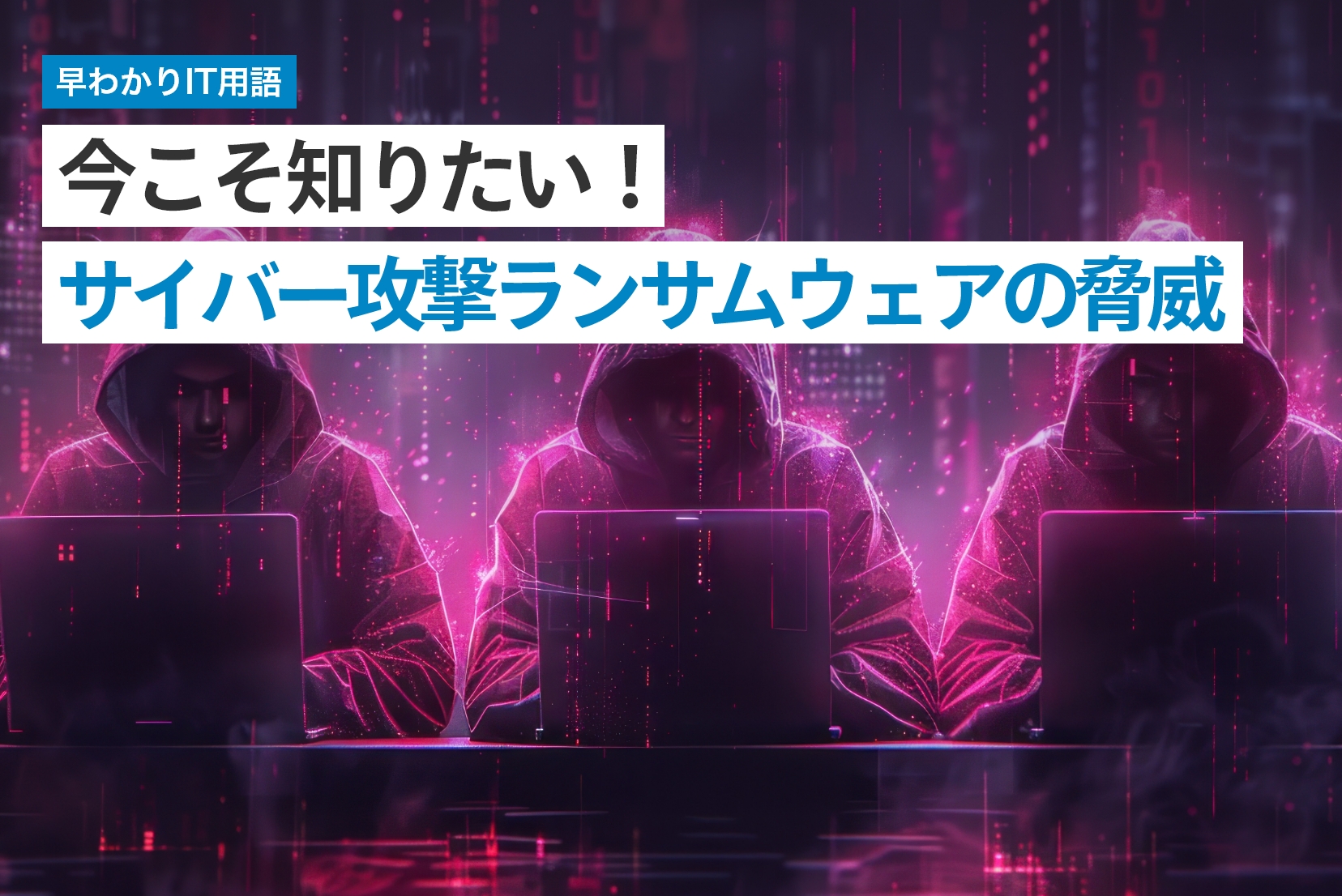
早わかりIT用語
2025年12月24日

早わかりIT用語
2025年12月23日
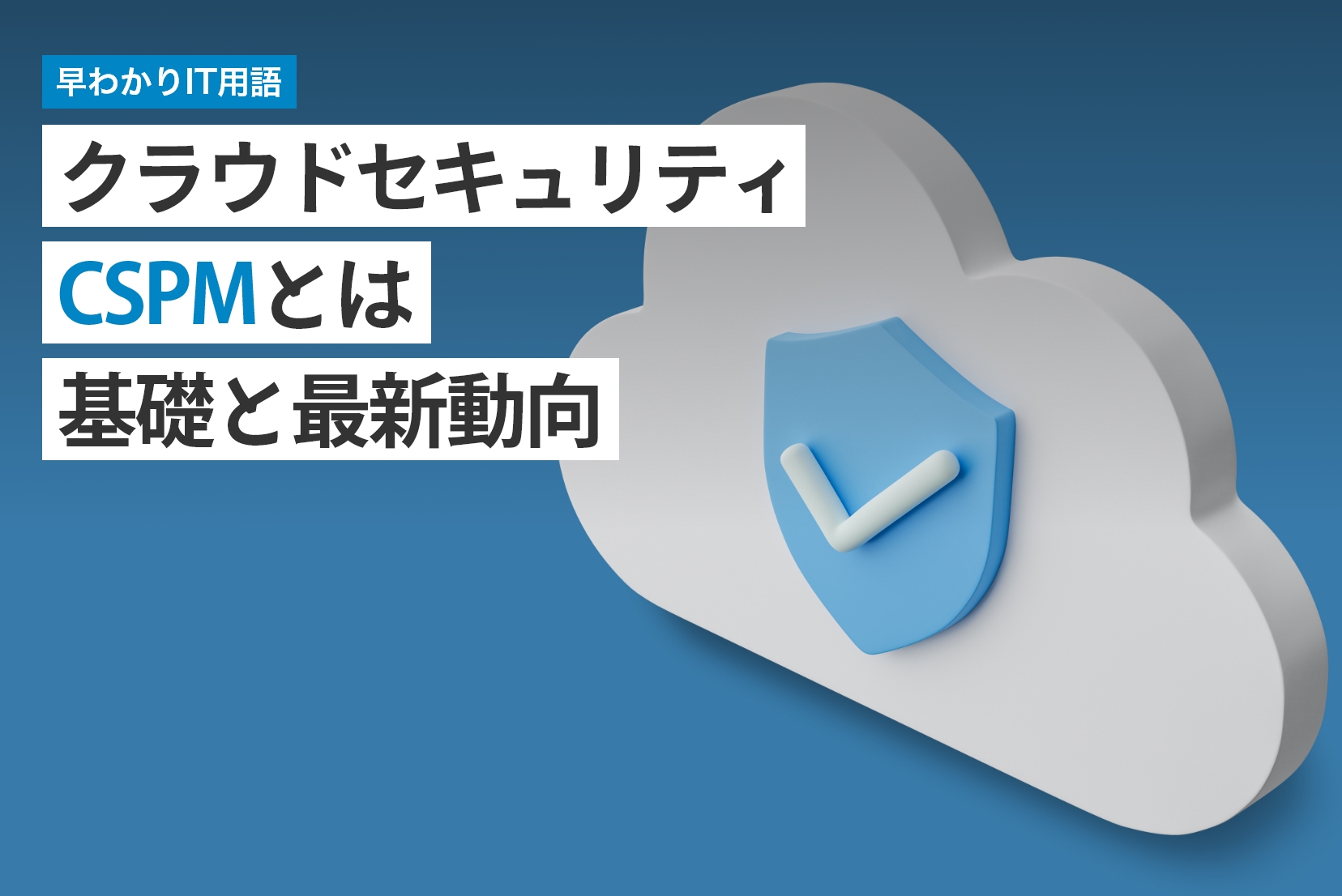
早わかりIT用語
2025年12月11日
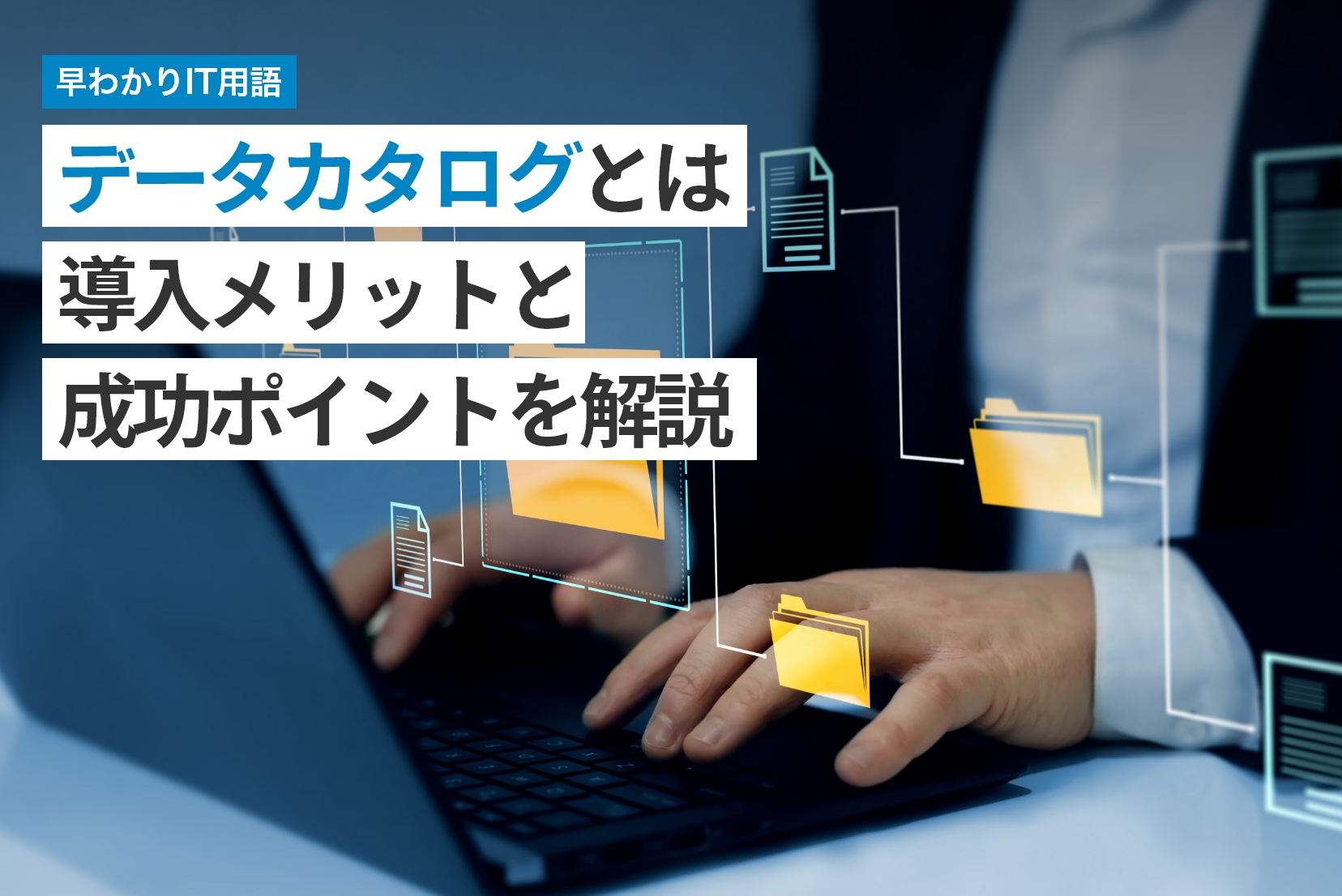
早わかりIT用語
2025年12月11日

早わかりIT用語
2025年11月28日

早わかりIT用語
2025年11月28日
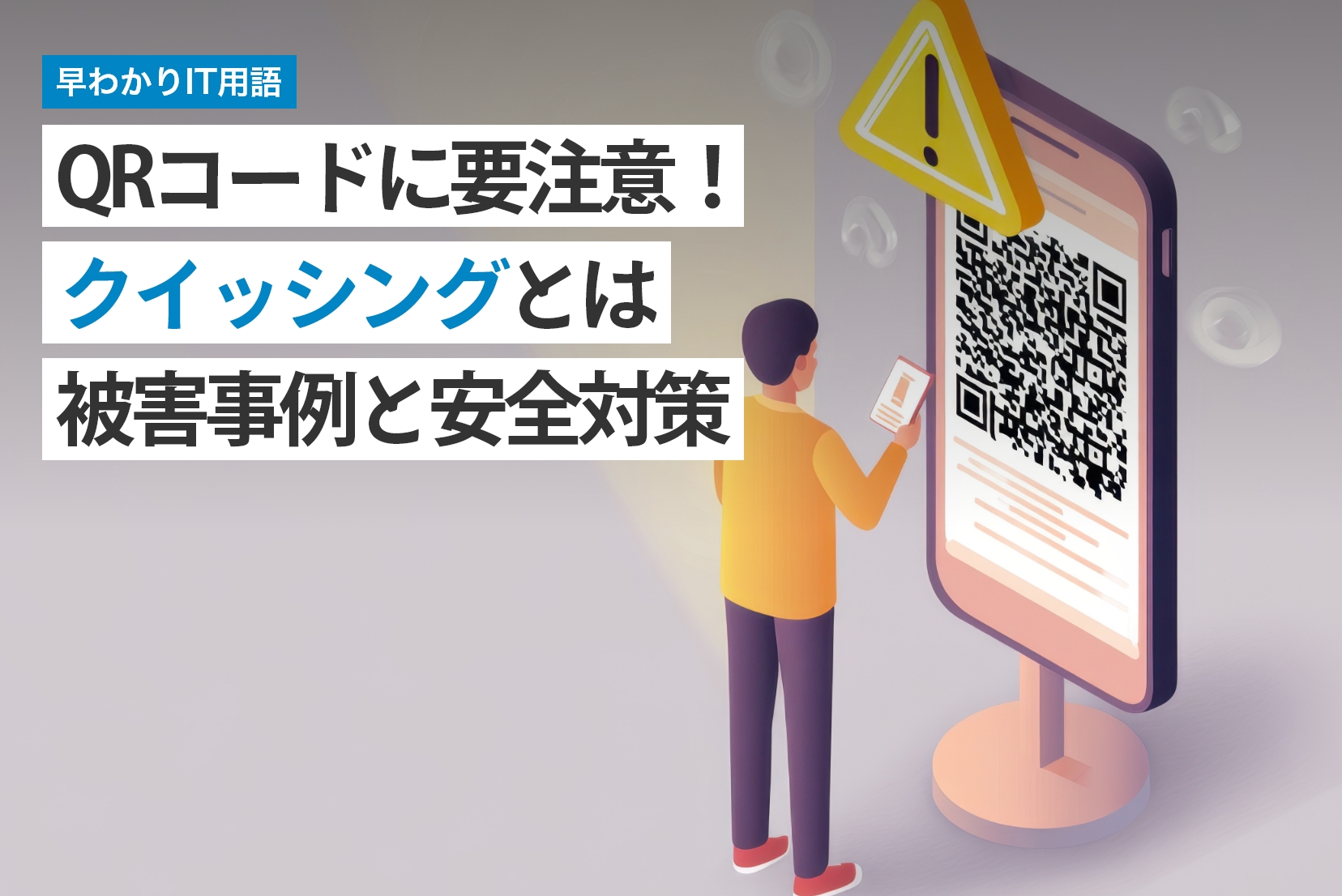
早わかりIT用語
2025年11月28日

早わかりIT用語
2025年11月28日

早わかりIT用語
2025年11月18日
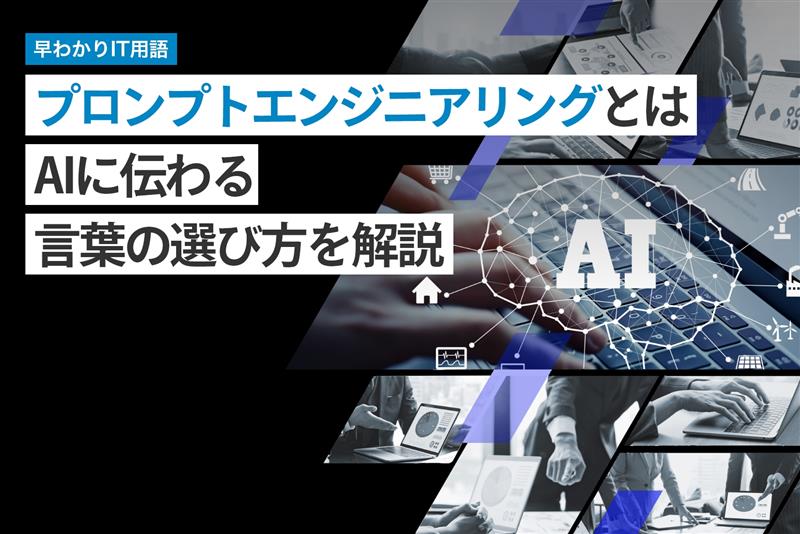
早わかりIT用語
2025年11月6日

早わかりIT用語
2025年10月30日

早わかりIT用語
2025年10月29日
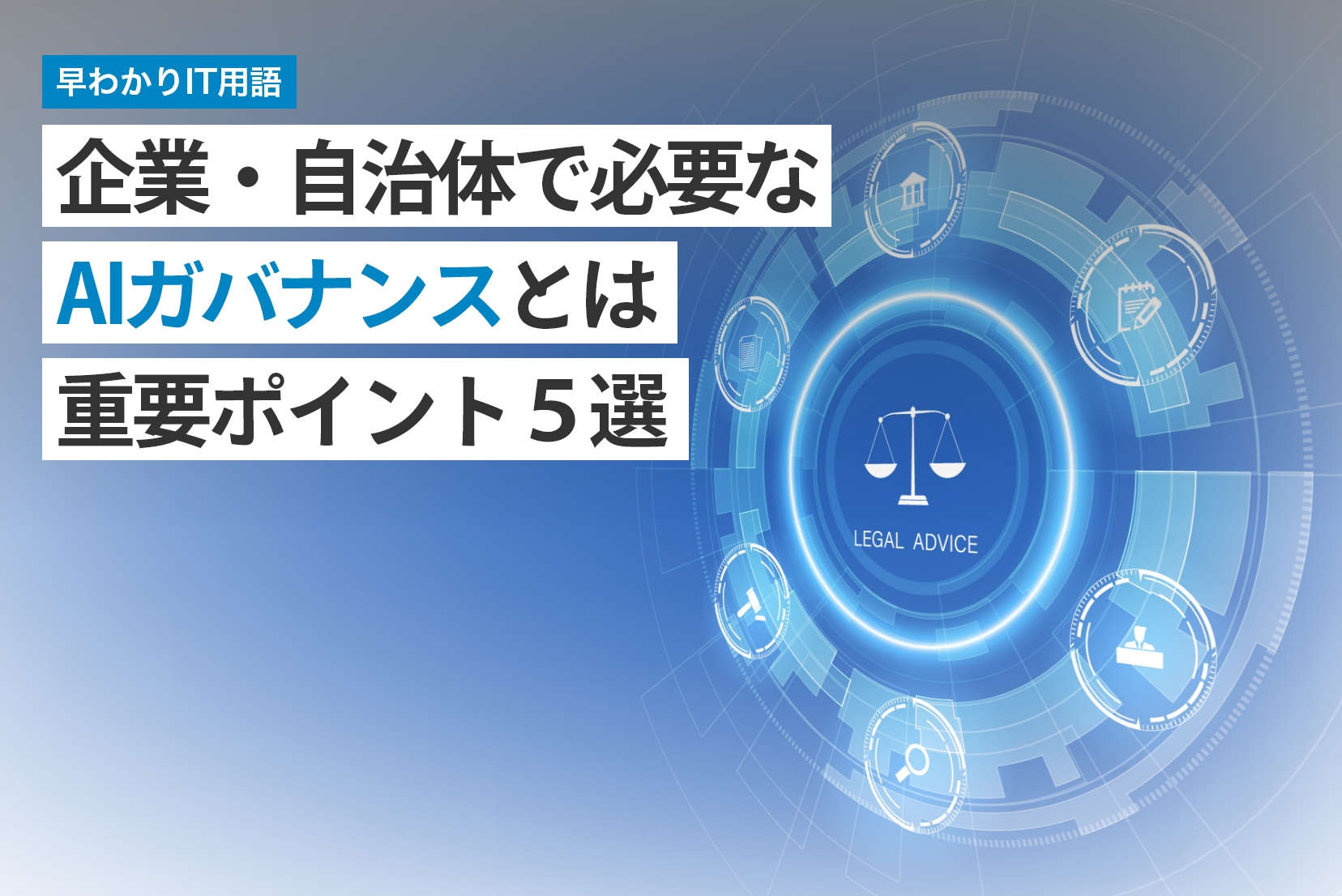
早わかりIT用語
2025年10月24日
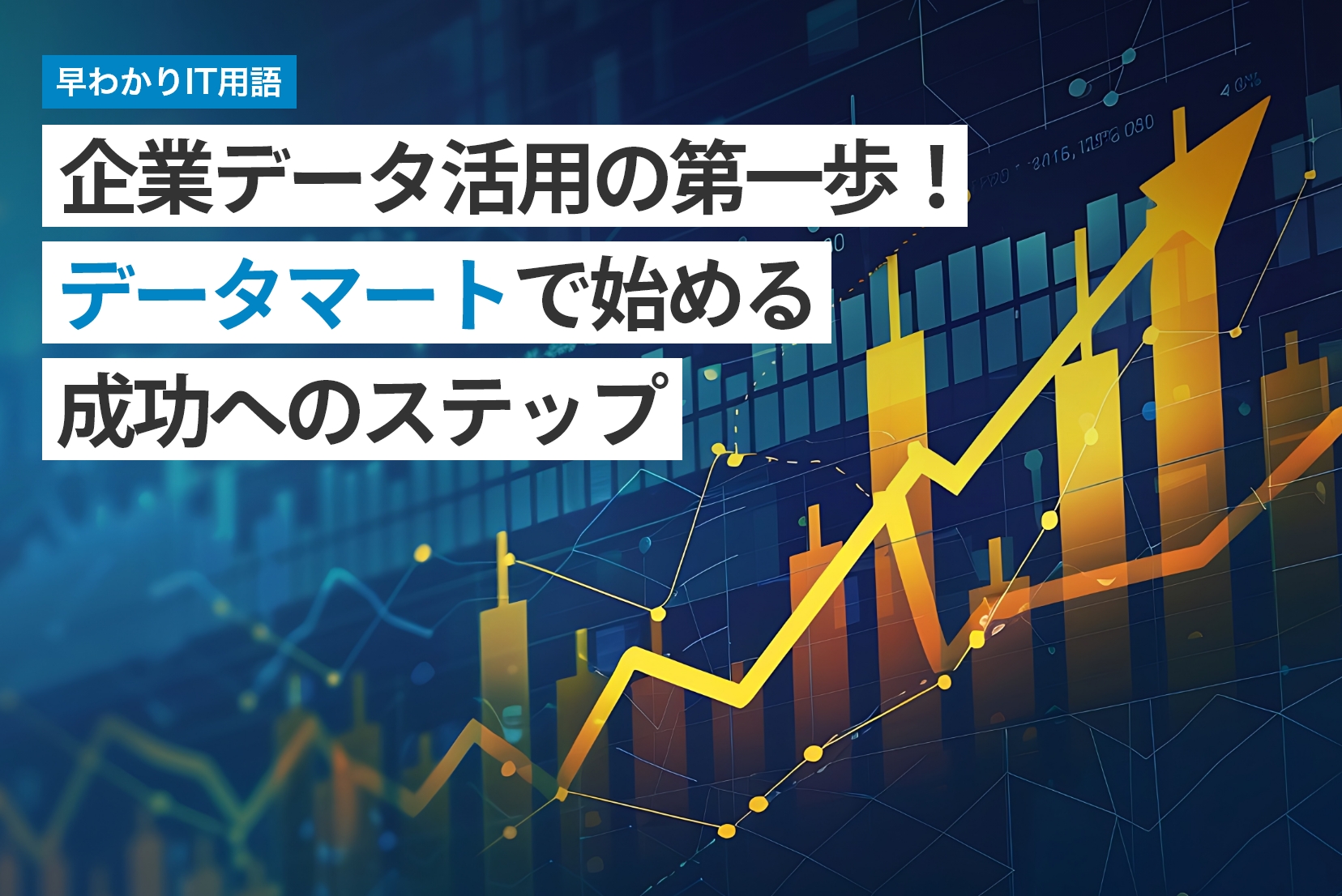
早わかりIT用語
2025年10月16日
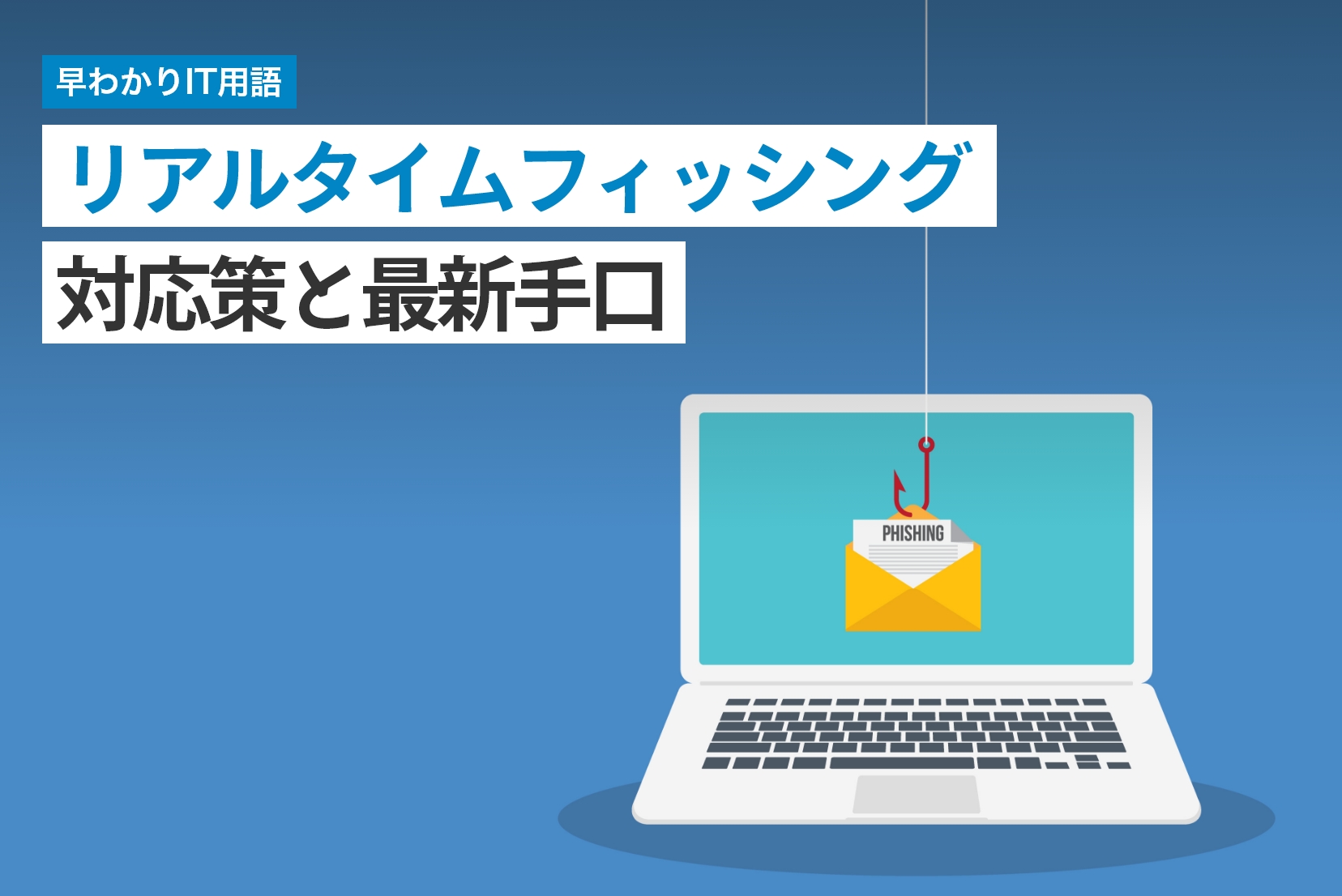
早わかりIT用語
2025年10月10日

早わかりIT用語
2025年10月10日

早わかりIT用語
2025年9月29日
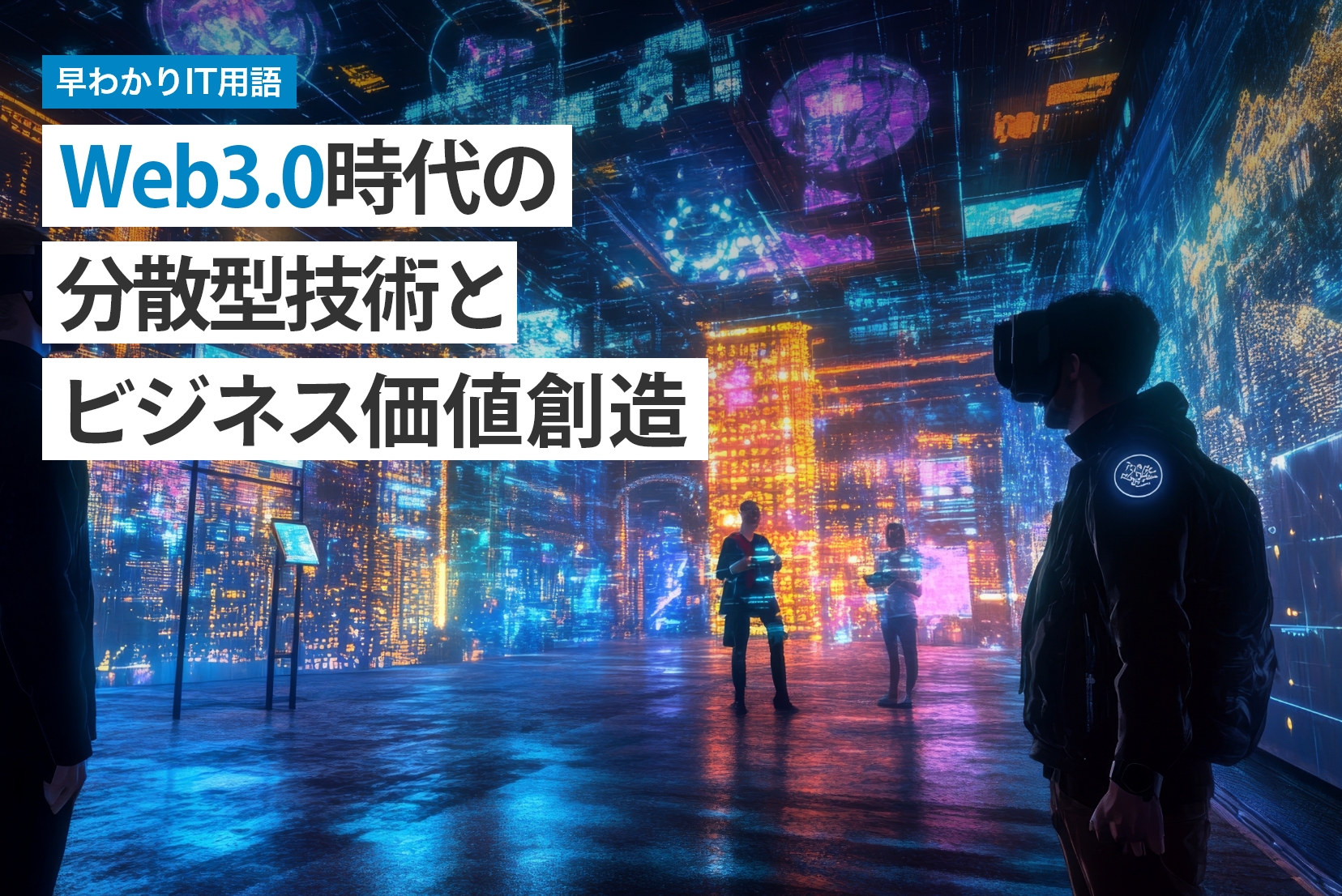
早わかりIT用語
2025年9月24日

早わかりIT用語
2025年9月24日
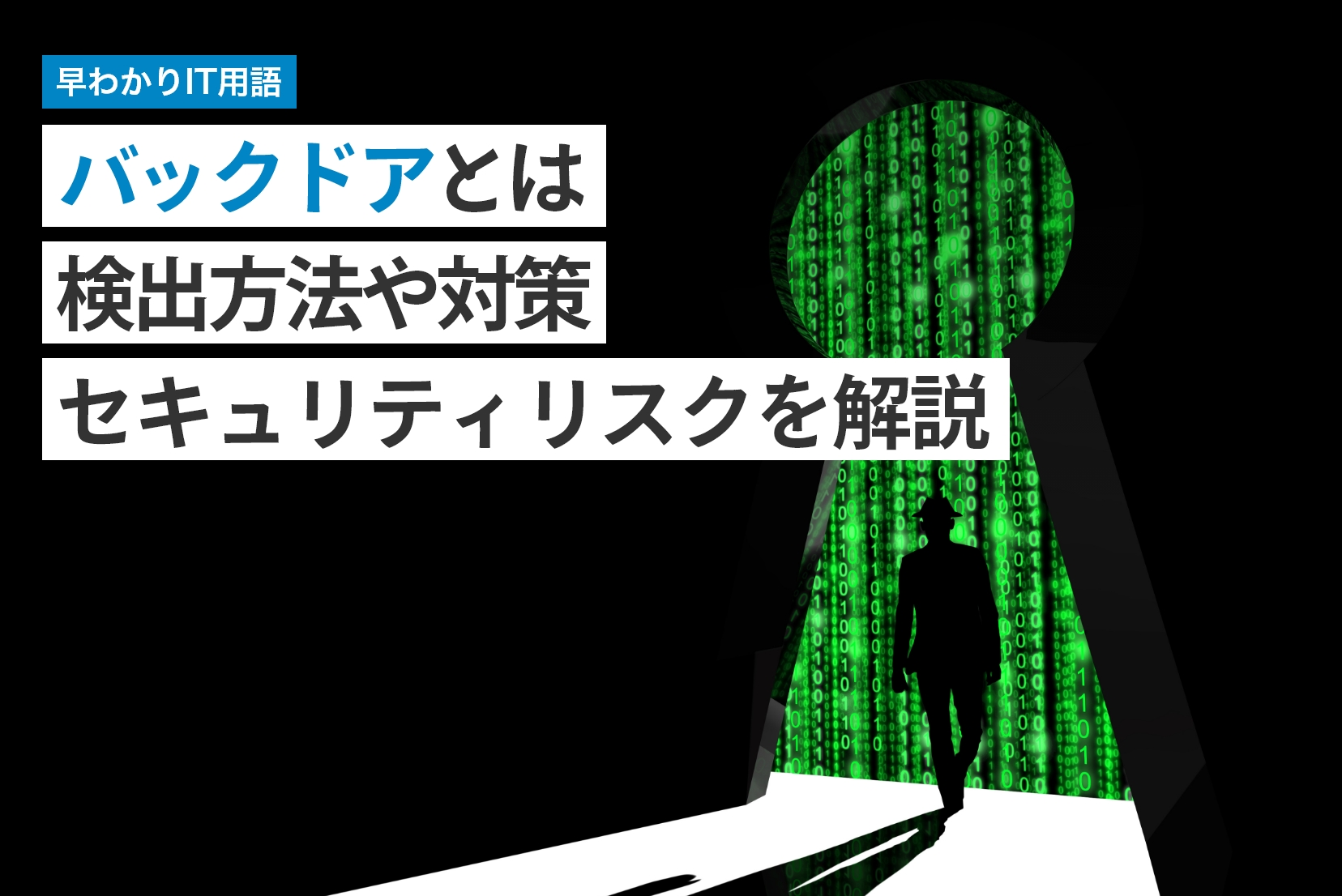
早わかりIT用語
2025年9月24日
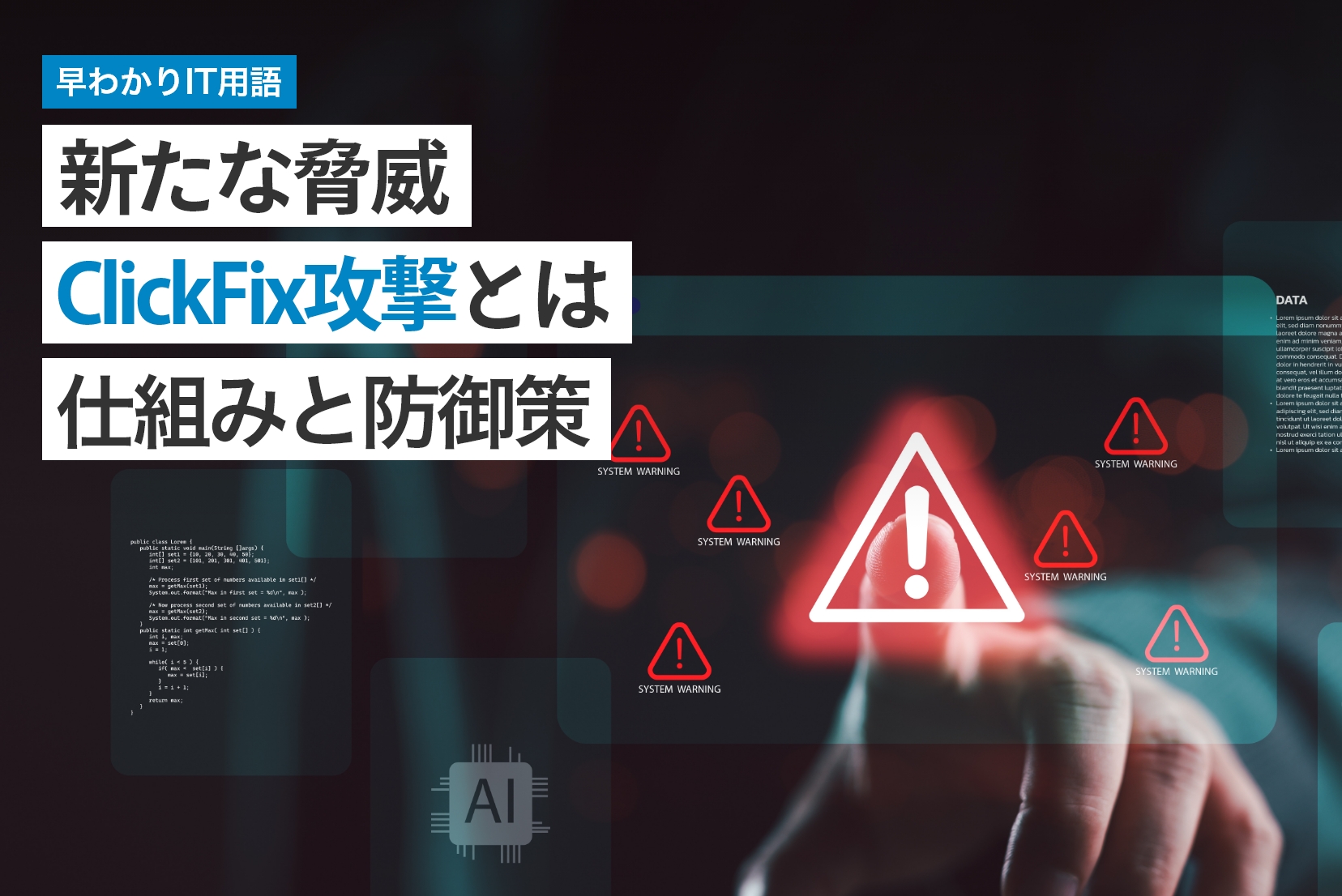
早わかりIT用語
2025年9月3日
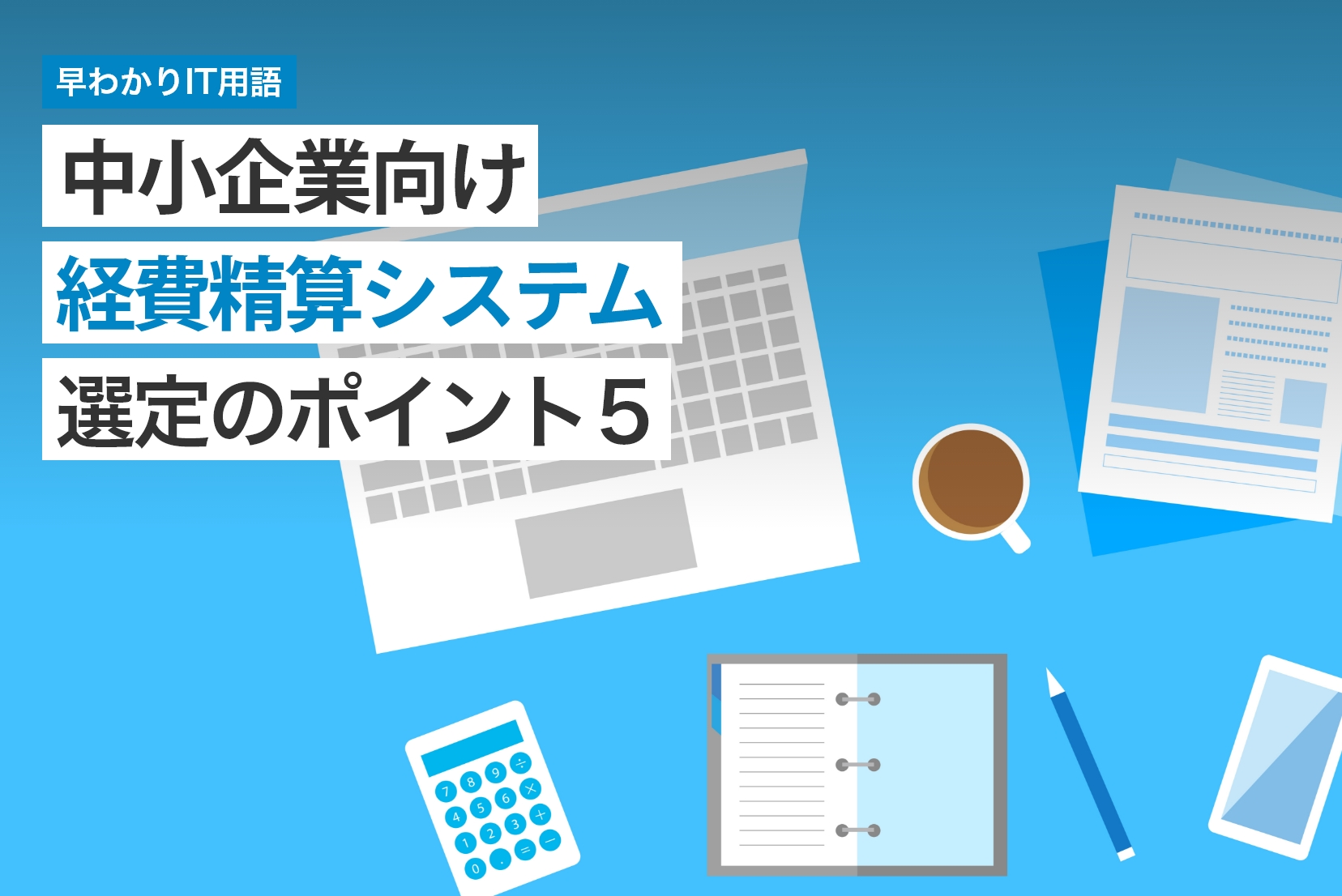
早わかりIT用語
2025年8月28日

早わかりIT用語
2025年8月28日

早わかりIT用語
2025年8月28日

早わかりIT用語
2025年7月25日
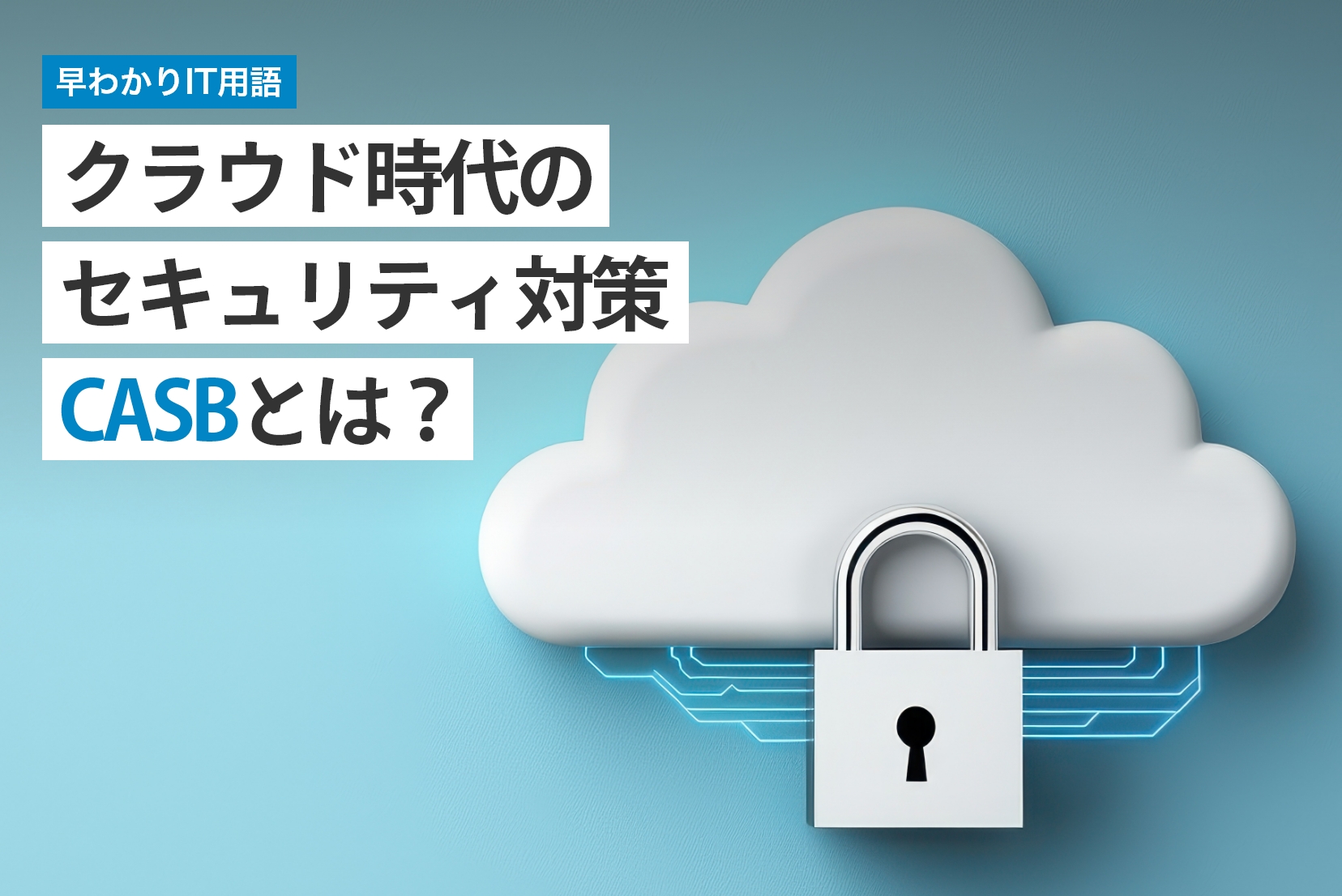
早わかりIT用語
2025年7月25日

早わかりIT用語
2025年7月15日

早わかりIT用語
2025年7月2日
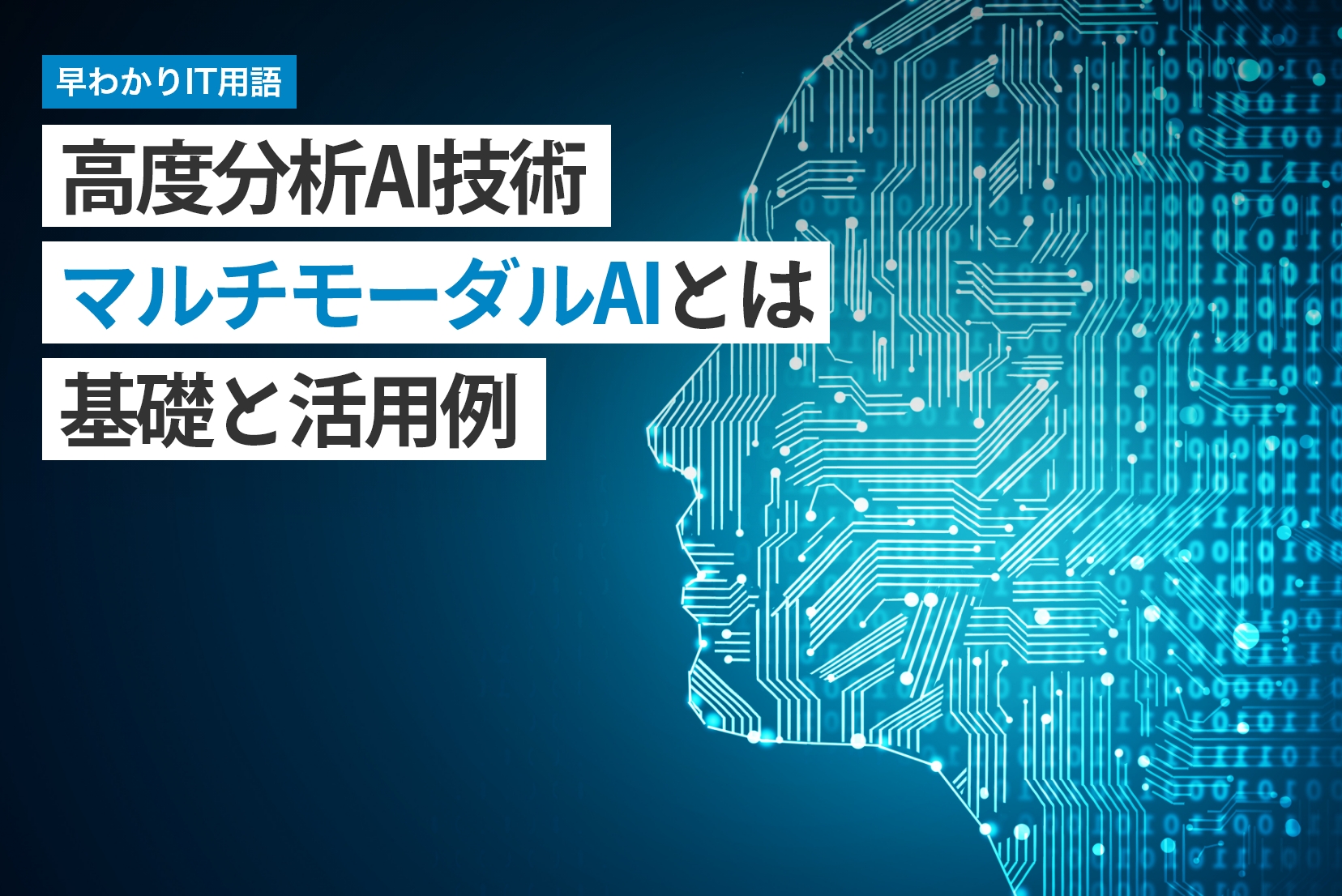
早わかりIT用語
2025年7月2日

早わかりIT用語
2025年6月20日

早わかりIT用語
2025年6月20日
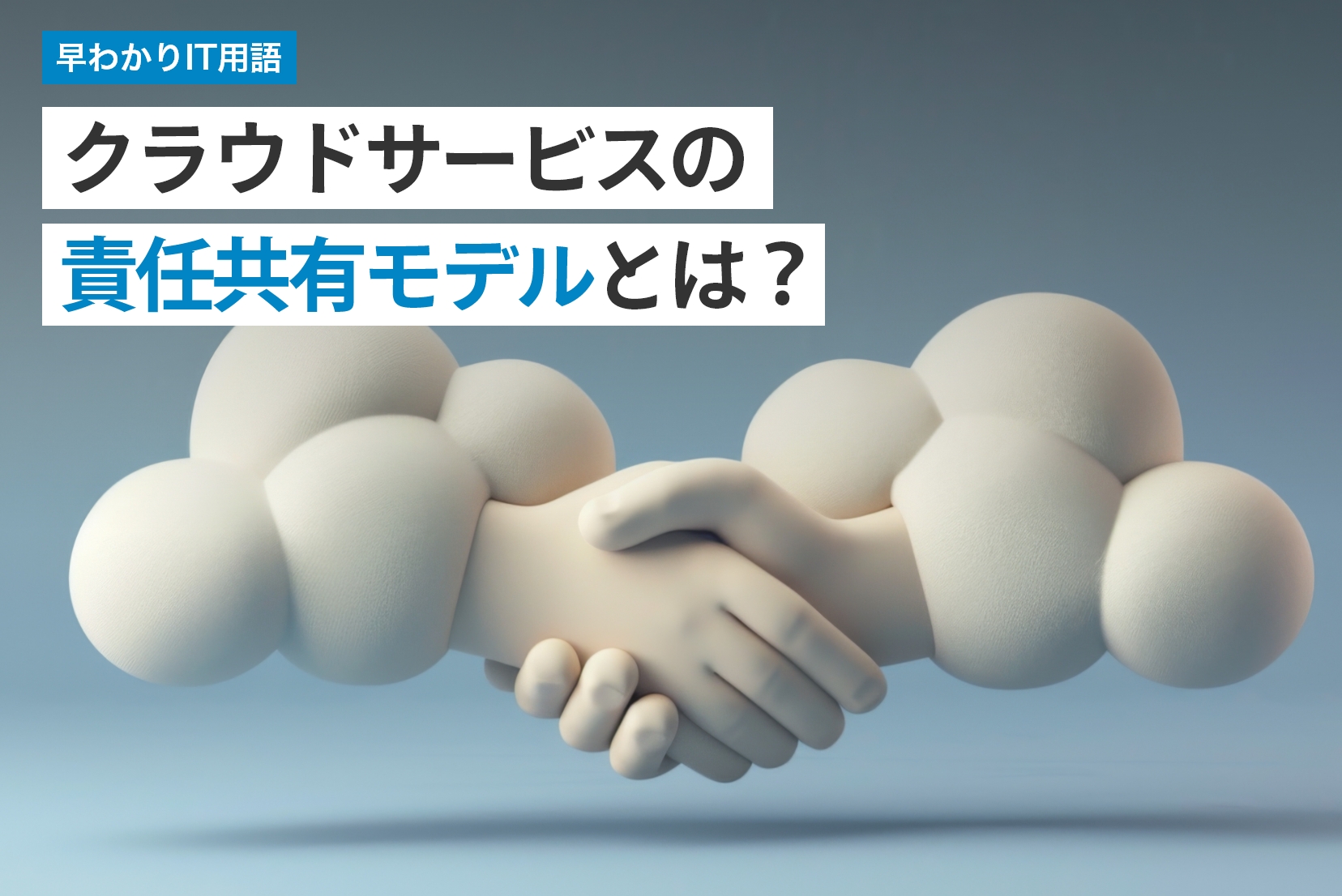
早わかりIT用語
2025年6月10日
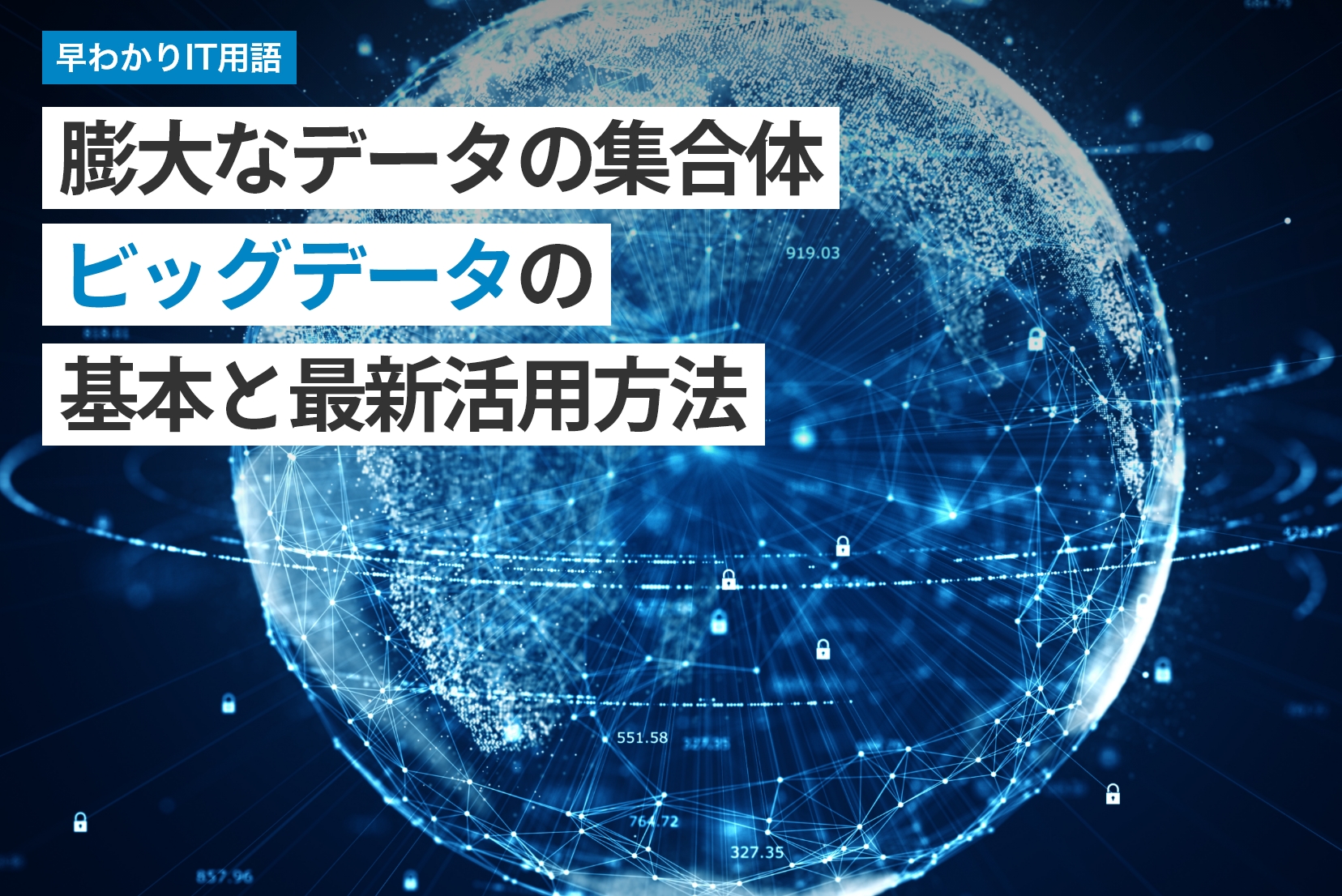
早わかりIT用語
2025年6月10日
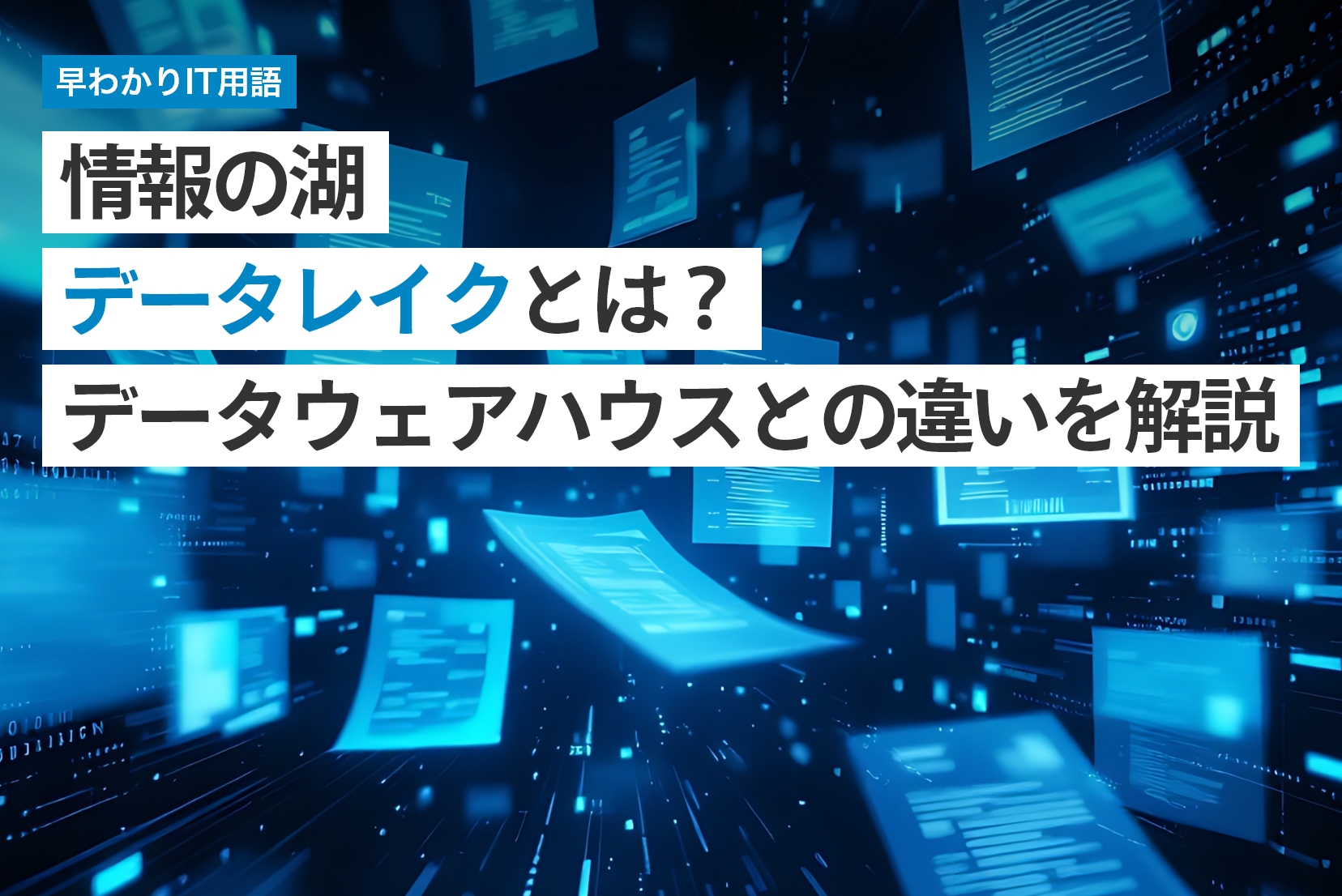
早わかりIT用語
2025年5月27日

早わかりIT用語
2025年5月27日

早わかりIT用語
2025年5月16日
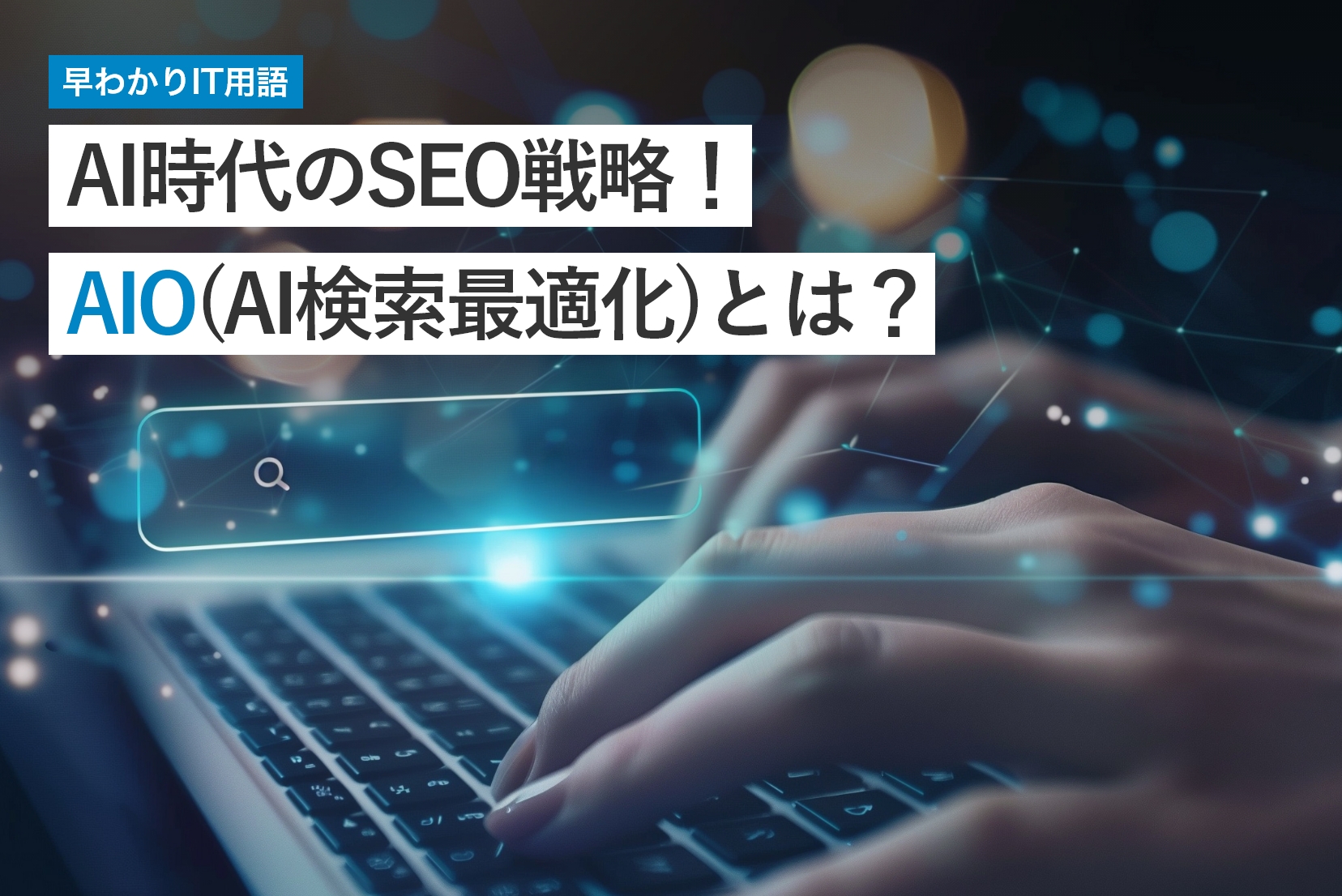
早わかりIT用語
2025年5月16日

早わかりIT用語
2025年5月8日

早わかりIT用語
2025年5月8日

早わかりIT用語
2025年5月8日
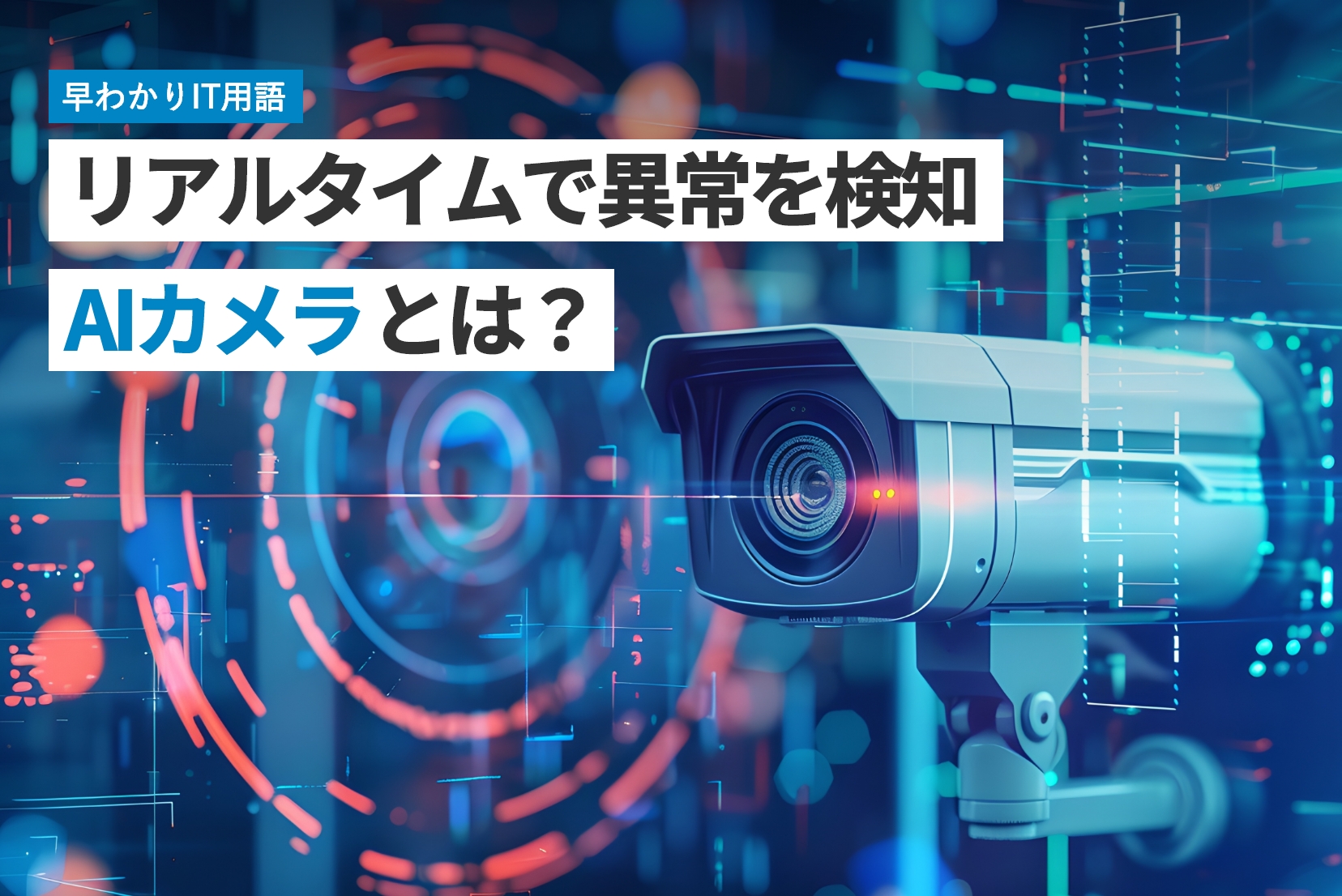
早わかりIT用語
2025年3月31日
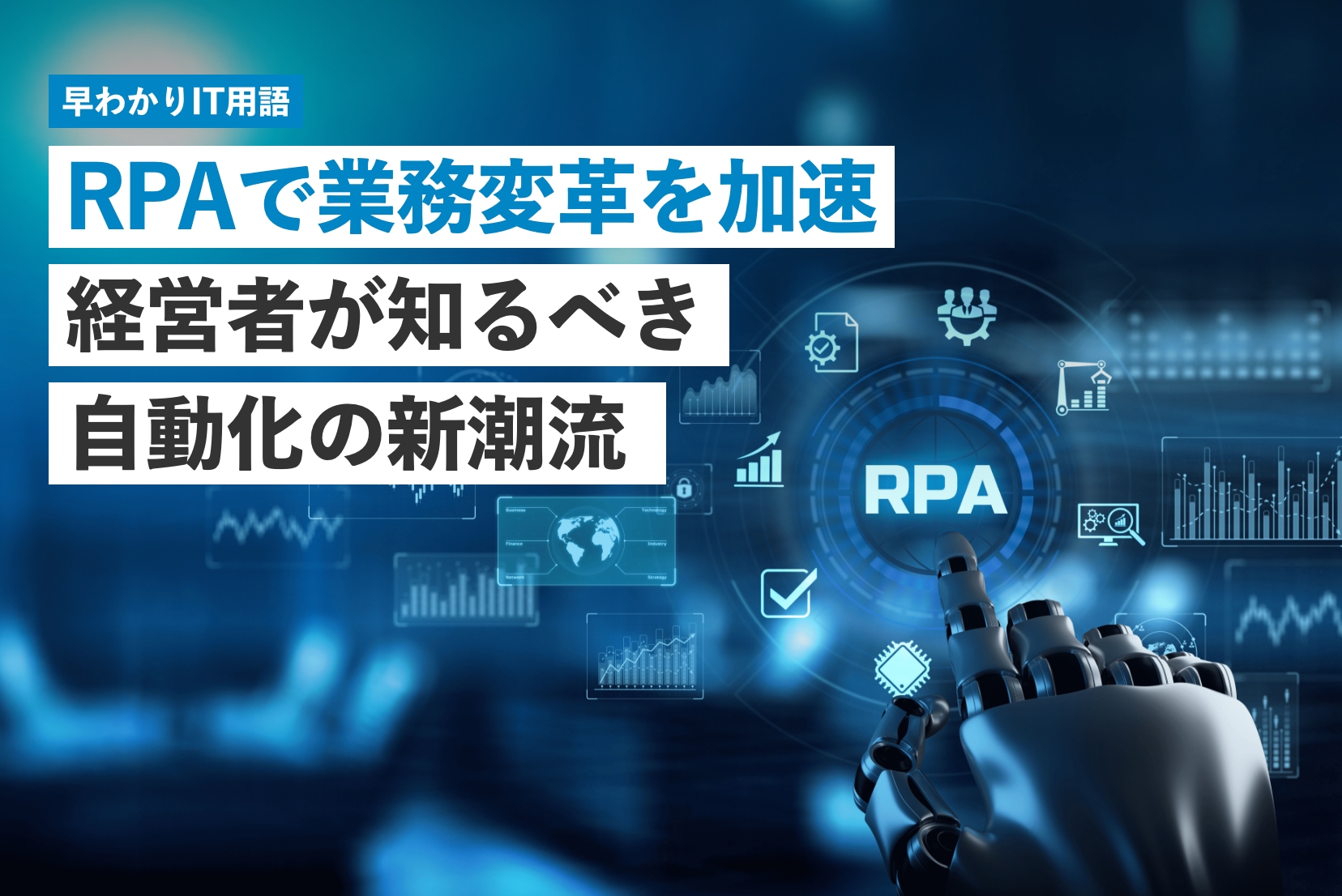
早わかりIT用語
2025年3月18日
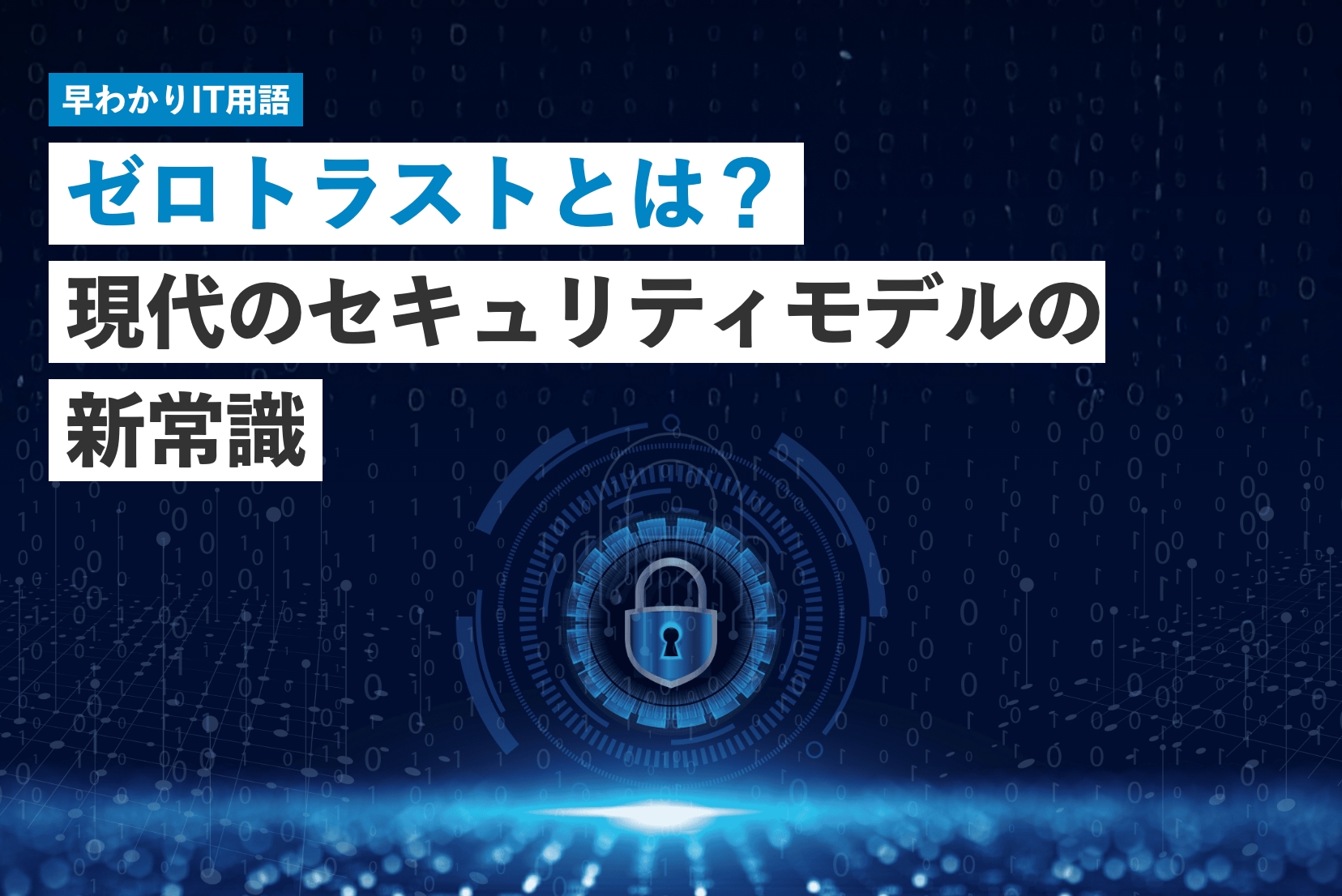
早わかりIT用語
2025年3月18日
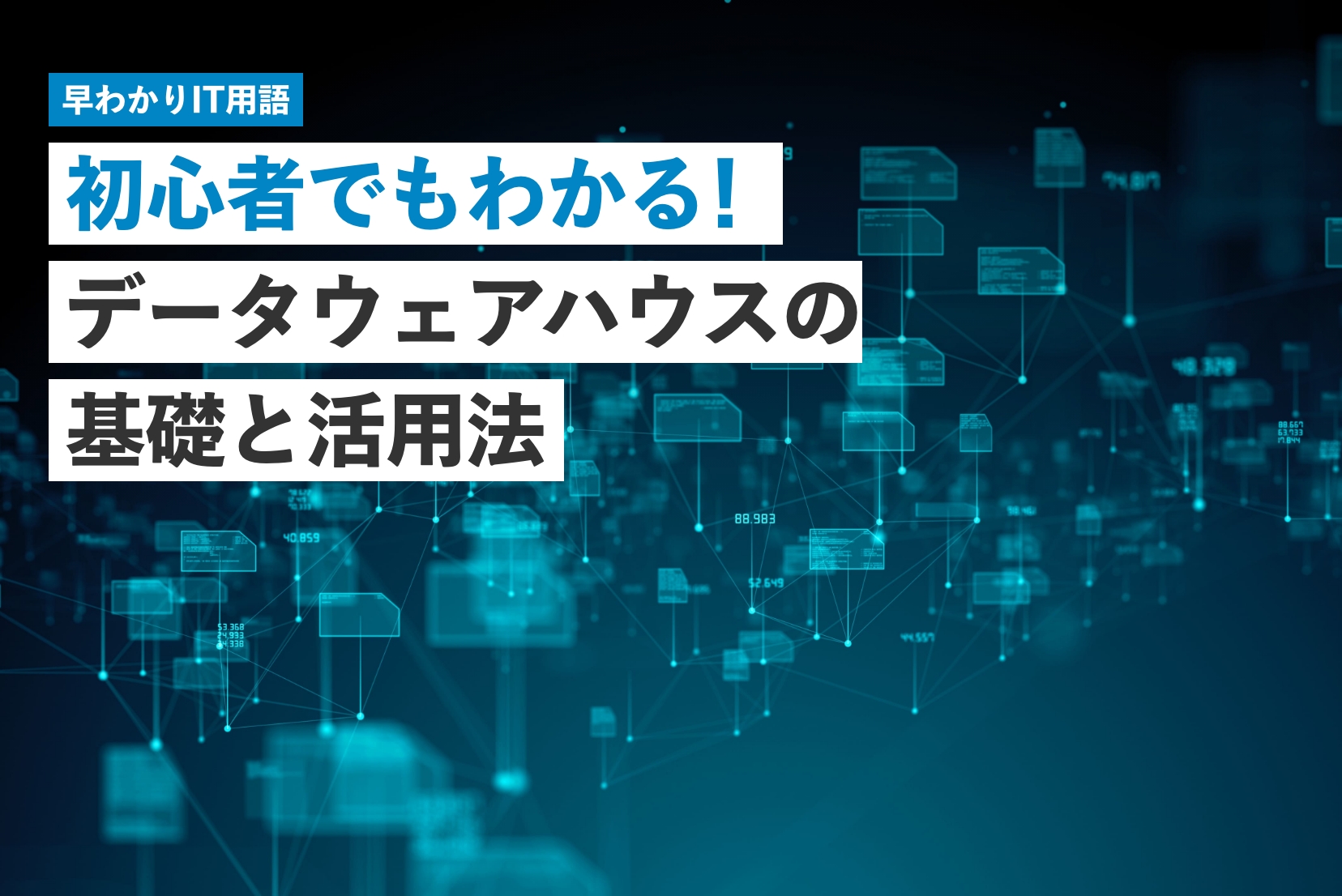
早わかりIT用語
2025年3月18日

早わかりIT用語
2025年2月18日

早わかりIT用語
2024年12月10日

早わかりIT用語
2024年12月10日
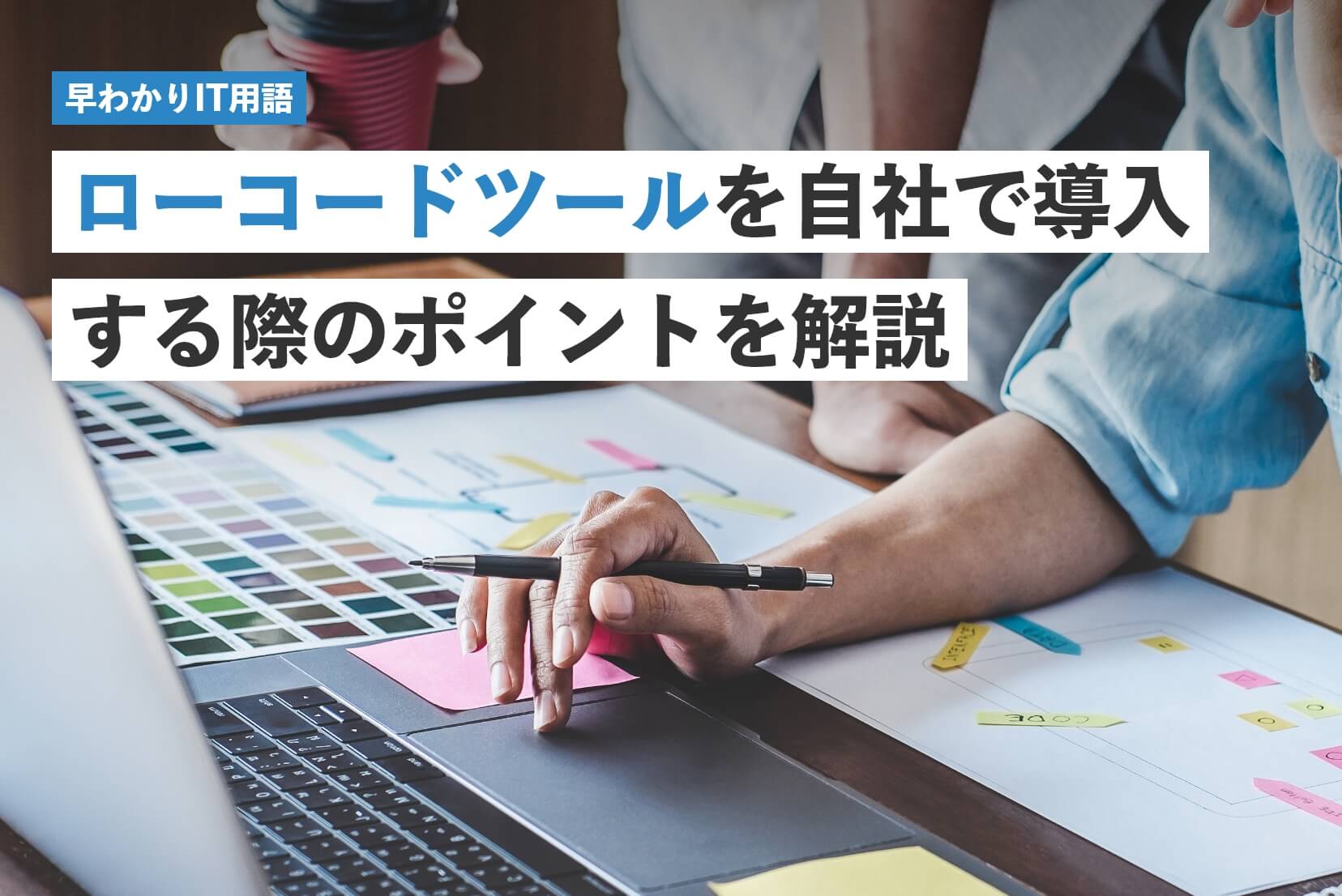
早わかりIT用語
2024年9月6日
タグで絞り込む
すべてのタグを見る話題の記事

早わかりIT用語
2025年5月8日
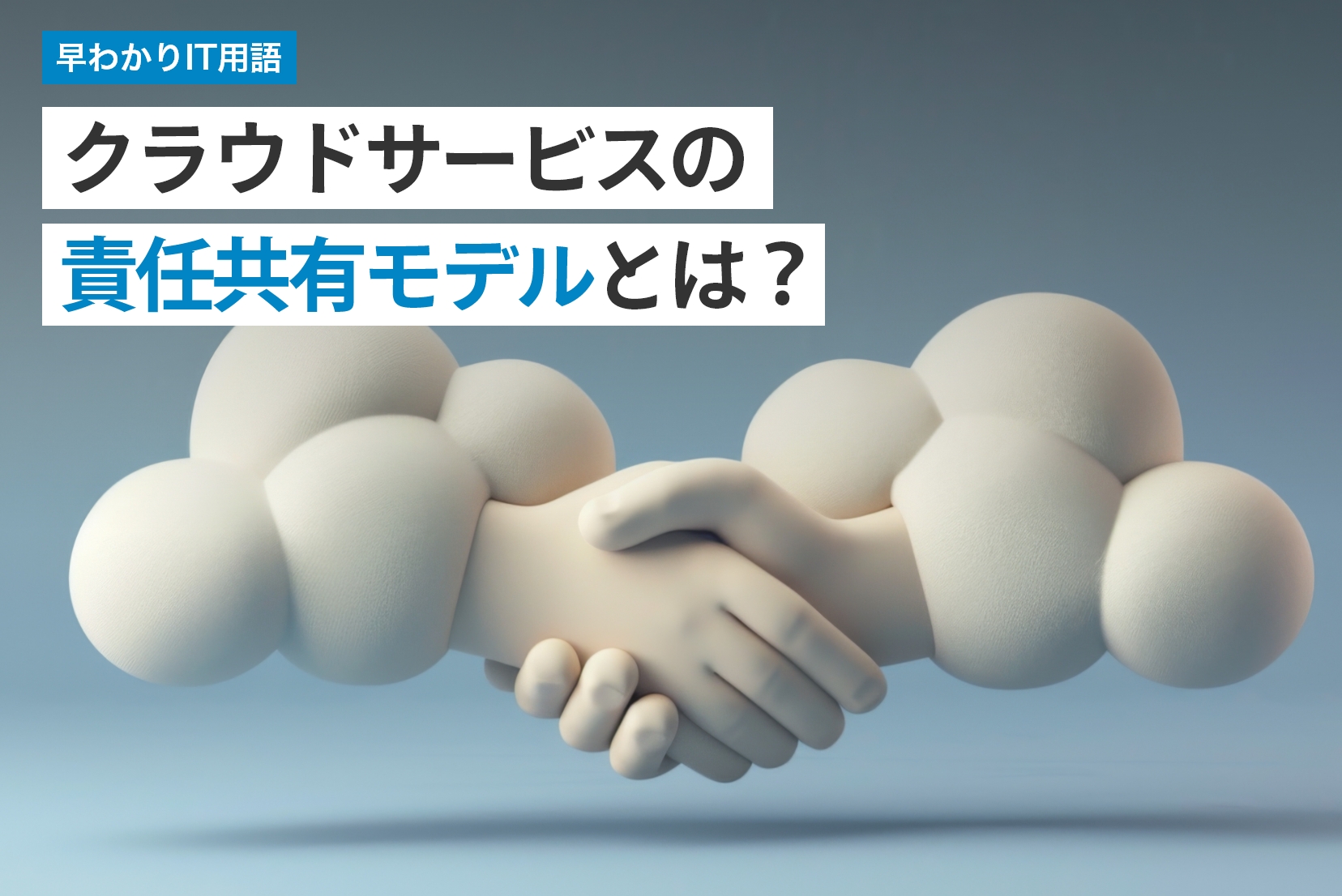
早わかりIT用語
2025年6月10日

早わかりIT用語
2025年12月24日

早わかりIT用語
2025年8月28日



