データマートで始める企業データ活用の第一歩!成功のための7ステップ解説
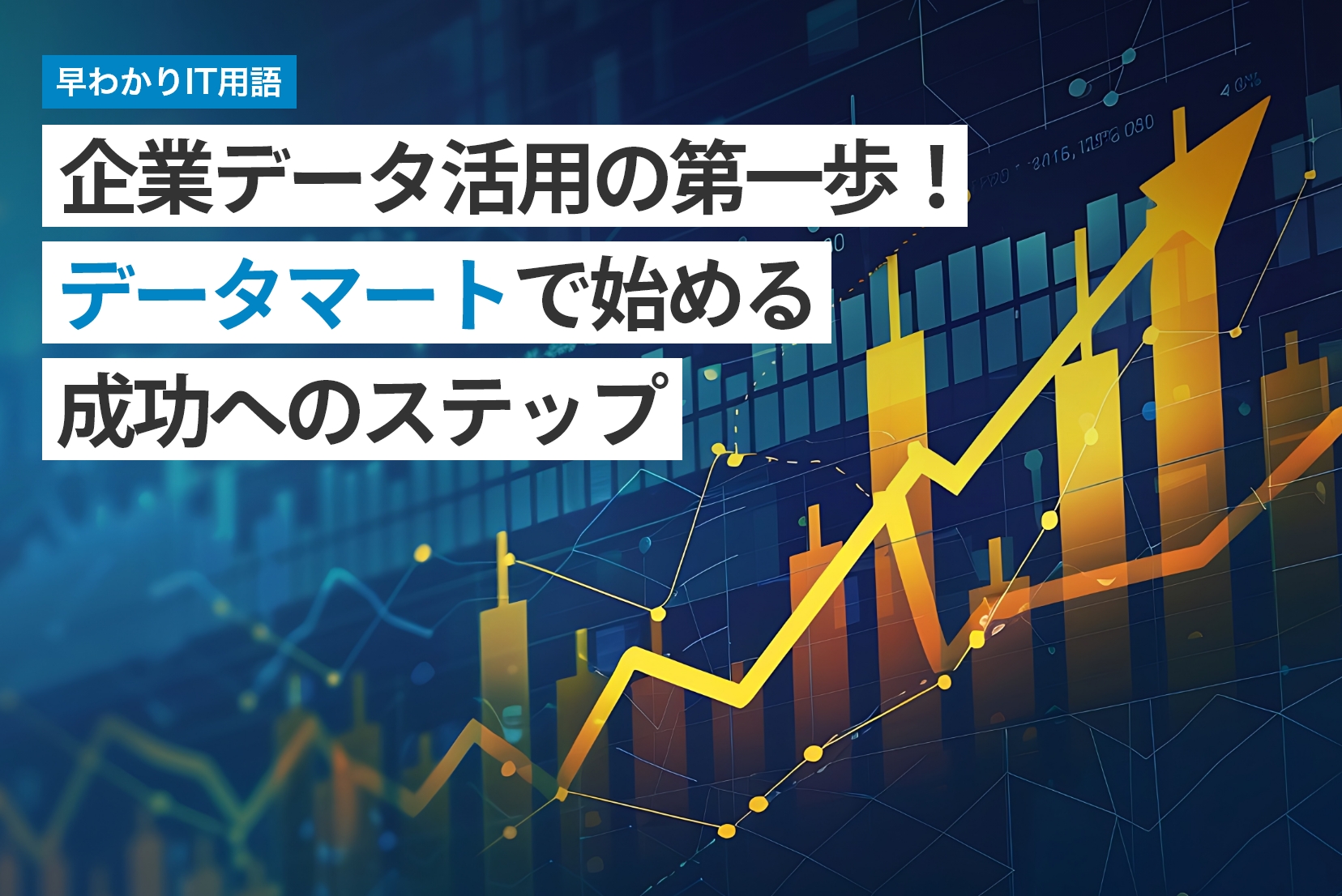
データ活用の重要性が増す一方で、企業が直面する課題は「どこから手をつけるべきか」という点です。特に中堅から大企業の情報システム部門や経営企画部門の担当者にとって、データ基盤の構築から運用までを社内リソースだけで賄うのは難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、データマートを活用した企業データ活用の第一歩を踏み出し、成功のための7ステップを解説します。データマートの導入は、分析リードタイムの短縮や部門別ニーズへの最適化を実現し、現場のデータ活用を促進するための有効な手段です。さらに、BIやAIとの連携による新たな価値創出も期待できます。
- データマートとはシステムに蓄積された膨大なデータの中から、データ利用者の用途、目的などに応じて必要なものだけを抽出・加工し、利用しやすい形に格納したデータベースを指します。
- データの分析リードタイムの短縮や部門別ニーズへの最適化、現場でのデータ活用の促進といったメリットがあります。
- BIツールを活用することで、データの可視化が容易になり、AIを活用した予測分析で、将来のトレンドを予測し、戦略的な意思決定をサポートできます。
-
 熊原 郁光ネットソリューション事業本部 ネットインテグレーション事業部
熊原 郁光ネットソリューション事業本部 ネットインテグレーション事業部2023年、富士ソフトへ入社。配属当初から現在まで、主にTreasureDataを使用したCDP環境の開発業務を担当。
現在は業務と並行してSnowflakeに関しての勉強を進めており、「SnowPro Core」などの資格を保持。
- 1. データマートとは?基本概要とデータウェアハウス・データレイクとの違い
- 2. データマートの3つのタイプ
- 3. データマートが解決する現場の課題とメリット
- 4. データマートの導入効果とDX推進へのインパクト
- 5. データマートの導入成功事例3選
- 6. 導入する際に押さえたいデータマート運用ガバナンスと体制のポイント
- 7. 導入形態(オンプレ・クラウド・ハイブリッド)とコスト感を比較解説
- 8. データマート導入プロジェクトを成功させる7ステップ
- 9. 信頼できるデータマートパートナーの選び方
- 10. 知っておきたいデータマート導入の注意点とリスク管理
- 11. データマートの導入で得られる成果と今後の展望
データマートとは?基本概要とデータウェアハウス・データレイクとの違い

データマートは、企業がデータを効果的に活用するための重要なツールです。データウェアハウスと比較して、特定の部門や業務に特化したデータを集約し、迅速な分析を可能にします。データマートの基本的な概要とデータウェアハウス、データレイクとの違いを明確にし、企業のデータ活用における第一歩を踏み出すための知識を提供します。
データマートとは
データマートとは、システムに蓄積された膨大なデータの中から、データ利用者の用途・目的に応じて必要なものだけを抽出・加工し、利用しやすい形に格納したデータベースを指します。通常、データウェアハウスから抽出されたデータを基に構築され、特定のニーズに応じた分析を迅速に行うことができます。また、データマートは「サブジェクト指向(主題指向)」の考え方に基づいて設計される点が特徴です。サブジェクト指向とは、売上、顧客、商品、在庫といった“分析の対象となる主題(サブジェクト)ごと”にデータを整理・統合する設計手法のことです。これにより、業務観点で必要な情報がひとまとまりに整理され、ユーザーは目的に沿った分析を効率的に行えるようになります。データマートの特徴として、データの取り扱いが簡単であることや、特定のユーザーグループに最適化されていることが挙げられます。これにより、部門ごとのデータ活用が促進され、業務効率が向上します。
データマートのスタースキーマとは
スタースキーマとは、データマートやデータウェアハウスで使われる代表的なデータ構造のひとつで、分析に最適化されたデータベースの設計手法です。中心に数値データを持つ「事実テーブル」を置き、その周囲を商品・顧客・時間などの「次元テーブル」が囲む構造です。星形のように単純でわかりやすく、分析や集計を高速に行える点が特徴です。
データウェアハウス(DWH)とデータマートの違い
データウェアハウスは、企業全体のデータを統合的に管理する大規模なデータベースです。構築にはETLツールなどを使用して、様々なデータベースのデータを自動で格納します。一方、データマートはデータウェアハウスからのデータソースを抽出し、特定の目的に特化したデータセットを提供します。データウェアハウスは広範なデータを扱うため、構築や運用に時間とコストがかかることがありますが、データマートは特定のニーズに応じた迅速な分析を可能にし、導入が比較的容易です。
データウェアハウスについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
初心者でもわかる!データウェアハウスの基礎と活用法
データレイクとデータマートの違い
データマートは、特定の目的に特化したデータセットを提供する小規模なデータベースです。データレイクは、構造化・非構造化を問わず、あらゆるデータをそのままの形で保存する大規模なストレージです。データマートは迅速な分析を可能にし、データレイクは多様なデータの蓄積と柔軟な活用を支援します。
データレイクについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
データレイクとは?初心者向けにデータウェアハウスとの違いを徹底解説
| 項目 | データマート | データウェアハウス(DWH) | データレイク |
| 目的 | 特定部門向けの分析用データ提供 | 全社的な分析基盤 | あらゆる形式のデータを蓄積・活用 |
| データ形式 | 構造化データ | 構造化データ | 構造化・半構造化・非構造化データ |
| 拡張性 | 中程度 | 中〜高 | 非常に高 |
| コスト | 比較的低コスト | 高コスト(整備・運用が必要) | 初期コスト低だが運用次第で変動 |
| 主な用途 | 部門別レポート、KPI分析 | 経営分析、BIツール連携 | 機械学習、ビッグデータ分析、ログ解析 |
| 導入スピード | 比較的早い | 時間がかかる | 早い(整備は後回しにできる) |
代表的な利用ケース
データマートは、営業部門やマーケティング部門など、特定の部門でのデータ分析に活用されます。例えば、マーケティング部門では、顧客の購買履歴や行動データを基にしたターゲティング分析が行われます。また、営業部門では、売上データを基にしたパフォーマンス分析が可能です。これにより、各部門が迅速に意思決定を行い、ビジネス成果を向上させることができます。
データマートの3つのタイプ
独立型データマート
独立型データマートは、データウェアハウスに依存せず、部門が独自に構築するデータマートです。必要なデータを各部門のシステムから直接収集するため、短期間で導入しやすく柔軟性も高い点が特徴です。一方で、部門ごとにデータ構造や定義が異なることが多く、全社的なデータ整合性を確保しにくいという課題があります。
従属型データマート
従属型データマートは、企業全体のデータを集約したデータウェアハウスから必要な情報を抽出して構築します。全社共通のデータ定義が適用されるため、部門間でデータの一貫性が保たれ、信頼性の高い分析が可能です。ただし、DWHの整備が前提となり、構築や運用に時間とコストがかかる点がデメリットです。
ハイブリッド型データマート
ハイブリッド型データマートは、データウェアハウスに加えて外部システムや部門データなど複数の情報源を組み合わせて構築するタイプです。必要なデータを柔軟に取り込めるため、迅速な分析や新規施策への対応がしやすいことが強みです。しかし、複数のデータソースを扱うため、設計や管理が複雑化する傾向があります。
3つのタイプの比較表
| タイプ | 概要 | メリット | デメリット | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 独立型データマート | 部門が独自に構築し、DWHに依存しないデータマート。 | 短期間で構築可能。 部門のニーズに柔軟に対応できる。 |
データ定義がバラバラになりやすい。 全社整合性が低い。 |
小規模でまず分析基盤を整えたい場合。 スピード重視の現場。 |
| 従属型データマート | DWHから抽出したデータで構築するデータマート。 | データの一貫性が高い。 信頼性の高い分析が可能。 |
DWH構築が前提で時間とコストがかかる。 | 全社統一でデータ活用を進めたい場合。 |
| ハイブリッド型データマート | DWHと外部データなど複数ソースを組み合わせて構築。 | 柔軟にデータを取り込める。 迅速な分析が可能。 |
構造が複雑化しやすく、管理が難しい。 | 多様なデータを扱うマーケティング部門。 最新データをすぐ使いたい場合。 |
データマートが解決する現場の課題とメリット

データマートは、企業が抱えるデータ活用の課題を解決するための強力なツールです。特に、データの分析リードタイムの短縮や部門別ニーズへの最適化、現場でのデータ活用の促進といったメリットがあります。企業全体のデータ活用がスムーズになり、ビジネスの意思決定が迅速かつ的確に行えるようになります。
分析リードタイムの短縮
データマートを導入することで、分析リードタイムが大幅に短縮されます。従来のデータ分析では、データの抽出や加工に多くの時間がかかっていましたが、データマートはこれらのプロセスを効率化します。これにより、分析結果を迅速に得ることができ、ビジネスの意思決定をスピーディに行うことが可能になります。
部門別ニーズへの最適化
データマートは、各部門の特定のニーズに応じたデータセットを提供することができます。営業部門やマーケティング部門が自分たちの視点でデータを分析しやすくなり、より具体的なインサイトを得ることができます。部門ごとのニーズに応じたデータ活用が可能になることで、全社的なデータ活用の効率が向上します。
現場のデータ活用促進
データマートは、現場でのデータ活用を促進するための重要な役割を果たします。現場の担当者が必要なデータに迅速にアクセスできるようになることで、日常業務の中でデータを活用する機会が増えます。これにより、現場の業務効率が向上し、データに基づいた意思決定が可能になります。
データマートの導入効果とDX推進へのインパクト

データマートの導入は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させる重要な要素です。データの集約と分析を効率化することで、迅速な意思決定を可能にし、ビジネスの競争力を高めます。この章では、データマートがどのようにDX推進に寄与するのか、その具体的な効果を探ります。
分析スピード向上と意思決定の質の変化
データマートの導入により、分析スピードが飛躍的に向上します。従来のデータウェアハウスと比較して、特定の部門やプロジェクトに特化したデータセットを迅速に構築できるため、必要な情報を即座に取得可能です。これにより、経営層や現場の担当者は、より迅速かつ正確な意思決定を行うことができ、ビジネスの方向性を柔軟に調整することが可能になります。
業務改善例(営業・マーケ・現場部門)
データマートは、営業やマーケティング、現場部門における業務改善にも大きく貢献します。例えば、営業部門では、顧客データをもとにしたターゲティング精度の向上が期待できます。マーケティング部門では、キャンペーンの効果測定が迅速に行えるため、リアルタイムでの戦略修正が可能です。現場部門では、プロセスの効率化やコスト削減に寄与し、全体的な業務効率を高めます。
BI・AIとの連携による新たな価値創出
データマートは、BI(ビジネスインテリジェンス)やAI(人工知能)との連携により、新たな価値を創出します。BIツールを活用することで、データの可視化が容易になり、経営層や現場の担当者が直感的にデータを理解できるようになります。また、AIを活用した予測分析により、将来のトレンドを予測し、戦略的な意思決定をサポートします。これにより、企業は競争優位性を確保し、持続的な成長を実現することが可能です。
データマートの導入事例3選
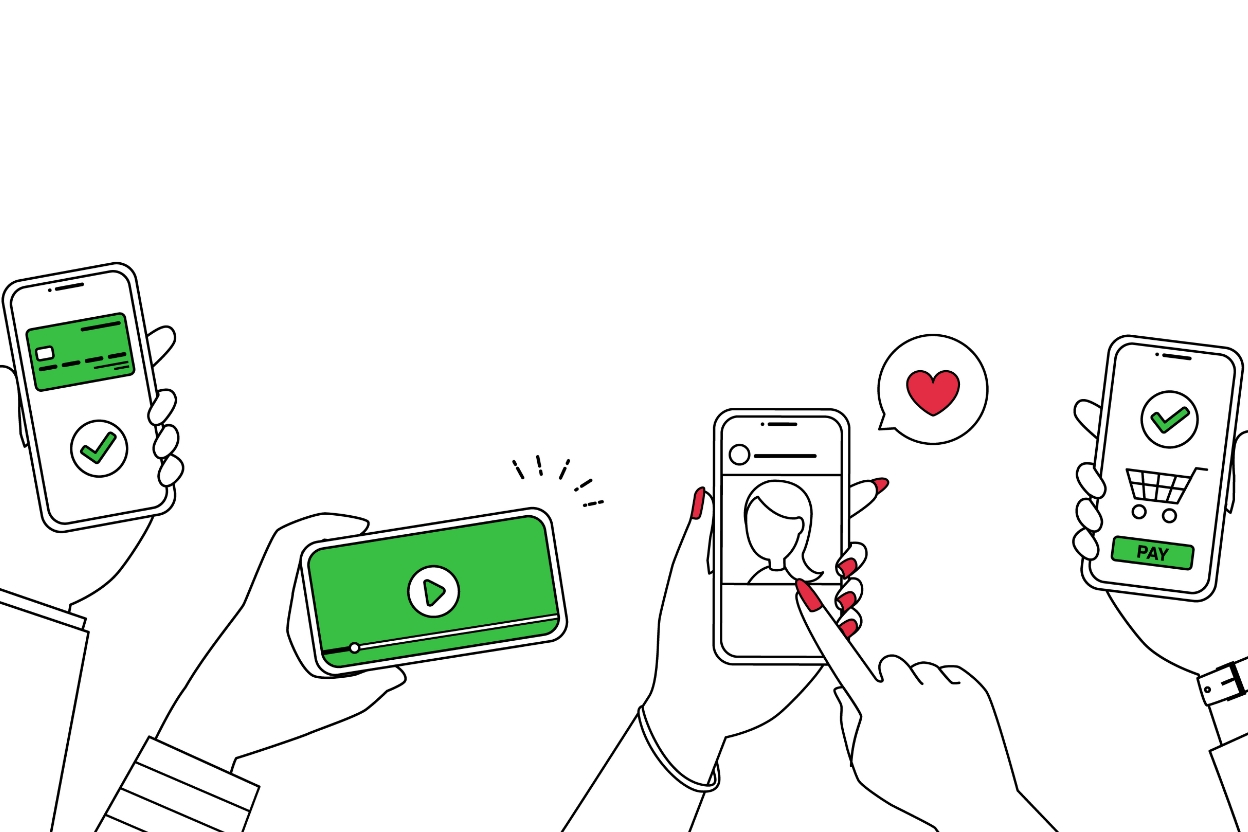
データマートの導入は、企業がデータ活用を進める上で重要なステップです。企業がどのようにデータマートを活用して成功を収めたのか、具体的な導入事例を通じて解説します。
大手製造業での部門横断データ活用事例
大手製造業では、部門間のデータを統合し、全社的な視点での分析を可能にするためにデータマートを導入しました。これにより、製造プロセスの効率化や品質管理の向上が実現され、結果として生産性が大幅に向上しました。特に、リアルタイムでのデータ分析が可能になったことで、迅速な意思決定が可能となり、競争力を高めることができました。
流通業の顧客分析高度化事例
流通業界では、顧客の購買行動を詳細に分析するためにデータマートを活用しています。これにより、顧客のニーズを的確に把握し、パーソナライズされたサービスを提供することが可能になりました。結果として、顧客満足度の向上やリピート率の増加が見られ、売上の拡大に寄与しています。データマートの導入により、マーケティング施策の精度が向上し、効果的なキャンペーンの実施が可能となりました。
金融業の迅速なリスク分析事例
金融業界では、リスク管理の精度を高めるためにデータマートを導入しました。これにより、膨大で複雑な取引データを迅速に分析し、潜在的なリスクを早期に発見することが可能になりました。特に、AI技術と組み合わせることで、リスク予測の精度が向上し、適切な対策を迅速に講じることができるようになりました。これにより、金融機関は安定した運営を維持しつつ、顧客への信頼性を高めることができました。
導入する際に押さえたいデータマート運用ガバナンスと体制のポイント

データマートの導入は、企業のデータ活用を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、適切な運用ガバナンスと体制の構築が不可欠です。データマートを導入する際に押さえておくべきガバナンスのポイントと、効果的な体制構築の方法について詳しく解説します。
セキュリティ・権限制御の基本
データマートの運用において、セキュリティと権限制御は最も重要な要素の一つです。データの不正アクセスを防ぐためには、ユーザーごとにアクセス権を厳密に設定し、必要なデータのみを閲覧可能にすることが求められます。また、データの暗号化やログの監視を行うことで、セキュリティの強化を図ることができます。企業の機密情報を守りつつ、安心してデータ活用を進めることが可能になります。
データ品質維持のための運用指針
データマートの効果を最大限に引き出すためには、データの品質を維持することが不可欠です。データの整合性や一貫性を保つためには、定期的なデータクレンジングやデータの更新を行うことが重要です。また、データの出所や更新履歴を明確にすることで、データの信頼性を高めることができます。これにより、分析結果の精度が向上し、より的確な意思決定が可能となります。
ベンダー活用と自社体制構築のバランス
データマートの導入においては、ベンダーの活用と自社体制の構築のバランスが重要です。ベンダーを活用することで、専門的な知識や技術を迅速に取り入れることができますが、自社内での体制構築も同時に進める必要があります。これにより、ベンダー依存を避け、長期的な運用を見据えた体制を整えることが可能です。自社のリソースを最大限に活用しつつ、外部の専門家の力を借りることで、効率的なデータマート運用が実現します。
導入形態(オンプレ・クラウド・ハイブリッド)とコスト感を比較解説

データマートの導入において、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドの各形態は、それぞれ異なる特徴とコスト感を持っています。各形態の特性を理解し、企業のニーズに最適な選択をするための指針を提供します。情報システム部門の担当者や経営企画部門のマネージャーが、導入形態の違いを把握し、コスト面でのメリットを最大化するための知識を得ることができます。
オンプレミス型の特徴とコスト感
オンプレミス型は、自社内にサーバーを設置し、データを管理する形態です。セキュリティ面での安心感があり、カスタマイズ性が高いのが特徴です。しかし、初期投資が大きく、ハードウェアの維持管理にコストがかかるため、長期的な視点での費用対効果を考慮する必要があります。特に、既存のITインフラを活用したい企業にとっては、オンプレミス型が適しています。
クラウド型の特徴とコスト感
クラウド型は、インターネットを通じてデータを管理する形態で、初期投資が少なく、スケーラビリティに優れています。必要に応じてリソースを増減できるため、コストの最適化が可能です。また、最新の技術を迅速に取り入れられる点も魅力です。ただし、データのセキュリティやガバナンスに関しては、クラウドプロバイダーとの契約内容をしっかり確認することが重要です。
ハイブリッド型の特徴とコスト感
ハイブリッド型は、オンプレミスとクラウドの利点を組み合わせた形態です。データの機密性や法規制に応じて、どちらの環境を利用するかを選択できる柔軟性があります。これにより、セキュリティとコストのバランスを取りながら、最適なデータ管理が可能です。選び方としては、自社のデータ特性や業務要件を考慮し、どのデータをどの環境で管理するかを明確にすることが求められます。
データマート導入プロジェクトを成功させる7ステップ

データマートの導入は、企業のデータ活用を飛躍的に向上させるための重要なプロジェクトです。データマート導入を成功させるための具体的な7つのステップを紹介します。これにより、情報システム部門や経営企画部門の担当者が、プロジェクトを円滑に進めるための道筋を明確に理解できるようになります。
1. データ活用の目的整理とゴール設定
データマート導入の第一歩は、データ活用の目的を明確にし、具体的なゴールを設定することです。これにより、プロジェクト全体の方向性が定まり、関係者間での共通理解が深まります。目的を整理する際には、現場のニーズや経営層の期待を考慮し、データ活用がどのようにビジネス成果に結びつくかを明確にすることが重要です。
2. 関係部門・ステークホルダーとの連携体制構築
データマート導入には、関係部門やステークホルダーとの連携が欠かせません。プロジェクトの成功には、各部門のニーズを把握し、適切なコミュニケーション体制を構築することが求められます。これにより、データの活用が部門横断的に進められ、全社的なデータ活用の推進が可能となります。
3. 現状データの棚卸しと課題把握
現状のデータを棚卸しし、課題を把握することは、データマート導入の基盤を整えるために不可欠です。データの質や量、アクセス権限などを確認し、どのような課題が存在するのかを明確にします。これにより、データマート構築に向けた具体的な改善策を講じることができます。
4. データマート構築・設計方針の策定
データマートの構築には、設計方針の策定が重要です。データの収集、整理、分析のプロセスを明確にし、どのような技術やツールを用いるかを決定します。設計方針を明確にすることで、プロジェクトの進行がスムーズになり、期待される成果を確実に得ることができます。
5. 技術・ツール(AI/Snowflake等)選定と導入
データマートの構築には、適切な技術やツールの選定が不可欠です。AIやSnowflakeなどの最新技術を活用することで、データ分析の精度や効率が向上します。選定した技術やツールを導入する際には、社内のリソースやスキルセットを考慮し、最適なソリューションを選ぶことが重要です。
6. 運用・保守体制の設計
データマートの運用・保守体制を設計することで、長期的なデータ活用が可能になります。運用体制の設計には、データのセキュリティや品質管理、権限制御などを含め、継続的な改善が求められます。これにより、データマートが安定して稼働し、ビジネスに貢献し続けることができます。
7. 分析結果のビジネス活用推進
データマートから得られた分析結果をビジネスに活用することで、具体的な成果を生み出すことができます。分析結果をもとに、顧客体験の向上や業務プロセスの改善を図り、企業全体の競争力を高めることが可能です。ビジネス活用を推進するためには、関係者間での共有とフィードバックが重要です。
信頼できるデータマートパートナーの選び方
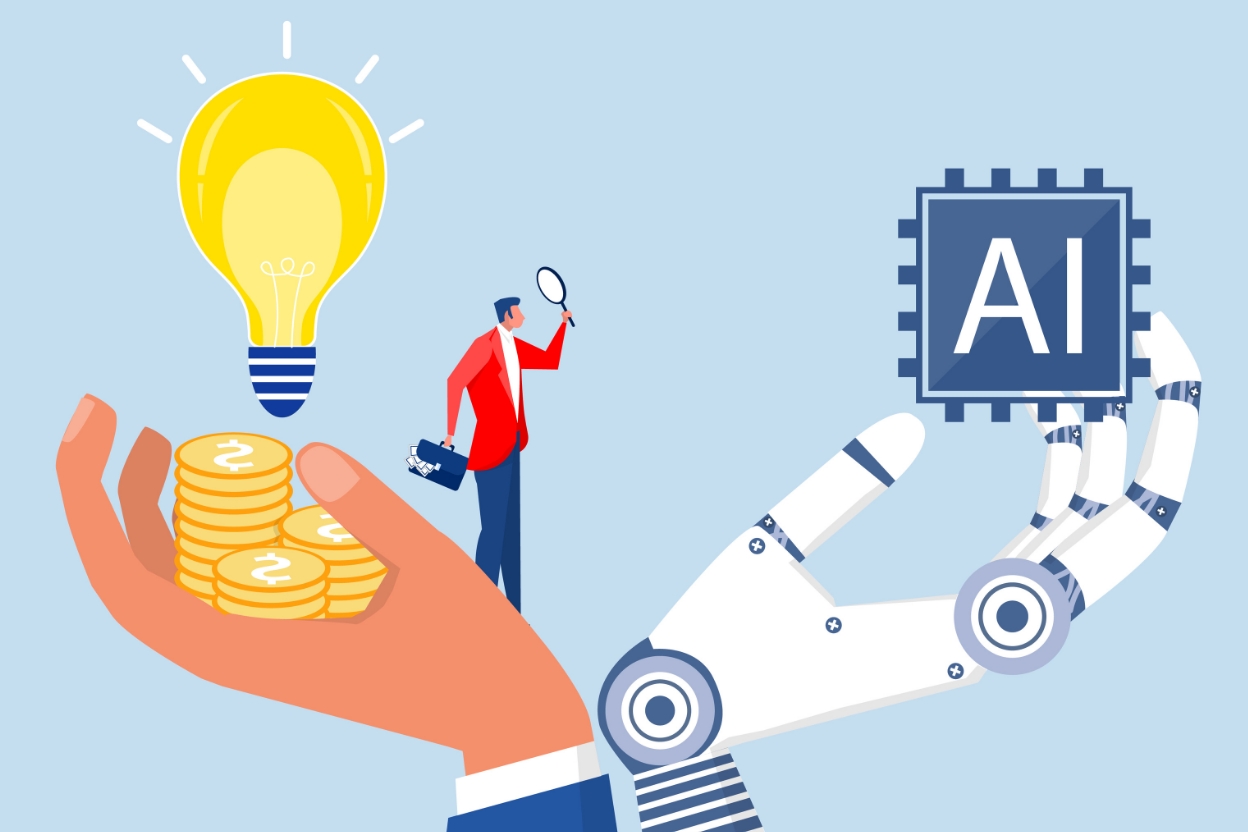
データ活用を推進するためには、信頼できるパートナーの選定が重要です。特にデータマートの導入においては、企業のニーズに合ったパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。この見出しは、データマートパートナーを選ぶ際のポイントを詳しく解説し、最適な選択をサポートします。
ワンストップサービスを提供する企業の特徴
ワンストップサービスを提供する企業は、企画から運用まで一貫したサポートを行います。これにより、複数のベンダーとの調整が不要となり、プロジェクトの進行がスムーズになります。特に、データマートの導入においては、データの収集、分析、活用までを一手に引き受ける企業が理想的です。こうした企業は、豊富な実績と専門知識を持ち、顧客のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。
専門性・最新技術対応力の見極め方
データマートの導入において、専門性と最新技術への対応力は欠かせません。AIやSnowflakeなどの最新技術を活用できる企業は、データ分析の精度を高め、ビジネス成果を最大化する手助けをします。専門性を見極めるためには、企業の過去のプロジェクト事例や技術者のスキルセットを確認することが重要です。また、技術の進化に対応するための研修制度や技術者の育成方針もチェックポイントとなります。
知っておきたいデータマート導入の注意点とリスク管理

データマートの導入は、企業のデータ活用を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。しかし、その一方で、適切な注意点とリスク管理を怠ると、プロジェクトの失敗につながることもあります。知っておくべきデータマート導入時の注意点とリスク管理のポイントを解説します。
プロジェクトの失敗例とその要因
データマート導入プロジェクトが失敗する要因として、計画段階での目的不明確さや、関係者間のコミュニケーション不足が挙げられます。例えば、データの整合性が取れず、分析結果が信頼できないものとなったケースがあります。また、技術的な課題として、既存システムとの統合がうまくいかず、データの抽出や変換などのデータ処理に時間がかかることも失敗の一因です。これらの失敗例から学び、事前にリスクを洗い出し、適切な対策を講じることが重要です。
リスクを最小限にするポイント
データマート導入におけるリスクを最小限に抑えるためには、まずプロジェクトの目的を明確にし、関係者全員が共有することが重要です。さらに、データの品質管理を徹底し、信頼性の高いデータを基に分析を行う体制を整えることが求められます。また、技術的な側面では、既存システムとのスムーズな統合を図るために、専門的な知識を持つパートナーと協力することが効果的です。これにより、プロジェクトの成功率を高めることができます。
データマートの導入で得られる成果と今後の展望
データマートの導入は、企業のデータ活用を大きく前進させる鍵となります。まず、データマートを活用することで、部門ごとのデータニーズに応じた分析が可能になり、迅速な意思決定が実現します。これにより、営業やマーケティング部門は、より的確な戦略を立てることができ、顧客体験の向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化に寄与します。
さらに、データマートはDX推進の基盤としても重要です。AIやBIツールとの連携により、データから新たな価値を創出し、競争力を高めることができます。今後の展望としては、クラウド技術の進化に伴い、データマートの導入がより手軽になり、コスト面でも柔軟な選択肢が増えることが期待されます。
※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。






