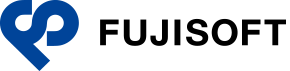交通費を自動計算にするには?
経費精算の効率化のためのステップを解説
交通費の手動計算は、企業の経理担当者にとって非常に時間のかかる業務の一つです。従業員から提出される交通費申請書を一件ずつ確認し、運賃や距離を計算して承認する作業は、ミスが発生しやすく業務効率の大きな妨げとなっています。近年、多くの企業がこうした課題を解決するため、交通費の自動計算システムの導入を検討しています。
交通費の自動計算とは、従来手作業で行っていた運賃計算や距離計算をシステムが自動で行う仕組みです。ICカード連携や経路検索機能、GPSを活用した移動距離の自動測定などにより、申請から承認までのプロセスを大幅に効率化できます。
本記事では、交通費自動計算の導入を検討している企業の担当者に向けて、自動計算の仕組みやメリット、導入手順、システム選定のポイントまで詳しく解説します。精算業務の効率化を実現し、負担軽減とコスト削減を目指しましょう。
Writer Profile
高津 咲
富士ソフト株式会社
ソリューションビジネスユニット
ソリューション事業本部 営業統括部
ソリューション営業部 第1営業グループ 主任
2017年 富士ソフト入社。アカウント営業として活動したのち、クラウド・AI-IoT・ワークフロー・AI-OCR等のソリューション営業を経て、現在はConcurをメインとしたお客様の経理業務の課題解決と活性化を支援するソリューションの営業を行っている。

交通費自動計算とは
交通費の自動計算システムは、従来手作業で行っていた運賃や距離の計算を、システムが自動で処理する仕組みです。これにより経理担当者の負担を大幅に軽減し、計算ミスの防止と業務効率の向上を実現できます。
交通費自動計算の仕組み
交通費の自動計算システムでは、従業員が出発地と目的地を入力すると、システムが複数の経路を検索し、最も安い運賃や会社規定に沿った経路を自動選択してくれます。
また、定期券区間の自動控除機能のあるシステムでは、通勤定期券でカバーされる区間は運賃から自動的に差し引かれます。これにより、従業員が手動で計算する必要がなくなり、計算ミスも防止できます。
ICカード連携による実績データの取得
ICカード連携機能を持つシステムでは、交通系ICカードの利用履歴を直接読み込んで交通費を自動計算できます。これにより、実際の乗車実績に基づいた正確な交通費申請が可能になります。
加えて、ICカードのデータを自動で取り込めるため、従業員は手動での入力作業が不要になり、申請業務の大幅な効率化を実現できます。実績ベースでの精算により、不正申請の防止効果も期待できるのです。
モバイルアプリによる申請の簡素化
多くの交通費の自動計算システムでは、モバイルアプリを提供しており、外出先からでも簡単に交通費申請ができます。
モバイルアプリでは領収書の撮影機能も搭載されている場合もあり、撮影した画像から自動でテキストを抽出して申請内容に反映させることができます。これにより、申請業務の時間短縮と正確性の向上を同時に実現できます。
交通費自動計算のメリット
交通費の自動計算システムの導入には、業務効率化からコスト削減まで多岐にわたるメリットがあります。
業務効率化と時間短縮
交通費の自動計算により、従来の手動計算にかかっていた時間を大幅に短縮できます。これにより、経理担当者の負担も軽減され、より付加価値の高い業務に時間を充てられるようになります。
また、承認ワークフローの自動化により、申請から承認までの期間も短縮されます。従業員にとっても、申請作業の負担が軽減され、本来の業務により集中できる環境が整います。
計算精度の向上とミス防止
手動計算では避けられない計算ミスも、自動計算システムにより大幅に削減できます。精度の高いデータを確保できることで、経理処理全体の信頼性も高まります。
社内の経費規定チェック機能も備えている自動計算システムは、申請内容が会社の経費規定に適合しているかを自動で確認してくれます。これにより、不適切な申請の事前防止と経費管理の適正化を実現できます。
コスト削減効果
交通費の自動計算システムの導入により、人件費の削減効果が期待でき、他の重要な業務により多くのリソースを配分できるようになります。
また、正確な交通費計算により過払いを防止し、適正な経費管理を実現できます。定期券区間の自動控除機能がある場合は、重複支払いの防止効果も得られます。
導入前の準備と現状分析
交通費の自動計算システムの導入を成功させるためには、事前の準備と現状分析が重要です。現在の交通費精算業務における課題を明確にし、システム導入による改善目標を設定する必要があります。
現状業務の課題洗い出し
まずは現在の交通費精算業務における課題を具体的に洗い出すことが重要です。申請件数や処理時間、よくあるミスの種類などを数値化して把握しましょう。
次に、経理担当者へのヒアリングを通じて、日常的に感じている負担や改善したいポイントを収集します。また、従業員側の申請業務における課題も合わせて調査することで、包括的な問題把握ができます。
社内規定の整備と標準化
交通費の自動計算システムを効果的に活用するためには、社内の交通費規定を明確に定義し、標準化する必要があります。距離単価や支給基準、承認権限などは、事前に分かりやすくルール化しておくと安心です。
また民間企業においても、旅費法改正の流れを踏まえた社内規程の見直しや透明性確保が求められるケースが増えています。特に出張旅費や交通費の取り扱いに関しては、国の基準を参考にすることで、社内規程がより合理的で監査対応にも強いものとなります。
規定の標準化を行うことで、システムでの自動チェック機能を最大限活用でき、より正確な経費管理を実現できます。また、従業員にとっても申請基準が明確になり、適切な申請が行いやすくなるため、社内規定は明確にするとよいでしょう。
必要機能の要件定義
現状分析の結果を踏まえて、導入するシステムに必要な機能を整理しましょう。例えば、ICカードとの連携が必要か、どの交通機関に対応するか、モバイルアプリが必要かどうかを検討します。
既存の経理システムとの連携要件も重要な検討事項です。データの自動連携により、さらなる業務効率化を実現できる可能性があります。要件を明確にすることで、システム選定時の比較検討がしやすくなります。要件をカテゴリごとに整理すると、次のようになります。
| 要件カテゴリ | 検討項目 | 優先度 |
|---|---|---|
| 基本機能 | 経路検索、運賃計算 | 必須 |
| 連携機能 | ICカード、既存システム | 高 |
| 運用機能 | 承認フロー、レポート | 中 |
システム選定のポイント
交通費の自動計算システムの選定では、機能面だけでなく運用面やコスト面も総合的に評価する必要があります。自社の業務要件に最も適したシステムを選択することで、導入効果を最大化できます。
機能比較と評価基準
システム選定では、自社の要件に対する機能の適合度を詳細に比較評価することが重要です。基本的な自動計算機能に加えて、ICカード連携や経路検索の精度、対応交通機関の範囲などを確認しましょう。
また、ユーザーインターフェースの使いやすさも重要な評価ポイントです。従業員が日常的に使用するシステムのため、直感的で操作しやすい設計であることが欠かせません。
コストパフォーマンスの評価
初期導入費用だけでなく、月額利用料や保守費用を含めた総所有コストで評価することが大切です。従業員数や申請件数に応じた料金体系を確認し、自社規模に適したプランを選択しましょう。
費用対効果の算出では、人件費削減効果やミス防止によるコスト削減効果も考慮に入れる必要があります。長期的な視点でのコストパフォーマンスを評価することで、適切な投資判断ができます。
セキュリティと法令対応
交通費データには個人情報や機密性の高い情報が含まれるため、システムのセキュリティ対策は非常に重要です。データの暗号化や接続セキュリティ、バックアップ体制などを確認しましょう。
また、電子帳簿保存法への対応状況も確認が必要です。法令要件を満たすシステムを選択することで、将来的な法改正にも安心して対応できます。定期的なセキュリティ監査も重要な評価ポイントです。
導入プロセスと運用開始
交通費の自動計算システムの導入は、計画的に進めることが重要です。システム設定から従業員への教育まで、各フェーズを丁寧に実行することで、スムーズな運用開始を実現できます。
導入プロセスでは、関係部署との連携や従業員からのフィードバック収集も重要です。適切なプロジェクト管理により、予定通りの導入とその後の安定運用を確保しましょう。
システム設定とカスタマイズ
システム導入の初期段階では、自社の交通費規定や承認フローをシステムに正確に設定することが重要です。距離単価や支給上限額、定期券管理などの基本設定を行い、実際の運用に即した環境を構築する必要があります。
また、既存の経理システムとのデータ連携設定も重要な作業項目です。自動データ連携により、さらなる業務効率化を実現できます。設定作業では、システムベンダーとの密な連携が必要です。
テスト運用とトラブルシューティング
本格運用前のテスト期間では、実際の申請パターンに基づいた動作確認を行います。様々なケースでの自動計算結果を検証し、システムの精度と安定性を確認しましょう。
テスト運用で発見された問題点は、本格運用前に確実に解決することが重要です。従業員からのフィードバックを収集し、使い勝手の改善や機能調整を行うことで、より良いシステム環境を整えられます。
教育とサポートのポイントとシステム導入のステップ
システムの機能を最大限活用するためには、従業員への適切な教育が不可欠です。操作方法だけでなく、新しい申請フローや注意事項についても丁寧に説明しましょう。
導入初期は、ヘルプデスク機能や問い合わせ窓口を充実させることで、従業員の不安を軽減できます。段階的な機能展開により、従業員が無理なくシステムに慣れることができる環境を整えることが大切です。
導入は以下のステップに分けて進めるとスムーズです。
| 導入フェーズ | 期間目安 | 主な作業内容 |
|---|---|---|
| システム設定 | 2-4週間 | 基本設定、カスタマイズ |
| テスト運用 | 2-3週間 | 動作確認、問題解決 |
| 本格運用 | 1週間 | 全社展開、サポート |
まとめ
交通費の自動計算システム導入は、経理業務の効率化と精度向上を実現する有効な手段です。ICカード連携や経路検索機能により、従来の手動計算から脱却し、大幅な業務改善を期待できます。
導入を成功させるためには、現状分析による課題の明確化とシステム要件の定義が重要です。また、適切なシステム選定と段階的な導入プロセスにより、スムーズな運用開始を実現できます。
交通費精算業務の負担軽減とコスト削減を目指す企業にとって、自動計算システムは投資効果の高いソリューションと言えるでしょう。特にConcurでは、ICCI(IC Card Integration Service)によって、交通系ICカードを利用したデータを自動で連携することができます。交通費の入力が実績データに基づいて自動的に行われるため、従業員の手動入力作業を削減するだけでなく、ミスの減少にもつながります。また、不正申請を防止し、申請プロセス全体の透明性が確保されます。計画的な導入により、経理部門の生産性向上と企業全体の業務品質向上を実現しましょう。
富士ソフトでは SAP Concur(コンカー)を用いて、多くのお客様の交通費精算業務における課題を解決した実績があります。
SAP Concur認定コンサルタントを含む100名以上のプロフェッショナルが、ライセンス契約から導入・アフターサポートまで、ワンストップパートナーとしてお客様のニーズに合わせた業務効率化のお手伝いをいたします。ぜひご相談ください。
富士ソフト Concur 導入サービス
SAP Concur(コンカー)は、出張・経費管理クラウドシステムです。
従業員の規模を問わず、日本をはじめ世界中で利用されています。
経費精算の全プロセスを自動化し、無駄な作業はすべてカット。経費精算業務を省力化することで、社内の生産性向上に役立ちます。
スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスにも対応し、場所を選ばず申請が可能で、200種類の分析レポートにより経費の使途を可視化することで経費の適正化やコスト削減につなげます。