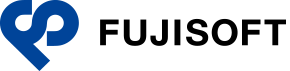経費精算ルールはどう設定すべき?
策定のメリットと注意点も併せて解説
経費精算ルールの策定は、企業の健全な財務管理と業務効率化において欠かせない取り組みです。適切なルールを設定することで、不正な経費申請を防ぎ、経理担当者の負担軽減にもつながります。
しかし、多くの企業では経費精算のルールが曖昧なまま運用されており、無駄な支出や社員間の不公平感が生じているケースも少なくありません。
本記事では、経費精算ルールの設定方法から策定のメリット、注意点まで詳しく解説し、最新の旅費法改正を踏まえた適切なルール作りのポイントをご紹介します。
Writer Profile
高津 咲
富士ソフト株式会社
ソリューションビジネスユニット
ソリューション事業本部 営業統括部
ソリューション営業部 第1営業グループ 主任
2017年 富士ソフト入社。アカウント営業として活動したのち、クラウド・AI-IoT・ワークフロー・AI-OCR等のソリューション営業を経て、現在はConcurをメインとしたお客様の経理業務の課題解決と活性化を支援するソリューションの営業を行っている。

経費精算ルールの基本設定
経費精算ルールを設定する際は、まず社内で統一された基準を明確に定義することが重要です。曖昧な表現や解釈の余地がある規定は、後々のトラブルの原因となるため、具体的で分かりやすい内容にする必要があります。
経費精算規定の対象範囲
経費精算ルールを策定する第一歩として、どのような費用が経費として認められるかを明確に定義します。一般的には交通費、宿泊費、会議費、通信費、消耗品費などが対象となりますが、業種や事業内容に応じて対象範囲を調整することが重要です。
例えば、営業職には出張や顧客対応のために必要な交通費や交際費が多く発生するため、その範囲を広げることが検討されます。一方、事務職やバックオフィスの従業員には、必要最低限の経費範囲を設けることで、経費管理の透明性と公平性を保つことが重要です。また、役職別に支出基準を設ける場合は、社員に対する説明責任を果たし、納得感を持たせるよう配慮が必要です。
また、個人的な支出との境界線を明確にするため、認められない経費についても具体的に列挙しておきます。例えば、家族同伴の宿泊費や個人的な買い物、プライベートな飲食費などは経費として認めない旨を明記します。
経費精算の上限と基準
各費用項目について、適切な上限金額や基準を設定することで、無制限な支出を防ぎます。交通費については実費精算とするか定額支給とするか、宿泊費については地域別の上限設定、交際費については相手先や目的による分類など、詳細な基準を策定します。
これらの基準を設定する際は、社員の職位や業務内容に応じて段階的な設定を行うことで、公平性を保ちながら適切なコスト管理が可能になります。例えば、管理職と一般職で交際費の上限を変えるなどの工夫が考えられます。
申請期限と承認フロー
経費精算の申請期限を明確に設定することで、経理処理の効率化を図ることができます。一般的には、経費発生から1ヶ月以内の申請を義務付けるケースが多く見られます。また、承認フローについても、金額や費用項目に応じた段階的な承認体制を構築する必要があります。
旅費法改正を踏まえた設定ポイント
近年の旅費法改正により、企業の経費精算ルールにも影響が生じています。特に出張旅費の取り扱いについては、最新の法令に準拠したルール設定が求められます。
旅費法改正の主な変更点
旅費法の改正では、旅費の支給基準や計算方法について見直しが行われています。旅費法改正に伴って、従来の定額支給から実費精算への移行を検討する企業が増えており、より透明性の高い旅費管理が求められています。
また、宿泊費については地域区分の細分化が進み、より実情に即した支給基準の設定が可能になりました。
| 内容 | 変更点 | 影響 |
|---|---|---|
| 支給方式の変更 | 従来の定額支給から上限付きの実費精算に変更 | 実際にかかった費用が支給されるため、自己負担が抑えられる一方、領収書やレシートの提出が必須となり、厳格な管理が求められる。 |
| 規定の簡素化 | 旅費の種類や内容に関する規定の簡素化、旅行命令簿や旅費請求書等の様式廃止など、旅費計算の規定が簡素化 | 旅行代理店の活用が可能になり、手配や精算の手続きが改善される。また、デジタル化を促進する要因にもなる。 |
| 不正防止と監査体制の強化 | 不正に受給した旅費は返納させる、または給与から控除するなどの規定が盛り込まれ、監査体制の強化が求められる。 | 故意の領収書改ざんなどの不正防止を意識した運用の必要性が高まる。 |
新しい旅費基準への対応
改正された旅費法に対応して、既存の経費精算ルールを見直す場合、特に、宿泊費や日当の支給基準について新たな設定を検討するとよいでしょう。
さらに、交通手段の選択基準についても見直しを行い、公共交通機関の利用を優先する規定を設けることが推奨されます。
税務上の取り扱いへの配慮
旅費法改正に伴い、税務上の取り扱いも変更される可能性があります。経費精算ルールを策定する際は、税理士などの専門家と連携し、適切な税務処理が行えるよう配慮した内容にすることが重要です。
特に、非課税となる旅費の範囲や計算方法については、最新の税法に準拠した規定を設ける必要があります。これにより、企業と社員双方にとって税務上のリスクを軽減できます。
経費精算ルール策定のメリット
適切な経費精算ルールを策定することで、企業は多くのメリットを享受できます。コスト削減から業務効率化まで、様々な効果が期待できます。
不正防止と内部統制の強化
明確な経費精算ルールの存在は、不正な経費申請を防ぐ重要な役割を果たします。申請基準や承認フローが明確化されることで、社員の意識向上と内部統制の強化を実現することが可能です。
また、定期的な監査や抜き打ちチェックの実施基準も規定に盛り込むことで、継続的な不正防止効果が期待できます。これにより、企業の信頼性向上と健全な経営基盤の構築につながります。
業務効率化とコスト削減
統一された経費精算ルールにより、申請者と承認者双方の業務効率が向上します。具体的には、申請書類の標準化や承認フローの明確化により、処理時間の短縮と業務負担の軽減が実現します。
さらに、適切な上限設定や基準の明確化により、無駄な支出を削減し、企業全体のコスト管理を効果的に行うことができます。経費精算システムの導入と併せて運用することで、より大きな効果が得られます。
社員の満足度向上
公平で透明性の高い経費精算ルールは、社員の不公平感を解消し、職場環境の改善に寄与します。申請手続きの簡素化や迅速な承認により、社員のストレス軽減も期待できます。
経費精算ルールを適切に設定することで、社内のコミュニケーションが円滑になります。例えば、社内で明確なルールを設けることで、各部門の理解が深まり、従業員同士のトラブルを未然に防ぐことができます。また、社員が疑問に感じた際にルールを明確に説明できるため、経費精算に対する不安が減少します。ルールの透明化によって、企業全体のモラルが向上し、経営陣と社員の信頼関係が深まることにも繋がります。
ご紹介したメリットの一覧を表にまとめると以下の通りです。
| メリット | 具体的効果 | 期待される成果 |
|---|---|---|
| 不正防止 | 内部統制強化 | 企業信頼性向上 |
| 業務効率 | 処理時間短縮 | 人件費削減 |
| コスト管理 | 無駄な支出削減 | 利益率改善 |
| 社員満足 | 公平性確保 | 離職率低下 |
策定時の注意点と運用のポイント
経費精算ルールを策定し、効果的に運用するためには、いくつかの重要な注意点があります。これらのポイントを押さえることで、ルールの実効性を高めることができます。
明確で分かりやすい表現
経費精算ルールは、すべての社員が理解できる明確で分かりやすい表現で記載する必要があります。専門用語や曖昧な表現は避け、具体例を交えた説明を心がけることで、誤解やトラブルを防ぐことができます。
また、図表やフローチャートを活用して視覚的に理解しやすい経費精算マニュアルを作成することも重要です。特に、複雑な承認フローや例外規定については、分かりやすい図解を用いて説明するとよいでしょう。
また、経費精算プロセスの簡素化も重要です。社員が申請を行う際に手間を感じることなく、スムーズに申請できるようなシステムを導入することで、社員の負担を軽減できます。例えば、領収書を簡単にスキャンできるアプリの導入や、モバイル端末を使った申請ができるようにすることで、外出先からでも申請が可能になります。また、迅速な承認と明確な基準により、社員が不安を感じることなく、経費精算を行える環境を提供することが重要です。
定期的な見直しと更新
経費精算ルールは、法令改正や社会情勢の変化に応じて定期的な見直しが必要です。年1回程度の定期見直しに加えて、重要な法改正があった際には随時更新を行うようにしましょう。
見直しの際は、実際の運用状況や社員からのフィードバックを踏まえて、より実用的で効果的なルールに改善していくことが重要です。また、見直し結果は全社員に適切に周知し、新しいルールの理解促進を図るようにしましょう。
システム化と連携
経費精算システムの導入により、ルールの自動適用や承認フローの効率化が可能になります。システム選定の際は、自社の経費精算ルールに適合する機能を持つものを選択し、必要に応じてカスタマイズを検討しましょう。
また、会計システムや人事システムとの連携により、データの一元管理と処理の自動化を実現できます。これにより、経理担当者の負担軽減と処理精度の向上が期待できます。
システムの導入により、社員が手間なく精算できるだけでなく、企業側はデータ分析を通じて、無駄な経費がどこで発生しているのかを特定できます。このようなデータを活用することで、年間の経費削減目標を設定し、継続的なコスト削減を実現することができます。これらにより、企業全体の業務効率が大幅に向上します。
教育と周知徹底
どんなに優れた経費精算ルールを策定しても、社員に適切に理解され、遵守されなければ意味がありません。新入社員研修や定期的な全社説明会を通じて、ルールの内容と重要性を継続的に伝えることが必要です。
さらに、Q&A集の作成や相談窓口の設置により、社員が疑問を解決しやすい環境を整えることで、ルールの適切な運用を促進できます。
まとめ
経費精算ルールの適切な設定は、企業の健全な財務管理と業務効率化において不可欠な要素です。明確な基準の設定から旅費法改正への対応まで、総合的な視点でルールを策定することが重要になります。
策定時には不正防止、業務効率化、コスト削減といったメリットを最大限に活用できるよう、実用性と透明性を重視した内容にする必要があります。また、定期的な見直しと社員への周知徹底により、ルールの実効性を継続的に高めていくことが成功の鍵となります。
適切な経費精算ルールの運用により、企業は健全な成長基盤を構築し、社員にとっても働きやすい環境を実現できるでしょう。
富士ソフトでは SAP Concur(コンカー)を用いて、多くのお客様における適切な経費精算ルールの策定をご支援し、課題を解決した実績があります。
SAP Concur認定コンサルタントを含む100名以上のプロフェッショナルが、ライセンス契約から導入・アフターサポートまで、ワンストップパートナーとしてお客様のニーズに合わせた業務効率化のお手伝いをいたします。ぜひご相談ください。
富士ソフト Concur 導入サービス
SAP Concur(コンカー)は、出張・経費管理クラウドシステムです。
従業員の規模を問わず、日本をはじめ世界中で利用されています。
経費精算の全プロセスを自動化し、無駄な作業はすべてカット。経費精算業務を省力化することで、社内の生産性向上に役立ちます。
スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスにも対応し、場所を選ばず申請が可能で、200種類の分析レポートにより経費の使途を可視化することで経費の適正化やコスト削減につなげます。