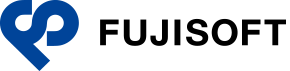法人カード経費精算を効率化するには?
システム選びのポイント
法人カードと経費精算システムの連携は、企業の経理業務効率化において重要な要素となっています。従来の手作業による経費精算では、領収書の整理や明細の手入力、承認フローの管理など多くの時間とコストが必要でした。しかし、適切なシステムを選択することで、これらの課題を大幅に改善することができます。
本記事では、法人カードと経費精算システム連携のメリットから、システム選択時の具体的なポイント、主要サービスの比較まで、効率化を実現するための実践的な情報をお伝えします。
Writer Profile
高津 咲
富士ソフト株式会社
ソリューションビジネスユニット
ソリューション事業本部 営業統括部
ソリューション営業部 第1営業グループ 主任
2017年 富士ソフト入社。アカウント営業として活動したのち、クラウド・AI-IoT・ワークフロー・AI-OCR等のソリューション営業を経て、現在はConcurをメインとしたお客様の経理業務の課題解決と活性化を支援するソリューションの営業を行っている。

法人カードと経費精算システム連携のメリット
法人カードと経費精算システムを連携することで、企業の経理業務は劇的に効率化されます。この連携により実現される具体的なメリットを詳しく解説します。
手入力作業の削減と時間短縮
法人カード連携の最大の利点は、クレジットカード明細自動取得機能による手入力作業の削減です。従来は経費申請者が領収書を見ながら金額や支払先を一つずつ入力していた作業が、システム導入によってカード利用と同時に自動でシステムに反映されます。これにより、月末の経費精算作業にかかる時間を大幅に短縮できます。
また、経理担当者の確認作業も効率化されます。カードの利用明細とシステム上の申請内容が自動で照合されるため、金額の相違や入力ミスの確認作業が軽減されます。
証憑管理の電子化とペーパーレス化
AI-OCR機能を搭載したシステムでは、撮影した領収書から金額や支払先の情報を自動で読み取り、データ化できます。
電子帳簿保存法やインボイス制度対応機能が備わったシステムなら、法的要件を満たしながらペーパーレス化を実現できます。これにより、書類の保管コストや管理工数も削減されます。
交通系ICカード連携による交通費の自動精算
Suica・PASMO・nimocaなどの交通系ICカードと連携することで、改札通過情報や利用履歴が自動で取り込まれ、交通費申請を半自動化できます。申請者は経路と金額の入力を省略でき、経理側は不備確認や差し戻し対応の工数を削減できます。
| 自動取得できる主な項目 | 業務上の効果 |
|---|---|
| 乗車日、区間(出発/到着)、運賃 | 手入力の削減、虚偽申請の抑止、経路の妥当性確認が容易 |
| 定期券区間の判定 | 定期区間内の申請を自動控除し、過請求を防止 |
| モバイルIC(モバイルSuica等)の利用履歴 | 紙の領収書不要、ペーパーレス化を加速 |
出張・営業活動が多い組織ほど、交通費申請の件数×1件あたりの処理時間が大きく削減され、月末に集中していた精算業務の負担を分散できます。
経費精算システムの選択ポイント
法人カードと連携する経費精算システムを選択する際は、自社の業務フローや規模に適したシステムを選ぶことが重要です。選択時に検討すべき主要なポイントを解説します。
対応カードの種類と連携機能
システムによって対応している法人カードの種類は異なります。主要な法人カード会社との連携状況を事前に確認することが必要です。クレジットカード明細自動取得機能の精度や更新頻度も、日常業務に大きく影響するため重要な選択基準となります。
また、交通系ICカード連携機能があるシステムでは、交通費の自動精算も可能です。従業員追加カード発行時の管理機能や、外貨精算対応の有無も確認しておくべき項目です。
ワークフロー機能と承認プロセス
企業の組織構造や承認ルールに合わせて、ワークフロー自動化機能をカスタマイズできるかが重要な選択基準です。承認フロー設定では、金額や申請者の役職に応じた柔軟な設定が可能かを確認しましょう。
モバイルアプリ対応のシステムを選ぶと、承認者が外出先からでも承認作業を行えるため、承認プロセスの迅速化が図れます。通知機能の設定により、承認漏れや申請の遅延も防止できます。
AI-OCR機能とデータ化精度
領収書の自動読み取り精度は、システムの使いやすさに直結します。AI-OCR機能の精度や対応言語、手書き文字の認識能力などを事前に確認することが重要です。
レシートや領収書の形式によって読み取り精度が変わるため、実際の運用を想定したテストを実施することが推奨されます。読み取りエラー時の修正機能の使いやすさも重要な評価項目です。
経費精算システムの特徴と選び方
市場には多くの経費精算システムが存在し、それぞれ異なる特徴を持っています。システム選択の参考となる主要な比較ポイントと機能の違いを解説します。
クラウド型システムの特徴
現在主流となっているクラウド型システムは、運用の簡便性が特徴です。セキュリティ対策強化についても、専門のセキュリティ会社による監視や定期的なアップデートにより、自社でサーバーを運用するよりも高いセキュリティレベルを実現できます。
スケーラビリティも高く、企業の成長に合わせてユーザー数や機能を柔軟に追加できます。災害時のデータ保護やバックアップ体制も充実しているサービスが多いです。
機能別比較のポイント
複数の経費精算システムを比較する際には、単に基本機能の有無だけでなく、自社の業務ニーズにどれだけ対応しているかを見極めることが重要です。たとえば、出張精算が頻繁に発生する企業では、日当や宿泊費の自動計算、外貨換算への対応など、出張管理に特化した機能が求められます。
また、小口現金の運用がある企業では、現金支出の記録と法人カード利用の統合管理ができるかどうかも、効率化に大きく影響します。さらに、既存の会計システムとの連携機能の有無も、経理業務全体の自動化を進めるうえでの重要な評価軸となります。
以下の表は、主要な機能分野ごとに「基本機能」と「上位機能(発展的機能)」を整理したものです。自社の業務内容や成長フェーズに応じて、必要な機能レベルを明確にしておくと、導入後のギャップを防げます。
| 機能分野 | 基本機能 | 上位機能 |
|---|---|---|
| 精算機能 | 経費入力・申請 | AI自動仕訳・予算管理 |
| 承認機能 | 基本ワークフロー | 条件分岐・代理承認 |
| 連携機能 | カード明細取得 | 会計システム連携 |
| 分析機能 | 基本レポート | BI連携・予実管理 |
コストと投資対効果
システムの導入コストは、初期費用と月額利用料に分けて評価する必要があります。ユーザー数課金制のサービスでは、将来の組織拡大を考慮した料金体系の確認が重要です。
導入により削減される人件費や業務時間を金額換算し、システムの利用料と比較することで、投資対効果を定量的に評価できます。ポイント還元特典がある法人カードとの組み合わせにより、実質的なコスト削減効果も期待できます。
導入成功のための実践的アプローチ
経費精算システムの導入を成功させるためには、技術面だけでなく、組織的な取り組みも重要です。導入から運用定着までの実践的なアプローチを解説します。
導入準備と要件定義
システム導入前の要件定義では、現在の経費精算業務の課題を具体的に洗い出すことが重要です。月次の精算件数や承認にかかる時間、よく発生するエラーの種類などを定量的に把握します。
インボイス制度対応や電子帳簿保存法への対応状況も、法的要件として必須の確認項目となります。既存の会計システムやその他の業務システムとの連携要件も明確にしておく必要があります。
段階的導入とユーザー教育
大規模な組織での導入では、部署別や段階別の導入が効果的です。まず経理部門や管理部門での試験運用を実施し、課題を解決してから全社展開を行いましょう。
ユーザー教育では、システムの操作方法だけでなく、新しい業務フローや承認ルールについても十分な説明が必要です。モバイルアプリ対応システムの場合は、スマートフォンでの操作方法についても研修を実施するようにしましょう。
運用開始後の継続改善
システム運用開始後も、定期的な利用状況の分析と改善が重要です。利用者からのフィードバックを収集し、設定の最適化や新機能の活用を検討しましょう。
承認フローの見直しや、AI-OCR機能の精度向上のための学習データの蓄積なども、継続的な改善活動として実施することが推奨されます。システムベンダーからの新機能リリースやアップデート情報も積極的に活用するとよいでしょう。
| 導入フェーズ | 主な活動 | 期間目安 |
|---|---|---|
| 準備期間 | 要件定義・システム選定 | 2-3ヶ月 |
| 導入期間 | 設定・テスト・研修 | 1-2ヶ月 |
| 定着期間 | 運用開始・改善活動 | 3-6ヶ月 |
まとめ
法人カードと経費精算システムの連携は、企業の経理業務効率化において非常に有効な手段です。手入力作業の削減、リアルタイムでの経費管理、証憑管理の電子化など、多くのメリットを実現できます。
システム選択では、対応カードの種類、ワークフロー機能、AI-OCR機能、コスト面を総合的に評価することが重要です。自社の業務フローや組織規模に適したシステムを選択し、段階的な導入と継続的な改善により、経費精算業務の大幅な効率化を実現できるでしょう。
富士ソフトでは SAP Concur(コンカー)を用いて、法人カードでの経費精算の効率化をご支援した実績が多数あります。
また、SAP Concur認定コンサルタントを含む100名以上のプロフェッショナルが、ライセンス契約から導入・アフターサポートまで、ワンストップパートナーとしてお客様のニーズに合わせた業務効率化のお手伝いをいたします。ぜひご相談ください。
富士ソフト Concur 導入サービス
SAP Concur(コンカー)は、出張・経費管理クラウドシステムです。
従業員の規模を問わず、日本をはじめ世界中で利用されています。
経費精算の全プロセスを自動化し、無駄な作業はすべてカット。経費精算業務を省力化することで、社内の生産性向上に役立ちます。
スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスにも対応し、場所を選ばず申請が可能で、200種類の分析レポートにより経費の使途を可視化することで経費の適正化やコスト削減につなげます。