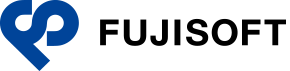電子帳簿保存法、領収書の正しい管理方法とは?
対応方法と注意点を紹介
2024年1月から電子帳簿保存法の改正により、電子取引データの電子保存が義務化されました。これまで紙で印刷して保管していた方法が認められなくなり、多くの企業が対応に追われています。
本記事では、電子帳簿保存法における領収書の正しい管理方法について、最新の法改正内容をふまえて詳しく解説します。紙の領収書と電子領収書それぞれの保存要件、必要なシステム要件、実務上の注意点まで、企業の経理担当者や個人事業主の方が迷わず適切な運用ができるよう、具体的な対応方法をご紹介します。
Writer Profile
高津 咲
富士ソフト株式会社
ソリューションビジネスユニット
ソリューション事業本部 営業統括部
ソリューション営業部 第1営業グループ 主任
2017年 富士ソフト入社。アカウント営業として活動したのち、クラウド・AI-IoT・ワークフロー・AI-OCR等のソリューション営業を経て、現在はConcurをメインとしたお客様の経理業務の課題解決と活性化を支援するソリューションの営業を行っている。

電子帳簿保存法における領収書管理の基本
電子帳簿保存法は、国税関係書類の電子保存を認める法律です。2024年1月の改正により、電子取引データの保存義務が強化され、領収書の管理方法も大きく変わりました。
この法律では、領収書を含む国税関係書類を「帳簿」「国税関係書類」「電子取引データ」の3つに分類しています。領収書は主に「国税関係書類」と「電子取引データ」に該当し、それぞれ異なる保存ルールが適用されます。
電子帳簿保存法の3つの保存区分
電子帳簿保存法では、書類の性質や受け取り方法により、以下の3つの保存区分に分類されます。
| 保存区分 | 対象書類 | 保存方法 |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフトで作成した帳簿・書類 | 電子データのまま保存 |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った国税関係書類 | スキャンして電子化保存 |
| 電子取引データ保存 | 電子的に授受した取引情報 | 電子データのまま保存(義務) |
領収書の受け取り方法による分類
領収書の管理方法は、どのような方法で受け取ったかによって決まります。紙で受け取った領収書は「スキャナ保存」の対象となり、電子メールやWebサイトから受け取った領収書は「電子取引データ保存」の対象となります。
電子取引データ保存については、2024年1月から保存義務が完全に施行されており、違反した場合は青色申告の承認取消しなどの罰則が科される可能性があります。一方、スキャナ保存は任意の制度ですが、活用することで業務効率化が図れます。
保存期間と保存要件の概要
領収書を含む国税関係書類の保存期間は、法人の場合は原則7年間、個人事業主の場合は5年間となっています。ただし、欠損金の繰越控除を受ける法人については10年間の保存が必要です。
電子保存する場合は、改ざん防止措置、検索機能の確保、システム関係書類の備付けなど、法的効力を保つための要件を満たす必要があります。これらの要件を理解し、適切なシステムや運用体制を整備することが重要です。
電子取引データとしての領収書保存方法
電子取引データとは、電子メールやWebサイト、EDIシステムなどを通じて電子的に授受した取引情報を指します。PDFファイルやスクリーンショットなど、電子データで受け取った領収書は、必ず電子データのまま保存しなければなりません。
電子取引データの保存要件
電子取引データとして領収書を保存する場合、以下の要件を満たす必要があります。まず、データの真実性を確保するため、タイムスタンプの付与や履歴が残るシステムでの授受が求められます。
| 要件項目 | 具体的な内容 | 対応方法例 |
|---|---|---|
| 真実性の確保 | 改ざん防止措置の実施 | タイムスタンプ付与、訂正削除履歴の保持 |
| 可視性の確保 | 検索機能の整備 | 日付・金額・取引先での検索機能 |
| システム要件 | 関係書類の備付け | システム概要書、操作説明書の整備 |
電子取引データの保存では、受領後速やかにタイムスタンプを付与するか、訂正削除の履歴が残るシステムでの管理が必要です。また、税務調査時に即座にデータを提示できるよう、適切な検索機能を備えたシステムの導入が求められます。
クラウドサービス活用時の注意点
多くの企業がクラウドサービスを活用して電子取引データの保存を行っています。クラウドサービスを利用する場合は、サービス提供者が電子帳簿保存法の要件に対応しているかを確認することが重要です。
特に、データの改ざん防止機能や検索機能、バックアップ体制について詳しく確認する必要があります。また、サービス終了時のデータ移行についても、事前に対応方法を確認しておくことが推奨されます。
PDF保存時の具体的な手順
電子メールで受け取ったPDF形式の領収書を保存する場合の手順をご説明します。まず、受信したメールから添付ファイルを保存し、ファイル名に日付や取引先名などの検索用情報を含めることが効果的です。
次に、保存したPDFファイルに対してタイムスタンプを付与するか、専用システムに登録します。この際、元のメールも併せて保存し、取引の経緯が分かるようにしておくことが重要です。最後に、検索用のインデックス情報を整備し、必要時に迅速にアクセスできる体制を整えます。
紙の領収書のスキャナ保存対応
紙で受け取った領収書については、原本保管を継続するか、スキャナ保存制度を活用して電子化するかを選択できます。スキャナ保存を選択する場合は、法定要件を満たしたスキャン処理と適切なデータ管理が必要になります。
スキャナ保存制度は任意の制度ですが、活用することで保管スペースの削減や検索性の向上など、大きな業務効率化メリットを得ることができます。ただし、適用には事前の税務署への届出が必要な場合があります。
スキャナ保存の基本要件
スキャナ保存を行う場合、書類の種類によって異なる要件が定められています。領収書などの重要書類については、特に厳格な要件が適用されます。
スキャナ保存では、原本受領後速やかにスキャンを行い、適切な解像度とカラー画像での保存が必要です。また、スキャン後のデータには必ずタイムスタンプを付与し、原本との整合性を確認する体制を整える必要があります。
| 要件項目 | 一般書類 | 重要書類(領収書等) |
|---|---|---|
| 解像度 | 200dpi以上 | 200dpi以上 |
| 色彩 | グレースケール可 | カラー画像 |
| タイムスタンプ | 必要 | 必要(速やかに付与) |
| 適正事務処理要件 | 不要 | 必要(相互けん制など) |
スキャン作業の実務手順
効率的なスキャン作業を実現するためには、標準化された手順の確立が重要です。まず、受け取った領収書を日付順に整理し、スキャン前に汚れや折れ目がないか確認しましょう。
スキャン実行時は、設定された解像度とカラー設定を確認し、画像の鮮明さをチェックします。スキャン完了後は、元の書類と画像データを照合し、内容に相違がないことを確認してからタイムスタンプを付与します。最後に、検索用の属性情報を登録し、適切なフォルダ構成で保存します。
原本保管からの移行検討
現在紙の領収書を原本保管している企業が、スキャナ保存に移行する場合は、段階的なアプローチが効果的です。まず、月次の領収書の一部からスキャナ保存を開始し、運用に慣れてから対象範囲を拡大していく方法があります。
移行期間中は、原本保管とスキャナ保存を併用することも可能です。ただし、同一の書類について二重の保存方法を適用することは避け、明確な区分ルールを設定することが重要です。また、税務調査への対応方法についても事前に整理しておく必要があります。
電子帳簿保存法対応システムの選定と運用
電子帳簿保存法に適切に対応するためには、法定要件を満たすシステムの導入が不可欠です。市場には多様な対応システムが提供されており、企業の規模や業務内容に応じた選定が重要になります。
システム選定の重要ポイント
電子帳簿保存法対応システムを選定する際は、まず法定要件への対応状況を詳細に確認しましょう。特に、タイムスタンプ機能、検索機能、データの真実性確保機能について、具体的な仕組みを理解することが重要です。
システム選定では、導入コストだけでなく、月額利用料、保守費用、追加機能の費用も含めた総合的なコスト評価が必要です。また、ユーザーの使いやすさや管理者の負担軽減についても重要な選定基準となります。
| 評価項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 法定要件対応 | タイムスタンプ、検索機能、改ざん防止 |
| 既存システム連携 | 会計ソフト、ERPとのデータ連携 |
| 操作性 | 直感的な操作、モバイル対応 |
| コスト | 初期費用、月額費用、追加費用 |
| サポート | 導入支援、運用サポート体制 |
クラウド型とオンプレミス型の比較
電子帳簿保存法対応システムには、オンプレミス型とクラウド型の選択肢があります。オンプレミス型は自社の厳格なセキュリティ要件に対応しやすく、既存システムとの密な連携が可能です。
一方、クラウド型はシステムの保守やバージョンアップが自動的に行われることから、運用や管理が簡便という特徴があります。加えて、常に最新のサービスが利用できることから、今後さらに進んでいく経費精算の自動化にも対応がしやすいというメリットがあります。近年、クラウドの利活用が進んでいることから、クラウド型を選択する企業が増えています。
上記のような特長や、企業の規模やセキュリティポリシー、IT管理体制に応じて適切なシステムを選択することが重要です。
導入プロジェクトの進め方
システム導入を成功させるためには、計画的なプロジェクト管理が必要です。まず、現在の業務フローを詳細に分析し、システム導入により改善される点と新たに発生する作業を明確にしましょう。
次に、段階的な導入スケジュールを策定し、ユーザー教育やテスト運用の期間を十分に確保するようにしましょう。本格運用開始前には、税務調査を想定したデータ提出テストを実施し、システムの動作確認を行うことが推奨されます。最後に、運用開始後の継続的な改善体制を整備し、法改正への対応も含めたシステム管理体制を構築することが必要です。
実務上の注意点と違反リスク対策
電子帳簿保存法への対応では、法定要件を満たすだけでなく、実務運用における様々な注意点を理解することが重要です。特に、違反時の罰則や税務調査への対応については、十分な準備と対策が求められます。
税務調査への準備と対応
税務調査では、電子保存された領収書データの提示を求められる場合があります。調査官が円滑にデータを確認できるよう、検索機能や表示機能が適切に動作することを事前に確認しておく必要があります。
また、システム関係書類の整備も重要な準備項目です。システムの概要書、操作マニュアル、データ保存に関する社内規程などを整備し、調査時に速やかに提示できるよう準備しておくことが推奨されます。さらに、データのダウンロード機能や印刷機能についても、調査官の要求に応じて対応できる体制を整えることが必要です。
経理業務の効率化と内部統制
電子帳簿保存法への対応を機に、経理業務全体の効率化を図る企業も多く見られます。領収書の電子化により、検索性の向上や保管スペースの削減といった直接的なメリットに加え、承認フローの電子化や自動仕訳機能の活用により、大幅な業務効率化が期待できます。
一方で、電子化により新たな内部統制リスクも発生します。データの不正な修正や削除を防ぐため、適切なアクセス権限の設定と監査ログの管理体制を構築することが重要です。また、システム障害時の業務継続方法についても、事前に検討し準備しておく必要があります。
まとめ
電子帳簿保存法における領収書の管理は、受け取り方法によって適用される保存区分が異なります。電子データで受け取った場合は電子取引データ保存の対象となり、2024年1月から完全義務化されているため、適切な電子保存システムの導入が必要です。
紙で受け取った領収書については、原本保管を継続するか、スキャナ保存制度を活用するかを選択できます。どちらの方法を選択する場合も、法定要件を満たした適切な管理体制の構築が重要となります。
システム選定や運用体制の整備においては、単に法令遵守だけでなく、業務効率化や内部統制の強化も含めた総合的な検討が求められます。継続的な法改正への対応も含め、長期的な視点での取り組みが成功の鍵となるでしょう。
富士ソフトでは SAP Concur(コンカー)を用いて、領収書の管理をはじめとした電子帳簿保存法への対応についてご支援した実績が多数あります。
また、SAP Concur認定コンサルタントを含む100名以上のプロフェッショナルが、ライセンス契約から導入・アフターサポートまで、ワンストップパートナーとしてお客様のニーズに合わせた業務効率化のお手伝いをいたします。ぜひご相談ください。
富士ソフト Concur 導入サービス
SAP Concur(コンカー)は、出張・経費管理クラウドシステムです。
従業員の規模を問わず、日本をはじめ世界中で利用されています。
経費精算の全プロセスを自動化し、無駄な作業はすべてカット。経費精算業務を省力化することで、社内の生産性向上に役立ちます。
スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスにも対応し、場所を選ばず申請が可能で、200種類の分析レポートにより経費の使途を可視化することで経費の適正化やコスト削減につなげます。