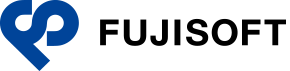電子帳簿保存法、違反するとどうなる?
違反リスクと対策ポイントを解説
電子帳簿保存法の義務化に伴い、多くの企業や個人事業主が「違反した場合の罰則はどうなるのか」という不安を抱えています。2024年1月以降、電子取引データの電子保存が完全義務化されたことで、適切な対応を怠ると深刻な影響を受ける可能性があります。
本記事では、電子帳簿保存法の違反リスクと具体的な罰則内容、そして効果的な対策ポイントを詳しく解説します。包括的なリスク像を把握し、安心して業務を進められるよう実践的な情報をお届けします。
Writer Profile
高津 咲
富士ソフト株式会社
ソリューションビジネスユニット
ソリューション事業本部 営業統括部
ソリューション営業部 第1営業グループ 主任
2017年 富士ソフト入社。アカウント営業として活動したのち、クラウド・AI-IoT・ワークフロー・AI-OCR等のソリューション営業を経て、現在はConcurをメインとしたお客様の経理業務の課題解決と活性化を支援するソリューションの営業を行っている。

電子帳簿保存法の違反で発生する主な罰則
電子帳簿保存法に違反した場合、複数の法的なペナルティが科せられる可能性があります。まずは、どのような罰則が存在するのかを正確に理解することが重要です。
青色申告承認の取消しによる税制優遇の喪失
電子帳簿保存法違反で最も深刻な影響の一つが、青色申告承認の取消しです。国税庁は、帳簿保存義務を適切に履行していない事業者に対して、状況に応じて青色申告の承認を取り消すことがあります。取消しが行われると、青色申告特別控除が受けられず、欠損金の繰越もできなくなるため注意が必要です。
青色申告承認が取り消されると、個人事業主は最大65万円の青色申告特別控除を受けられなくなります。法人の場合も、欠損金の繰越控除や各種特例措置を利用できなくなり、税負担が大幅に増加する可能性があります。
特に利益率の高い事業者にとって、この影響は経営に深刻なダメージを与える可能性があります。
会社法976条に基づく過料の適用
会社法976条では、会計帳簿の適切な保存を怠った法人に対して100万円以下の過料を科すと規定されています。電子帳簿保存法の要件を満たさない保存方法は、この過料の対象となる可能性があります。
企業にとって100万円の過料は決して軽視できない負担となり、資金繰りに影響を与える可能性があります。さらに、過料の適用は企業の法令遵守体制に問題があることを示すため、対外的な信用にも悪影響を及ぼします。
税務調査での不利な取扱いと重加算税
電子帳簿保存法に違反している場合、税務調査において不利な扱いを受ける可能性が高まります。適切な帳簿保存が行われていないと判断されると、帳簿の信頼性が疑問視され、より厳格な調査が実施される場合があります。
電子取引データの保存要件を満たしていない状況で、意図的な隠蔽や改ざんが疑われる場合、重加算税の対象となる可能性があります。重加算税は通常の追徴課税に加えて35%の税率が課されるため、税負担が大幅に増加します。
| 違反の種類 | 適用される罰則 | 影響の程度 |
|---|---|---|
| 帳簿保存義務違反 | 青色申告承認取消し | 税制優遇の完全喪失 |
| 会計帳簿保存違反 | 会社法976条過料 | 最大100万円の負担 |
| 意図的な隠蔽・改ざん | 重加算税 | 35%の追加税率 |
電子帳簿保存法違反による間接的なリスク
法的な罰則に加えて、電子帳簿保存法違反は企業活動や信用面において間接的なリスクをもたらします。これらのリスクは数値化が困難ですが、長期的には深刻な影響を与える可能性があります。
取引先との信頼関係悪化
電子帳簿保存法への対応状況は、企業のコンプライアンス意識を示す重要な指標として認識されています。適切な対応を怠っている企業は、取引先から法令遵守体制に問題があると判断される可能性があります。
大手企業では取引先選定の際にコンプライアンス体制を重視する傾向が強まっており、電子帳簿保存法への対応が不十分な企業との取引を見直す場合もあります。
また、監査法人や税理士事務所からの信頼も失墜する可能性があります。適切な帳簿管理体制が構築されていない企業に対しては、より厳格な監査や追加的な確認作業が必要となり、専門家との関係にも影響を与える場合があります。
金融機関からの評価低下
金融機関は融資審査において、企業の財務管理体制や法令遵守状況を重要な判断材料としています。電子帳簿保存法への対応が不適切な企業は、内部管理体制に問題があると評価される可能性があります。
融資条件の悪化や新規借入れの困難といった形で、資金調達面での制約を受ける可能性があります。特に中小企業にとって、金融機関との良好な関係は事業継続において不可欠な要素です。
近年、金融機関はESG経営の観点からもコンプライアンス体制を重視しており、法令違反のリスクがある企業への融資姿勢は慎重になっています。このような環境変化も踏まえ、適切な対応が求められます。
人材採用や企業価値への影響
法令遵守に問題のある企業は、優秀な人材の採用においても不利になる可能性があります。特に経理や財務担当者の採用では、適切な帳簿管理体制が整備されていることが重要な判断基準となります。
企業価値の観点からも、コンプライアンス体制の不備は投資家や株主からの評価を下げる要因となります。上場企業や上場準備企業にとって、このリスクは特に重要な考慮事項です。
| 影響を受ける分野 | 具体的なリスク | 対象となる関係者 |
|---|---|---|
| 取引関係 | 契約見直し・取引停止 | 既存・新規取引先 |
| 資金調達 | 融資条件悪化・審査厳格化 | 金融機関・投資家 |
| 人材確保 | 採用困難・離職率上昇 | 求職者・従業員 |
電子帳簿保存法の主要要件と違反回避のポイント
電子帳簿保存法違反を回避するためには、法的要件を正確に理解し、適切な対応体制を構築することが不可欠です。特に2024年以降の義務化内容と技術的要件について詳しく確認しましょう。
電子取引データの保存要件
2024年1月以降、電子取引データの電子保存が完全義務化されています。電子メールやEDI、インターネット経由で受け取った請求書や領収書などは、電子データのまま保存しなければなりません。
電子取引データは真実性と可視性の要件を満たして保存する必要があり、タイムスタンプの付与や訂正削除履歴の保存などが求められます。また、検索機能の確保も義務付けられており、取引年月日、取引金額、取引先名での検索が可能でなければなりません。
データの改ざん防止措置として、以下のいずれかの方法を採用する必要があります。タイムスタンプの付与、履歴が残るシステムでの保存、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程の整備などが選択肢として提示されています。
帳簿書類の電子保存における技術的要件
国税関係帳簿書類を電子保存する場合は、より厳格な技術的要件が適用されます。帳簿については、正規の簿記の原則に従って入力され、適時入力または業務処理後速やかな入力が必要です。
書類については、入力後の内容確認と承認体制の整備が求められます。また、定期的なバックアップやシステムの可用性確保も重要な要件です。
帳簿書類の電子保存では、税務調査時の可読性確保が特に重要であり、必要な機器やソフトウェアを常時使用可能な状態で維持する必要があります。システムの更新やバージョンアップの際も、過去データの可読性を維持することが求められます。
スキャナ保存制度の活用と注意点
紙で受け取った書類については、スキャナ保存制度を活用することで電子化が可能です。ただし、適切な解像度での読み取りやタイムスタンプの付与など、厳格な要件を満たす必要があります。
特に重要書類については、スキャン時の品質確認や承認プロセスの整備が不可欠です。また、原本の廃棄時期についても慎重な判断が求められます。
スキャナ保存を行う場合は、事前に税務署への届出が必要な場合があります。制度の詳細については、国税庁のガイドラインを参照し、専門家との相談も検討することが推奨されます。
効果的な電子帳簿保存法対策の実践方法
電子帳簿保存法への適切な対応には、システム面と運用面の両方からアプローチする必要があります。企業規模や業務実態に応じた実践的な対策方法を検討しましょう。
システム導入における選定基準
電子帳簿保存法対応システムを選定する際は、法的要件への適合性を最優先に検討する必要があります。特に、真実性確保のためのタイムスタンプ機能や、検索要件を満たす機能の有無を確認することが重要です。
システム選定では、将来の法改正への対応能力も重要な判断基準となり、ベンダーのサポート体制や更新頻度も考慮すべきポイントです。また、既存の会計システムや業務システムとの連携性も確認し、業務効率を損なわないシステム構成を検討する必要があります。
クラウド型とオンプレミス型のそれぞれにメリット・デメリットがあります。クラウド型は初期コストが抑えられ、法改正への対応が迅速ですが、データの管理権限やセキュリティ面での検討が必要です。オンプレミス型は自社でのデータ管理が可能ですが、システム維持費用や法改正対応のコストが発生します。
内部体制の整備と従業員教育
システム導入だけでは電子帳簿保存法への適切な対応は実現できません。従業員の理解度向上と適切な運用体制の構築が不可欠です。
まず、経理担当者だけでなく、電子取引に関わる全ての従業員が法的要件を理解する必要があります。特に営業担当者や購買担当者は、電子取引データの取り扱いについて正確な知識を身につけることが重要です。
定期的な社内研修の実施や、業務マニュアルの整備により、法令遵守意識の向上と適切な業務遂行を促進することができます。また、システムの操作方法だけでなく、なぜこの法律が存在するのかという背景も含めて教育することで、より効果的な定着が期待できます。
継続的な改善と監査体制の構築
電子帳簿保存法への対応は一度構築すれば終わりではありません。法改正への対応や業務プロセスの改善を継続的に行う体制が必要です。
内部監査機能の強化により、運用状況の定期的なチェックと問題点の早期発見が可能になります。また、外部専門家による定期的な点検も有効な手段です。
国税庁からの新しいガイドラインや通達に対する情報収集体制も整備する必要があります。税理士や公認会計士との定期的な情報交換や、業界団体からの情報収集により、最新の動向を把握し続けることが重要です。
まとめ
電子帳簿保存法の違反は、青色申告承認の取消しや過料といった直接的な罰則だけでなく、取引先との信頼関係や企業価値にも深刻な影響を与える可能性があります。特に2024年以降の完全義務化により、適切な対応がより重要になっています。
効果的な対策には、法的要件を満たすシステムの導入と、全社的な運用体制の構築が不可欠です。また、継続的な改善と最新情報への対応により、長期的な法令遵守体制を維持することが求められます。
電子帳簿保存法への適切な対応は、リスク回避だけでなく業務効率化や競争力向上にもつながる重要な取り組みです。早期の対策検討により、安心して事業活動を継続できる環境を整備していきましょう。
富士ソフトでは SAP Concur(コンカー)を用いて、お客様社内における運用体制構築を含めた電子帳簿保存法への対応のご支援を行った実績があります。
また、SAP Concur認定コンサルタントを含む100名以上のプロフェッショナルが、ライセンス契約から導入・アフターサポートまで、ワンストップパートナーとしてお客様のニーズに合わせた業務効率化のお手伝いをいたします。ぜひご相談ください。
富士ソフト Concur 導入サービス
SAP Concur(コンカー)は、出張・経費管理クラウドシステムです。
従業員の規模を問わず、日本をはじめ世界中で利用されています。
経費精算の全プロセスを自動化し、無駄な作業はすべてカット。経費精算業務を省力化することで、社内の生産性向上に役立ちます。
スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスにも対応し、場所を選ばず申請が可能で、200種類の分析レポートにより経費の使途を可視化することで経費の適正化やコスト削減につなげます。